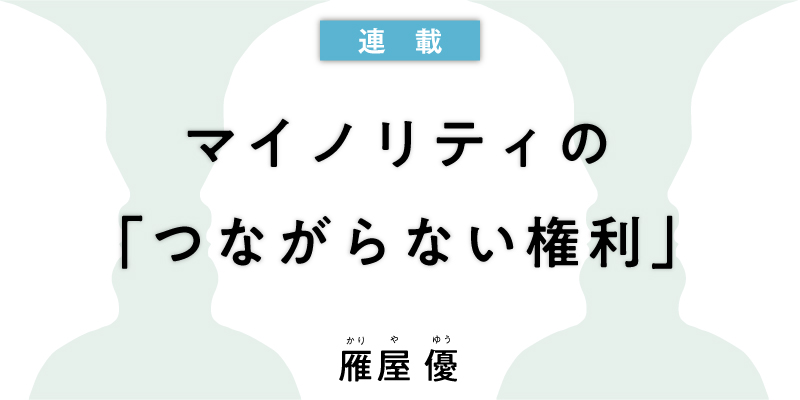解決編 1.当事者運動は社会に開かれなくてはならない
ここからは前回再定義したマイノリティの「つながらない権利」を実現するために欠かせない視点や要素を提案していく。まず私が提案したいのは、マイノリティ性のある人々、つまり当事者の運動が社会に開かれることだ。
マジョリティはふつうに生きていたら知るきっかけがない
「「つながらない権利」の話なのに、なぜ開くのか」と疑問に思った方も少なくないだろう。しかし、マイノリティの「つながらない権利」を獲得するためには当事者運動が社会に開かれなければならない。なぜなら、マイノリティの「つながらない権利」を阻害するものの一つに、マジョリティの無知があるからだ。
相羽さんのインタビューで出てきた、障害児の親が育児について研修を受けられる北欧の制度はそこをよく理解している。障害児の親が障害者とは限らない。障害者の文化も現実も何も知らない健常者が、ある日突然障害児の親になる。そういうことは何も珍しくない。
しかし、この社会でマジョリティとして生きていくのにマイノリティに関する知識はさほど必要ない。視覚障害者であっても白杖を扱えない私がいるくらいなのだから、マジョリティであれば、マイノリティ関連の知識がどれほど抜け落ちるかは想像に難くない。そして、マジョリティであり続ける限り、知らずとも困ることはない。これが特権である。
北欧ほどの手厚い研修はないものの、障害児の育児について、日本でも当事者団体や親の会が精力的に情報を発信している。それでも、親がマジョリティである限り、我が子がマイノリティ性ゆえにぶつかる困難を予期することも、理解することも、至難の業だ。親として努力を重ねていても、社会のなかで作られた常識は簡単には抜けてくれない。
進路選択への助言において、それが顕著に出てくる。親も自分の視点で助言をするが、その視点はマイノリティのことを知らなくても困らない社会で形作られたものだ。視覚障害者の職業としては三療(あんま、鍼、灸の総称)の道しかない、セクシュアルマイノリティといえば夜の仕事。そんな言葉が親から悪意もなく飛び出した経験は私も見聞きしている。
「つながらない権利」のために、開く
マイノリティのことを知らなくても困らないのではなく、当たり前にマイノリティが暮らしていることを実感できる社会でなくてはならない。それも、キーワードを知り検索しなくても、生活に情報が飛びこんでいくくらい、一般的なものになる必要がある。
とはいえ、点字ブロック、手話、車椅子などをまったくイメージできない人もいないだろう。ではそれらを使う暮らしとは、どういうものなのか。どこに困難があるのか。どんな風に余暇を楽しんでいるのか。どのように収入を得ているのか。その暮らしをイメージできるようになるにはどういう発信が必要なのだろうか。
地域づくりの文脈で使われる、「関係人口」という言葉がある。関係人口とは、その地域に住んでいるのでもなく、観光に来たのでもない、多様な方法で地域に関わっていく人々を指す。(参考:関係人口ポータルサイト 総務省)
また、企業組織の利害関係者を指す「ステークホルダー」も重要な言葉だ。単に消費者や顧客だけではなく、取引先や株主、行政機関、未来の顧客までを含む幅広い概念といえる。
当事者やその家族、支援者や政策決定者に向けた発信のみでなく、マイノリティの関係人口やステークホルダーを増やす発信ができないだろうか。これができれば、マジョリティとして生きていてもマイノリティの情報がある程度目に入り、親となっても子どものマイノリティ性を深く理解し的確な助言が可能になるのではないか。
また、関係人口やステークホルダーとなりうるのは、親となるかもしれない人々だけではない。人はマイノリティ性をどこかで持つリスクを抱えて生きているし、大切な人がマイノリティ性を抱えることもありうる。そう考えると、決して誰も関係のない話ではないのだ。
それなのに、当事者運動の向いている先の多くは当事者と家族、支援者、政策決定者だ。当事者運動は当事者の安全な場を作るためのものだからそれも当然だけれど、「視覚障害があるとどういう生活になるのかな」「聴覚過敏ってどういう状態なんだろう」とライトに興味を持った人がアクセスする手段は本当に少ない。
その人が未来の協力者になるかもしれないし、あるいは未来の当事者かもしれないのに。その視点が抜け落ちているように思えてならないのだ。
もちろん、人材や資金不足のために前述のような一般向けの発信にまで手が回らないこともあり、当事者運動だけではどうにもならない部分もある。けれど、現在の当事者、そして未来の当事者のためにマジョリティに向けた発信が必要だとする発想は持つべきだ。
視点を変えて、関係人口やステークホルダーを増やす
そうは言っても、マジョリティに興味を持ってもらうことは難しい。講習会や研修のような形式はある程度興味がないと行く勇気が出ない。何か入り口が必要だ。
入り口として、娯楽は一定の役割を果たしうると私は考える。
例えば、全盲の視覚障害者によるゲーム実況や全盲の芸人のInstagram、セクシュアルマイノリティのカップルチャンネル、マイノリティ性を取り扱った小説や漫画や映画がある。
私は視覚障害者としては見えている方だが、ゲームは下手だ。ゲーム内で移動を必要とするものでは毎回道に迷うし、戦闘では敵の動きに合わせて回避も攻撃もできない。晴眼者でも苦手な人はいる。視覚情報がほとんどのゲームを全盲の視覚障害者がどのようにやるのか、正直私も想像がつかないし、動画を視聴しても何が起きているかわからない。自身がゲーム下手だからか、全盲の視覚障害者によるゲーム実況と聞くと、興味をそそられる。
ものによっては偏見を助長してしまうこともあり、こういった発信がすべていいものとは言えない。発信する当事者によってコンテンツのクオリティもまちまちではある。しかし、ライトに興味がある人だけではなく、今までマイノリティのことを知らないで生きてきた人にも、実際にマイノリティが「いる」と示せる。これは大きい。
お盆と年末のコミケット主催団体が献血に寄与し表彰された話もあるが、そういった場に出ていって、目に入ること、そして接触の機会を作ることで、マイノリティが「いて当たり前」になる。
逆説的な話だが、閉じるためには開かれた状態も必要なのだ。