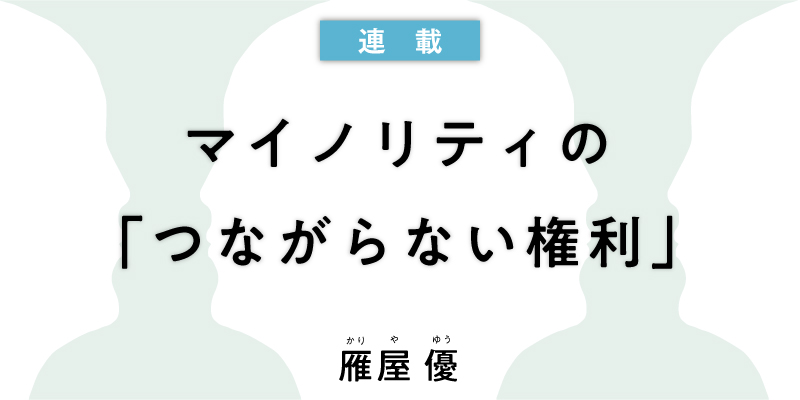番外編 私が「つながらない権利」を求めるまで~読書の旅を辿る~(2)
少しずつ、社会学に足を踏み入れる
物心ついたときからともにある遺伝疾患、アルビノに関するルポルタージュや社会学の観点からインタビュー調査を重ねた成果をまとめた書籍を通して、私は社会学にふれた。
読書により、社会学における「スティグマ」や障害の「社会モデル」と「個人(医学)モデル」についても理解を深めつつあったが、それでも生物学を専攻していた期間に培われた、「障害は身体機能の欠落を指す」「性別とは性染色体によって決定されるものでしかない」といった発想は、当時の私に根強く残っていた。
自然科学に携わる人間に社会学の発想が存在しないとまでは言わないが、自然科学を探究する人々が社会学と接する機会は少ない。当然の帰結として、障害学生支援やセクシュアルマイノリティへの理解において、社会学の視点は抜け落ちやすくなる。
そんな背景から、社会学に興味を持ちつつも、「今までの自分の行いを否定されるようで怖い」と怖気づいて、私は「社会学」と明確に書かれた書籍を手に取るには至らなかった。
自身のセクシュアリティや障害といったマイノリティ性に向き合っていくなかで、その迷いを言葉にし始めたのが、私の文筆活動のはじまりだ。自分の迷いやもやもやを書き連ねようにも、特にジェンダーの分野において、私には適切な言葉がなかった。
外から見ると、セクシュアリティに関する言葉がごちゃまぜになっているかのように見える時期であったことも一因ではあるだろう。しかし、自身の「男でも女でもない」「恋愛をしないし、他人に性的に惹かれない」特性をどう呼び表すべきかもわからずに混乱した。
そんなときに、『はじめてのジェンダー論』(加藤秀一著、有斐閣、2017年)を勧められて手に取った。
この本は、読み物としてもおもしろいだけでなく、章の最後に小さなワークや読書案内があるので、本の内容より先に学びを深めていくこともできるしくみになっている。
読み進めていくうちに、私のジェンダーの問題についての理解がいかに浅かったか、痛感した。この本は身近な事例を取り上げつつ、ジェンダーを取り巻く多くの問題の理解へと導いてくれた。
性別役割分業、性決定、トランスジェンダー、リプロダクティブ・ヘルス・ライツなど、さまざまな問題の語られ方にひそむ差別的な構造を解き明かすけれど、語り口は優しく、難しいことをわかりやすく説明してくれており、決して怖い本ではない。
私自身、他人に面と向かって「あなたは差別主義者だ」と言ってしまいたいことは日常的に多くある。でも、そんな私も「あなたのしていることは差別である」と断じられるのは怖い。大急ぎで謝って、その場を去ってしまいたくなる。恥ずべきことをしたと知りながら、そこに留まる勇気はない。
もちろんそのような態度を「深く反省して恥じるあまり去った」と取るか、「自分かわいさに対話を放棄した」と取るかは人それぞれで、それまで築いてきた関係性次第だ。どんなときも去るべきであるともいえないし、逆に、どんなときもその場に留まり対話するべきであるともいえない。
そういう意味で、この本は怖くない。差別構造に加担していることを責められるのではなく、考えてみるきっかけをもらえる。この本においては、どのように差別が生まれていて、それはなぜいけないのかが論理的に、非常に魅力的な理屈っぽさで語られているからだ。
この理屈っぽさが、他人に共感しにくい私にはとても合っていた。それに、論理的な伝え方は、トランスジェンダー差別や女性差別のひどさを知っても、「自分はその属性ではないから関係ない」と一蹴できてしまう人々にも届くように思えた。
大学で教科書として使われることを想定しているシリーズの一冊だけあって、言葉は易しいけれど、中身は深い。
メディアがジェンダー観に与える影響について書かれた箇所は、執筆活動の幅を広げようとしていた当時の私に、背筋の伸びる思いを抱かせた。
考え方の基礎やジェンダーを語る際の言葉を手に入れてからしばらくのことだ。SNSで話題になった本があった。『ふれる社会学』(ケイン樹里安、上原健太郎編著、北樹出版、2019年)だ。
『はじめてのジェンダー論』を何度も読み返し、社会学への苦手意識が薄れた頃でもあり、読みやすさや扱っているテーマへの評価もよかったので、読んでみることにした。
こちらも大学の教科書として使われることを想定している書籍だが、いい意味で衝撃的だった。『ふれる社会学』はスマホの話から始まるのだが、ふるまいやコミュニケーション、メディアとしてのスマホ、身体性の話をしている。身体性については、これまでに読んだ本でも目にしていたが、正直よくわからなかった。それが、身近にあるスマホを介した話を読むことで、劇的にわかりやすくなった。
各章は最後の章を除き、その章にちなんだ写真から始まる。「こんな風景、見覚えがある」と思うところから、文章に入っていける。写真の解説から入る章もあれば、章を読み終えた後だと写真が違って見える章もある。
分担執筆で書かれており、それぞれの執筆者の人となりが見えるのも大きな特徴だ。
さまざまなところに入り口を開く工夫がされ、社会学の入り口はすぐそこにあったのだと『ふれる社会学』は教えてくれる。社会学は怖いものではなく、人生を豊かにする視点なのだ。
単に「差別はいけない」と言うのではなく、差別の構造や背景を知った上で、差別を否定することが大切だと社会学を扱った書籍に教わった。
社会学を学んでいくことは、私にとって、傷が癒やされることであり、傷を自覚することでもあった。