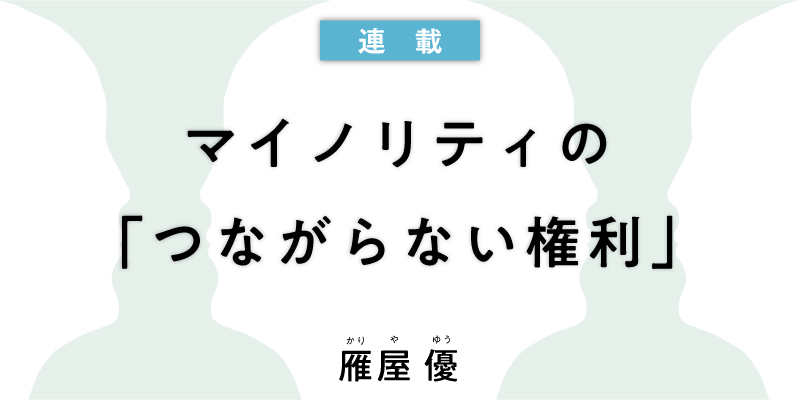問題提起編 1. 当事者コミュニティに参加できない/したくない理由(3)
マイノリティ性が“剥がれる”ことへの恐怖
前回までは、自分が当事者であることを受け入れられない、そもそもアクセスの面で困難があるといった点から、当事者コミュニティのみが当事者の抱える問題の解決を担うのには無理があると論じてきた。この2点は、比較的理解が容易なものだろう。しかし、今回の話は、自身のマイノリティ性を強く意識する生活をしていない方には想像しにくいものかもしれない。
当事者コミュニティに参加し、当事者と交流することに抵抗が生じる理由の一つとして、私は、マイノリティ性が“剥がれる”恐怖を挙げたい。
マイノリティ性が“剥がれる”とはどういうことか、私の経験を例に説明していく。
私は、色素が薄く生まれる遺伝疾患、アルビノ(眼皮膚白皮症として平成30年に指定難病にもなっている)の当事者だ。アルビノは色素が薄いために、弱視を伴うことがある。私も例に漏れず、弱視がある。それも、矯正が効きにくい上に、乱視や眼振、羞明(しゅうめい:眩しさを強く感じること)を併せ持つ弱視だ。単に視力の数値だけで想像できる見え方ではない。眼鏡ユーザーは年齢が上がるごとに周囲に増えていったが、眼鏡ユーザーたちの言うことも、見えにくさのメカニズムも、何一つ私と一致しなかった。
私は視覚特別支援学校や弱視学級に通わなかったため、家でも学校でもマイノリティとして生きてきた。それはある意味では苦難であり、ある意味では守られていたと言える。
指定難病となっているだけあって、アルビノの人々は少ない。難病情報センターのサイトによれば、国内に約5,000人と推定されている。視覚特別支援学校や弱視学級にアクセスしない日常生活を送っていて、偶然にアルビノ当事者同士が出会うことは考えにくい。
事実、私も、週に一度しかその病院で診察を行っていない眼科の主治医の待合室で出会うまで、他の当事者を見たことすらなかった。眼科の主治医の診察時間が限られていなかったら、起こりえない出会いだったかもしれない。
そういった状況だから、私が料理できないことも、運動が苦手なことも、手先が不器用なことも、私の苦手なことは全部、アルビノによる弱視で説明された。今思えば、発達障害の一つ、ASD(自閉スペクトラム症)に関係していることもいくらかあるのだろうが、ASDの診断をもらうのは成人後なので、未成年だった頃に周囲がそう判断したのも無理はない。
私が何かに失敗し続けると、親や教師は「やっぱり見えないとこれは難しいよね」と納得し、それを免除してくれる。その流れに慣れきってしまい、私自身も、自分のできないことは大体アルビノによる弱視が原因だと考えるようになった。
月日は流れ、大人になった私はアルビノや視覚障害者のコミュニティに顔を出すようになった。生来コミュニケーションは得意ではないため、上手くやれないのではないかと不安に思ってはいたが、「行ってみて居心地が悪かったら去ればいいや」と多少強引に自分を納得させて、参加したのだ。コミュニケーションへの不安よりも、他の当事者への興味が勝ったのかもしれない。何せ、今まで当事者に出会ったことがほとんどなかったのだ。
しかし、そこにあったのは予期していなかった恐怖だった。コミュニティで話し、勧められた関連書籍を読んでいるうちに、自分の今まで信じていたものが崩壊する感覚を味わった。
パラリンピックに出場する、アルビノや視覚障害のある人々。「全盲だけど、料理できるよ」と話す人。アルビノによる弱視ゆえに私が選択肢から外した職業で活躍する人々。
他の当事者と交流しなければ、私はずっと運動も料理も、アルビノによる弱視があるからできないのだと思っていられた。自分の努力不足や適切な方法を見つけられていないのではなく、自分の身体機能の問題だと、何の疑いもなく信じることは、もうできなくなってしまった。マイノリティ性が、“剥がれ落ちた”瞬間だった。
それは、ある意味では希望であり、またある意味では絶望だった。自分もやり方を変えればできることが増えるかもしれないと捉えれば希望だが、今まで自分がマイノリティ性のせいにして自分を甘やかしていたために現在のできなさがあると思えば絶望でしかない。
晴眼者(視覚障害のない人)から責められたところで、「あなたは見えるじゃないか」といくらでも反論できた。元々スタートラインが違うじゃないか、と。しかし、当事者からは責められるまでもなく、自分の足りていなさはマイノリティ性だけが原因でないと示されてしまう。
恐怖だった。得意な分野ではマイノリティ性のことなどほとんど考えずにできることを増やしていった私だが、苦手な分野はマイノリティ性のせいにしてきたことは事実だった。それをまざまざと見せつけられる。足場が崩れ落ちる感覚とでも言うべきそれは、劣等感だった。
しばらくは、これが自分だけの感覚なのかもしれないと考えていたが、前述のような構造に言及したり、私に劣等感をぶつけてきたりする当事者たちから、自分だけがそう感じるのではないと知った。
私が劣等感を抱くと同時に、誰かに劣等感を抱かれている可能性は十分にあったのだ。
「他人と比べることなく、自分の価値を見つけましょう」と言われるようになって久しい。しかし、人間は相対的評価から逃れられない。
あの人にはパートナーがいる。自分はパートナーを望んでいるのに、パートナーがいない。
同僚は営業成績が自分よりいい。
試験に受かる人がいれば、落ちる人がいる。
社会において、マイノリティ性が自分のイメージの多くを占めている際には、マイノリティ性に理由を求めることが可能だ。しかし、当事者と交流し、マイノリティ性が“剥がれる”と、そうはいかない。それ以外の要因があることを、直視させられるのだ。
日常では、マイノリティであるがゆえに困難があり、さらに当事者との交流で、マイノリティ性が“剥がれ落ち”、マイノリティ性を除いた部分の足りなさに向き合わされる。
その苦しみは、想像を絶するものだろう。
もし私がそのリスクに早々に気づいていたら、それでも当事者コミュニティに顔を出したと言い切れる自信がない。正直なところ、今でもその恐怖は消えていない。
このようなことから、当事者コミュニティに参加するのを躊躇する理由の一つとして、マイノリティ性が“剥がれる”恐怖がありうると、私は考える。