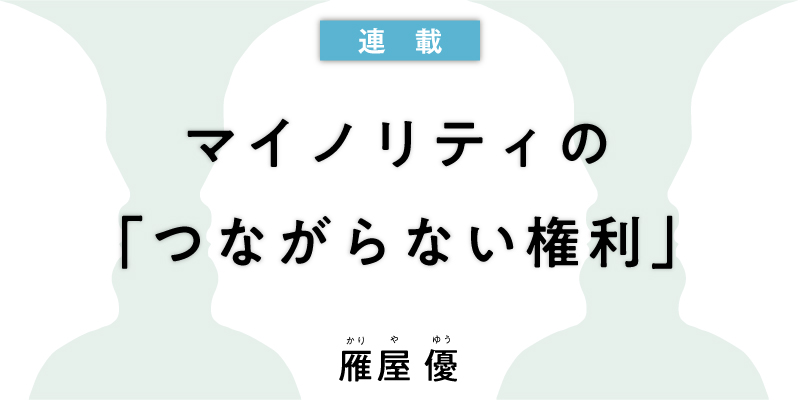問題提起編 2.当事者コミュニティの功罪(5)
ロールモデルに出会い、先のことを考えられる
「ロールモデルがいない」とは、マイノリティに関する問題点として、よく挙げられることだ。
ロールモデルと聞いても、馴染みがない方もいると思うので、説明する。ロールモデルとは、考え方、働き方、生き方などが他者の規範となる人のことを指す。女性活躍の文脈でも、「女性で管理職や幹部になった人がいない会社では、女性社員のロールモデルがいないため、女性社員のキャリア形成が難しい」などのように使われる言葉だ。
ロールモデルの不在は、女性社員だけの話ではない。ありとあらゆるマイノリティ――セクシュアルマイノリティ、障害者、ミックスルーツの人々など――の、共通の課題ともいえる。
マイノリティである以上、保護者をはじめとした周囲の大人の話は参考にならないことが多い。このような話には、私も覚えがある。中高生の頃、私と共通するマイノリティ性を持たない保護者、教員、その他の大人の語る“将来”は、私のマイノリティ性を正確に考慮できていなかったのだ。「あれもこれもできないだろう」と過小評価されたり、「頑張ればできるでしょう」と根拠のない励ましをされたりした。その結果、私は将来を適切に思い描くのに苦労した。
自分と同じようなマイノリティ性があり、経済的に自立している人に出会い、話す機会は、若いマイノリティの今後を左右する大事なものだ。そういった機会の多くが、当事者コミュニティで得られるものとなっている。
本を出しているマイノリティもいるが、そのなかで「ロールモデルにしたい」と思えるような人がどれほどいるかは疑問だと思う。私も一時期そのような本を図書館で読み漁ったのでわかるが、とてもではないが、「この人みたいなことが私にもできそう」とは思えなかった。
本を出しているマイノリティの代表格として、私が記憶している乙武洋匡氏の著書についてもそうだ。『五体不満足』(講談社、1998年)は、読んでいておもしろく、思いもよらない方法でさまざまなことをしていく乙武さんのエピソードに驚かされた。それでも、「乙武さんのようになりたい」とも「なれそう」とも思うことはできなかった。
本に出てくるマイノリティは機会や環境に恵まれている、「特別な人」ばかりに思えた。
私がそのような本を読み漁っていた時期は十年以上前なので、今は事情も変わってきているのかもしれない。現在では、『見た目が気になる 「からだ」の悩みを解きほぐす26のヒント』(河出書房新社編、2021年)のような本もあり、職業ややっていることは特殊だが、今までの本を出すマイノリティよりはぐっと近くに感じられる人の文章が載っている。
しかし、本を一冊書き表せるような人が、突出した何かを持っていることは否定できるわけもない。
そういう「特別な人」の話を読んだり聞いたりするのも、それはそれで楽しいし、意義のあることだ。でも、その人達がロールモデルになりうるかは、また別の問題だ。
かくいう私もおそらくロールモデルにはなりえない。アルビノによる弱視での、見え方の不利を、自身の発達障害ゆえの高い言語性IQや先取り学習で補ってきた部分がある。私の方法は、アルビノ当事者にも、発達障害当事者にも、「参考にならない」と言われるだろう。職業の意味でも、「雁屋さんはちょっと参考にならないかな」と言われたことがある。否定できる根拠は持ち合わせていなかった。編集プロダクションや制作会社での経験も、正規雇用の経験もなしに、個人事業主として文筆業を始めるのは、無謀と判断されて当然の行動だ。他人のロールモデルになど、なれやしない。
ロールモデルの不在は、深刻な問題だ。将来像を適切に描けないと、現在の学習や進学、それから収入を得ることに向けてどう動いていくべきかもわからず、モチベーションも下がってしまう。
当事者コミュニティには、「特別ではない」マイノリティも集まってくる。
そこでの話は、「本を書き上げました」「取材を受けました」といった特殊な経験だけではなく、「会社で必要な資格を取りました」「転職しました」のような日常にある、現実的であり、生きていくのに欠かせないものになる。
こういった話に、どれほど安心できるだろう。
メディアには、「特別」なマイノリティ表象が溢れ、本で読むマイノリティもやはりどこか突出している。人一倍の努力をして、何かに突出して特別になって初めて、マイノリティであることを許されるような気さえする。
そんな気持ちを解きほぐし、現実的な将来を思い描くきっかけとなる話を聞くことができる機会は、貴重だ。
何かで突出するだけがマイノリティの生きる道ではなく、手段を工夫したり、向いていることを見つけたりして、「特別」ではないけれど、幸せを感じられる日々を過ごしていける。そのような道があることを、先を行く人々の生の言葉で聞けることは、進路や将来設計を左右する大事な機会となるのだ。