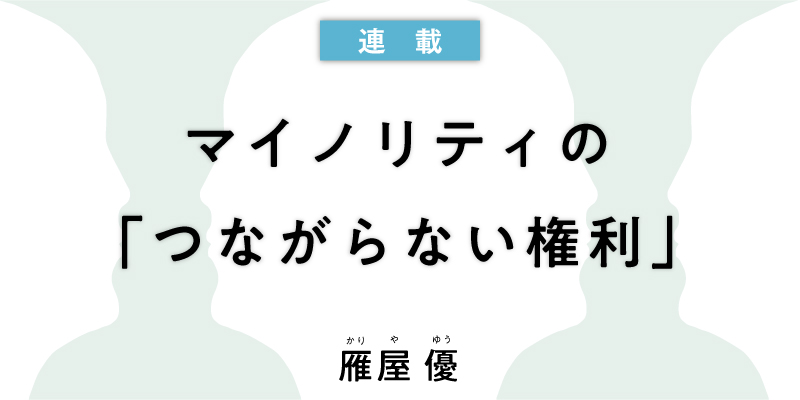問題提起編 2.当事者コミュニティの功罪(9)
コミュニケーションの得手不得手からは、逃れられない
これまでも書いてきた通り、私はコミュニケーションを苦手としている。仕事における情報伝達は問題なく行える。しかし、特に目的もなく、強いて言うなら、心を通わせ、仲良くなることが目的とされるようなシーンでは、どうしていいかわからない。
どうしていいかわからないから、黙る。何を言えばいいかわからず、話しかけられては動揺し、ちぐはぐな答えを返す。
当事者コミュニティでの交流は、仕事ではない。仲良くなろうとするためのあまり強い目的のないコミュニケーションは、私の苦手とするところそのものなのだ。
共通するマイノリティ性を持つ当事者同士だからといって、出会えば魔法のように仲良くなれるわけではない。仲良くなるには、やはり通常の手順を踏まねばならない。
誰かと仲良くなるために、適切な手順を踏むことも、私の苦手なことの一つだ。仲良くなりたいと思うことがあっても、どうしたらいいかわからなくて、諦めた経験は数多くある。
コミュニケーション、特に対面コミュニケーションが下手なのは、発達障害の一つ、自閉スペクトラム症(ASD)の特性によるものだろう。ASDのコミュニケーションに関する特性として、表情や身振りなどの非言語コミュニケーションを理解しにくいこと、言葉を文字通り受け取ってしまい、言外の意味には気づきにくいことなどが挙げられる。
音声通話のみのコミュニケーションにおいて、私のコミュニケーショントラブルがぐっと減ったのは、非言語コミュニケーションの要素が少なくなり、顔が見えない分、お互いに言葉を文字通りの意味で使うようになるからなのかもしれない。
それからSlackなどを用いたテキストコミュニケーションも、割とうまくいく。文字でしか伝わらないツールだから、非言語コミュニケーションが読み取れなくても、さほど困らない。言外の意味を含ませるのも、業務効率化のためにはいいことではない。
私にとってどうにもならないのは、対面コミュニケーションだ。
当事者コミュニティの多くは、その対面コミュニケーションを大事にしている。対面しているからこそ言えることもあるのは、身に染みてわかっているので、それは悪くない。
新型コロナウイルスの感染拡大を経て、オンラインでの交流会や音声通話(ClubhouseやTwitterのスペースなど)を利用したカジュアルな交流が行われるようになり、当事者コミュニティにおいても、コミュニケーション手段の選択肢ができたことは喜ばしい。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大が終息すれば、元通りになってしまう不安も拭いきれない。音声のみだから、テキストのみだから、話せた人々が、当事者コミュニティの対面重視への回帰により、ニーズを満たせなくなってしまうとしたら、それは問題だ。
多くのコミュニケーション手段を用意できたところで、コミュニケーションが上手くないと自認している人々が、「結局、コミュニケーションか……」と落胆し、去っていく可能性はゼロにはならない。
しかし、コミュニケーション手段がいくつかあれば、「これなら自分もできるかもしれない」と参加し、ニーズを満たしていく人も増えるだろう。
先ほども少し書いたが、発達障害にはコミュニケーションを苦手とする特性がいくつかある。非言語コミュニケーションの不得手、言外の意味を理解しにくいことに加え、喋りすぎてしまう、または、喋ることを考えているうちに会話が進んでいって何も言えない、など、多種多様だ。
発達障害当事者以外にも、過去の経験などからコミュニケーションを苦手としている人もいるだろう。
それでも、当事者コミュニティの場では、コミュニケーションから逃れられない。でも、当事者コミュニティを運営しているのは、当事者やその関係者が多く、心理学やコミュニケーションスキルの専門家に出会うことは少ない。
そのなかで心理的安全性の高い場作りをしようとすると、運営やコミュニケーションスキルの高い参加者に、場を調整する負担が集中する。そして、運営側やコミュニケーションスキルの高い参加者が疲弊していく。
私もそのような場にいたことがあるが、「あの人に負担をかけているだろうな」と思いつつ、自分自身の緊張をほぐすのに手一杯であり、またどうすれば助けになるかも、皆目見当がつかなかった。それがわかれば、コミュニケーションの不得手も克服できているだろうから、わからないのも、無理はない。
コミュニケーションの苦手さが、当事者コミュニティの内でも外でも大きく影響する。そんな社会を生きている。
せめて、当事者コミュニティのなかだけでも、コミュニケーションの得手不得手から逃れられる場所にできないだろうか。
コミュニケーションが苦手な当事者のニーズを満たす方法を、考えていく必要がある。コミュニケーションが不得手な人を置き去りにしないために、私達に何ができるだろうか。