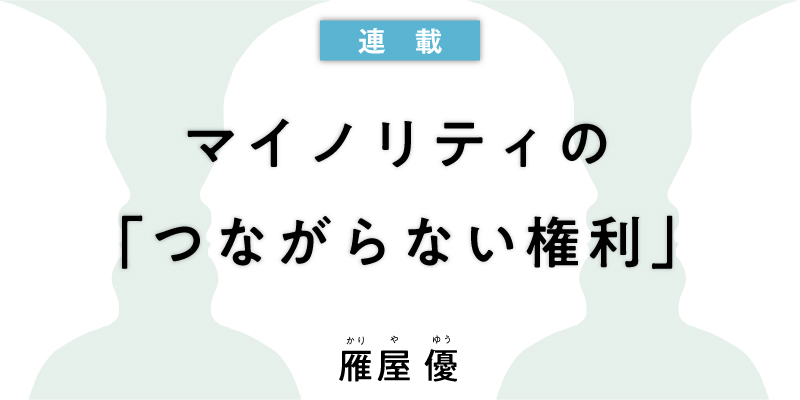番外編 私が「つながらない権利」を求めるまで~読書の旅を辿る~(6)
マイノリティだからこそコミュニケーションを要請される「しんどさ」を言葉にしていく
受験や進学に伴い、私は事前の面談や書類での申請を行う必要があった。視覚障害があること、日焼けに弱いこと、容姿が特殊であることについての説明をし、先方から対応の提案を受け、協議し、合意する。
その過程を経てようやく、目的である受験や進学が可能となる。
学生をしていた頃は、仕方のないことだと思っていた。自分には障害があるのだから、説明して、対応を求める必要がある、と認識していた。
しかし、社会学や障害学にふれていくにつれ、「仕方なくないのではないか」と疑問が出てくる。
合理的配慮の申請に際し、医師の診断書や意見書を求められることは珍しくない。病院へ行ってその手続をするのも、保険適用外になる文書代を支払うのも、私や私の保護者だ。
郵送や電話、メールでの先方とのやり取りも、時間と体力を奪っていく。合理的配慮を必要としない受験生は受験勉強に使える労力を、私は合理的配慮を得るために使わなくてはならない。
個別の事情は誰にでもある。けれど、マイノリティの側に負担が偏るのであれば、それは、不平等ではないか。
それに加え、マイノリティは学校や雇用主のような管理者に合理的配慮を要請するだけでなく、同級生や同僚など、周囲の人々に「適切に」サポートを依頼するコミュニケーションを「強いられる」ケースがある。
教員や雇用主にそのようなコミュニケーションを命じられることもあるが、そうせざるを得ない環境であるがゆえに仕方なく行うこともある。
合理的配慮の申請時だけでなく、日常のシーンでサポートを依頼するのにも、コミュニケーションがいる。しかもそれは、マイノリティ性のカミングアウトを含んでしまう。言わなければ、合理的配慮やサポートは受けられない。学業や仕事に支障が出るから、言うしかない。
ニーズの表明が合理的配慮の前提となっていることへの批判をはじめ、障害の社会モデルをよりうまく使っていくために書かれた書籍『「社会」を扱う新たなモード』(飯野由里子/星加良司/西倉実季著、生活書院、2022年)には、現状を疑い、よりよくしていく方策を考える視点を強化してもらった。
障害の社会モデルは大切な概念だが、大事なのはその使い方である。隙あらば社会の責任を小さく、マイノリティの責任や努力の範囲を大きくしようとしてくるこの社会に抗い続けるために欠かせないことを、本書からたくさん教わった。
障害の社会モデルは、思っているよりもずっと深くて、差別をなくすために有効な概念なのだ。そのことを、改めて胸に刻んだ。
障害の社会モデルを扱う上で、『障害社会学という視座』(榊原賢二郎編著、新曜社、2019年)も読んでみてほしい。
具体的な事例のないままに、「障害を社会モデルで捉えよう」と言われても、それだけでは実践に結びつきにくい。どのように社会モデルを使っていくのか、事例をどう捉えるのかは、具体的な事例を元に考える機会によって養われるものだ。
本書は6人の研究者の分担執筆、それらをまとめる編集によって成立している。髪がない女性の生きづらさ、発達障害に対するSST(ソーシャル・スキル・トレーニング)、知的障害者の親との離れがたさ、障害者スポーツ、ALSから考える進行していく病について、吃音について、とそれぞれの章で焦点を当てられていることが大きく異なっている。
読者にある程度障害への知識がある(吃音やALSを大まかにでも知っている状態)のであれば、本書は視野を広げる契機になる。
例えば、私は、執筆者の一人、吉村さやかさんの「1章 「女性に髪の毛がないこと」とは、どのような「障害」なのか」を読むために本書を購入している。他の章で取り上げられているトピックについては、「せっかく本を買ったのだから読んでみよう」と思って読み進めたのが正直なところだ。
これがいい出会いとなった。大まかにしか知らなかったことが、事例とともに書かれた研究者の文章によって、より細やかな事象となって浮かんできた。
発達障害支援の一環として行われるSSTをはじめ、こんなにも身近に、障害の社会モデル、そして障害について考えるきっかけはあった。私はつい日常をぼんやりと過ごしてしまいがちだが、少しずつでも観察し、考えられるようになろうと決意した。
マイノリティだからこそ、何かを強いられる。機会が平等でない。
それを差別という。
それなら、情報や合理的配慮、サポートなど生存に必要なものを得るために、マイノリティがコミュニケーションを強いられることは、不平等だろう。
マイノリティでなければ、インターネットで検索することで、大抵の情報を得られるのに、マイノリティはそうはいかない。
マイノリティであるがゆえに、生存のために、マジョリティよりもずっと強固に、コミュニケーションからの逃避を許されない。
情報は溢れている。ただし、マイノリティのことは想定されていない。
そんな現状が、マイノリティをコミュニケーションから逃さないのだ。