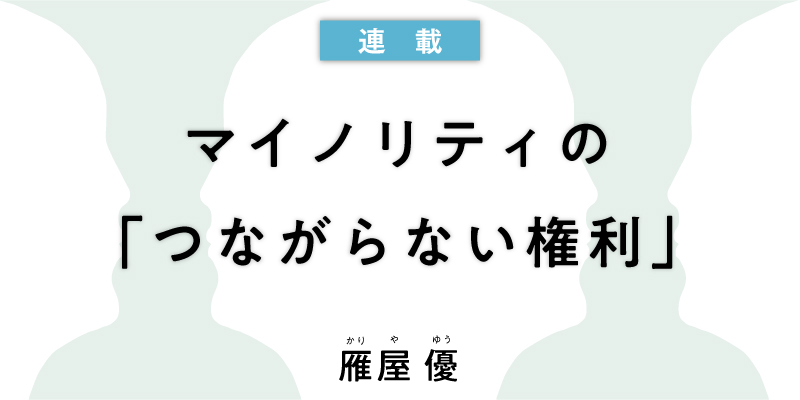番外編 私が「つながらない権利」を求めるまで~読書の旅を辿る~(5)
多くの言葉を借りながら、自身の希望や適性を見極めていく
私が自身の適性を知るのには、多くの時間を要した。発達障害の診断が出てから5年もの月日が経った今も、自身の感覚や思考が定型発達の人々と比較してどのように“特異”であるのかを完璧に説明できる自信はない。
それでも、病院での診察やカウンセリング、読書を通して、その骨格を描き出せるようになった。
障害に関する情報を集めるようになって、頻繁に目にしたのが、「当事者研究」なる言葉だった。
当事者研究について調べれば調べるほど、当事者が他の当事者とともに自身に起きている課題や困りごとを言語化していくことへの疑問は深まっていった。
障害者運動のなかで、「私たちのことを私たち抜きに決めないで」というフレーズがあり、それには頷けた私も、当事者研究にはどうにも納得できなかった。
それは、コントロール群があり、再現性があることが前提とされる自然科学をバックグラウンドとしている私には、当事者研究のあいまいさは、薄氷の上を歩くような怖さを秘めていると映ったからかもしれないし、この概念を受け入れれば、誰かと「つながる」必要性を認めなければならないという危機感だったかもしれない。
とはいえ、他人の記述から学べることは多いだろうと思い、『発達障害当事者研究』(綾屋紗月・熊谷晋一郎著、医学書院、2008年)を開いてみた。
わかったのは、他人の感覚はわからないという、至極当たり前のことだった。
著者の一人、綾屋紗月さんは私と同じ発達障害の一つ、ASD(本書のなかではアスペルガー症候群と書かれている)の診断を受けているが、その感覚の多くは私にはわからないものだった。
私の世界で、モノが語り出すことはない。
食事をしたいか、何を食べたいかに困惑する事態は、私には縁遠いものだ。どうすべきか、ルーティンを作ってしまいさえすれば、私はそれに従って手を動かし、消化器官も機能する。
声を出すことに困難を感じることはないではないが、その代わりに使うものは手話ではない。私はアルビノゆえの弱視のせいか、認知特性のせいか、手話を「何か手が動いている」としか認識できない。声の代わりには程遠い。
それでも、「これは知っている」と思う話もあった。疲労がわからないことに悩むこともあった私には、「1章 体の内側の声を聞く」に書かれていることの一部がそれだった。
同じ障害の診断を持っていても、感覚は違っている。わかる/わからないのなかで、私は当事者間の差異を改めてしっかり認識できた。
『つながり過ぎないでいい』(尹雄大著、亜紀書房、2022年)は、つながることから逃げたくてたまらなかった頃にタイトルを見て即座に購入した書籍だ。
発達障害をテーマにしているが、言葉やコミュニケーションをめぐる思考が綴られており、私にはとても興味深かった。コミュニケーションの話題といえば、とにかく、「つながりましょう」「他者とうまくつながるには」に終始するのに、著者の尹雄大さんは、「滑らかにコミュニケーションできる」ことに疑問を抱く。
今まで他者に感じてきた謎が少し解き明かされる本だった。
同時に、コミュニケーションが上手ではないことを、他者から、弱みとしてではなく、強みとして評価されうるのではないか、とも思えた。
コミュニケーションが怖い、逃げたいと思う私にとって、この本は柔らかく受け止めてくれる存在だった。「逃げてはいけない」と思えば思うほど、コミュニケーションを行うのに必要なエネルギーは多くなっていく、そんな時期の私には欠かせない視点をもらえた。
この社会には、やらないといけない(と思われている)ことが多過ぎる。家事、育児、仕事、他者との交流……。こうもやることが多くては、真にやりたいことに没頭する時間が足りない。まして、私のように疲れやすければ、なおのことだ。
そんな風に考えていたので、『「しなくていいこと」を決めると、人生が一気にラクになる』(本田秀夫著、ダイヤモンド社、2021年)はさらに思考を解き放ってくれる存在となった。
本書は、発達障害についての著書を多く出しており、発達障害について知りたい人々の間では有名な著者が書いているのだが、タイトルからもわかる通り、発達障害傾向のある人々を含めた、生きづらさを抱える人々に向けて書かれている。
この発想が、私には目から鱗だった。
障害、つまり医師によって健常者と何らかの差異があると診断された状態でしか、配慮や支援は受けられないと思ってきたからだった。それは、私を取り巻く制度がそうできていたからこそ生まれた思いこみなのだが、この思いこみは非常に危うい。
それは、発達障害傾向はあるけれども診断には至らない、「発達障害グレーゾーン」の人々や、片目を失明しているけれど、もう片方は見えているからと視覚障害者として認められない人々への合理的配慮や支援を、診断がないから不要と判断しかねないものだ。
本書はそんな思いこみとは真逆の発想で書かれており、発達障害の診断があろうとなかろうと、しなければいけないことは、本当にそんなにたくさんあるのだろうか、と問いかけてくれる。
自分に合ったやり方で自分の能力を活かせるように考えていこう。そんな優しくも力強いメッセージに溢れた本だった。
自分と他人は違う。
同じ部分はあっても、完全に一致はしない。
それゆえに言葉にする必要を感じつつも、コミュニケーションからは逃げたくなる。
でも、言葉にする必要を感じていることと、コミュニケーションから逃げたいことは、本当に矛盾しているのだろうか。
そんなことを考えながら、読書の旅を続けていった。