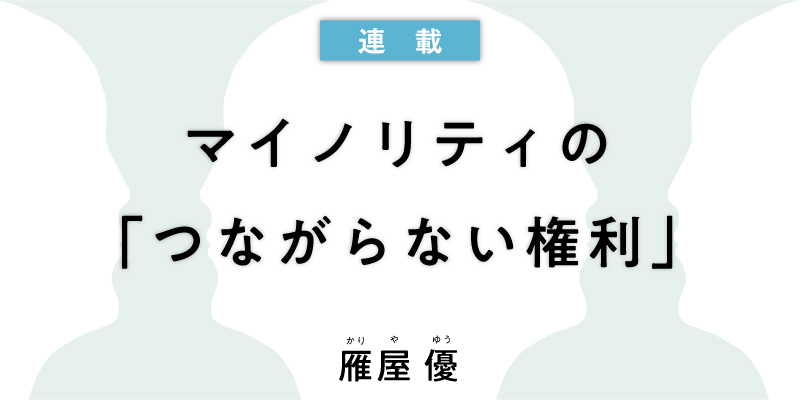問題提起編 2. 当事者コミュニティの功罪(1)
仲間に出会い、一人じゃないと思える
当事者コミュニティにつながった人がよく言う言葉として、「一人じゃないと思って、安心した」というのがある。おそらく、私はその言葉を実感できていない。今まで生きてきて、「一人じゃない」と思った瞬間が思い当たらないからだ。当事者コミュニティにいても、学校にいても、ライターの仕事をしていても、孤独は常にそこにあり、それこそが私の安寧だった。「自分は誰とも同じじゃない」と自覚しており、常にやりづらさを抱えているのも、また事実だ。このやりづらさについては、後の回で書くことにする。
しかし、実感はなくとも、構造を知り、理解を深めることはできる。
まず、マイノリティの人々は数が少ない。言葉遊びではなく、実際にそうなのだ。例えば、アルビノの人は日本国内に約5,000人いるとされている。(参考:難病情報センター)約1億2,000万人とされている日本の人口を考えれば、その状態で、約5,000人しかいないアルビノの人同士が自然に出会うことはかなりの難易度であると想像できるだろう。
そして、マイノリティの人々は、マイノリティ性をオープンにしないこともある。前述のアルビノも手間はかかるが、頑張ればある程度隠すことは可能だし、深く付き合わなければ、発達障害や精神疾患を隠すこともできる。
見た目に症状のある人が直面する差別などの問題、「見た目問題」に関連しても、症状を隠したい人が隠す手段として、手術やカバーメイクが挙げられている。なお、「見た目問題」の症状に関する手術は、見た目以外にも機能的な問題を抱えているために行われる場合が存在する。
そして、聴覚障害や視覚障害をはじめとした身体障害も、インターネットを介するなどして、関わり方を工夫すれば、障害を知られずに関係性を築くことができる。直接会わないからこそ障害を隠しきれる側面は、たしかにある。
マイノリティ性や相手との距離感、関わり方次第では、マイノリティ性を隠せるのだ。
マイノリティ性を隠すことで、自分を「ふつう」に見せて、マイノリティへの迫害や差別的な発言を避けることができる。マイノリティ性を隠すのは、当事者にとって攻撃から身を守るための手段だ。それなりにコストがかかるし、疲れもするのだが、それで得られる安心もある。隠すかどうかは本人が決めることであり、周囲に強要されるのは違うと書き添えておく。
しかし、数の少なさから元々出会いにくい上に、マイノリティ性を隠している人もいるとなれば、生活していて偶然に出会うことへの期待はますます低くなる。
そうなれば、当事者が「世界で自分ただ一人が変なのかもしれない」「自分だけがマイノリティだ」と孤立感を深めていってしまうことは容易に想像がつく。また、それ以外にも、さまざまな問題が発生してくる。
進路や職業選択において、参考になるロールモデルや情報を周囲から見出せず、結果として、進路の幅が狭まってしまうこともある。
それだけでなく、「自分は一人だ」という実感は、多くの場合、積極的に行動する意欲を奪っていく。
そんなときに、当事者コミュニティに参加し、自分と同じマイノリティ性のある、自分に似た人に出会えることは、貴重な経験だ。その人の持つ経験や情報が、自分とは完全に一致せず、自分のしたいこととは違っていて、あまり参考にならないかもしれない。それでも、初めて会う、自分と同じマイノリティ性のある人は、仲間になりうる。
同じマイノリティ性のある仲間だからこそ、できる話もある。
私は、自分のマイノリティ性に関して調べるのが半ば趣味と化しているようなところがある。複数のマイノリティ性を有していることもあり、常に気になる書籍や論文がいくつかある状態だ。書籍や論文を読んで感想を語り合うのは、いつも当事者だ。
非当事者の友人には、こんな話はできたものではない。私は、純粋に知的好奇心から調べ、「こんなことがわかったらしい」「これって、ここにつながっていくのでは」などと考えや想像を膨らませている。しかし、非当事者の友人には、「やっぱりそのことを気にしているんだ」と取られたり、返事にも気を遣われてしまったりすることがある。「当事者でないとわからないことがある」と考えている非当事者は多く、実際そういったことはあるが、私は「この人となら自身のマイノリティ性を探究するのも楽しいだろう」と思って声をかけている。だが、相手が非当事者の場合、そのような話題において、いつものように話すことは難しい。相手からの気遣いが生じてしまい、純粋に探究するわけにはいかなくなるのだ。
同じマイノリティ性のある仲間であれば、気遣われることはほぼなく、気兼ねせずにマイノリティ性に関する探究ができる。
私の場合は探究だったが、他には、ファッションやメイク、趣味の楽しみ方などの話題もあるだろう。非当事者にマイノリティ性の話を出すと、気遣われて本音を言えなくなり、気まずくなることがある。
だから、気兼ねなく話せる仲間に出会えると、気が楽になるのだ。
こんなこと、当事者コミュニティで同じマイノリティ性のある、自分と似た者同士の仲間にしか言えない。そういうことが、マイノリティの人々の日常には溢れている。
Aro/Ace(アロマンティック/アセクシュアル周辺のセクシュアリティ)の人々の集う場で、私が「好きな人がいるのがふつうとか、恋愛は皆がするものみたいな押しつけにいらいらする」と話すときに、詳細な説明はいらない。それは、その場においてある程度共有される経験なのだから。
同じ言葉を、例えば職場の昼休みにでも、同僚に聞かせたらどうなるか。まず返ってくるのは、困惑。そして、去っていくか、無神経な説得をされるか、今まで傷つけていなかったか聞いた上で、腫れ物に触るような扱いを受けるか、のどれかが待ち受けている。無神経に「いつかいい人に出会えるよ」と説得されるのが私は一番嫌だが、どの反応も、非常に”面倒くさい”のだ。だから、職場でそのような話はしないことにしている。面倒なことが起こるのは明白で、私はそのような面倒を嫌う。
当事者同士で「あるあるネタ」として話すことによって、気持ちがふっと軽くなる。そういうこともあるのだ。『私がアルビノについて調べ考えて書いた本――当事者から始める社会学』(矢吹康夫著、生活書院、2017年)にも、飲み会で語られる「あるあるネタ」としての語りについて書かれている。
“授業がつまらないんだけど拡大コピーを頼んだ手前サボりにくい”(44ページ)のは、問題提起するほどでもないが、誰かに吐き出したくなる話だ。私自身にも覚えがある。なお、サボりにくいのはある程度仕方ないと私は考えるが、「配慮をしているのだから、より一層しっかりやりなさい」と強いられることは明らかに差別であり、問題だ。
当事者コミュニティに参加することで、他の当事者が実在すると知って安心したり、面倒な説明を省いて非当事者には話しにくいことを気兼ねなく話せたりして、気が楽になる。マイノリティの人々にとって、それは価値あることだ。
非当事者に気遣われること、そして非当事者を気遣い説明するなどの面倒を背負うこと。そこから一時的に解放される場は、マイノリティの人々にとってオアシスとも呼べるかもしれない。