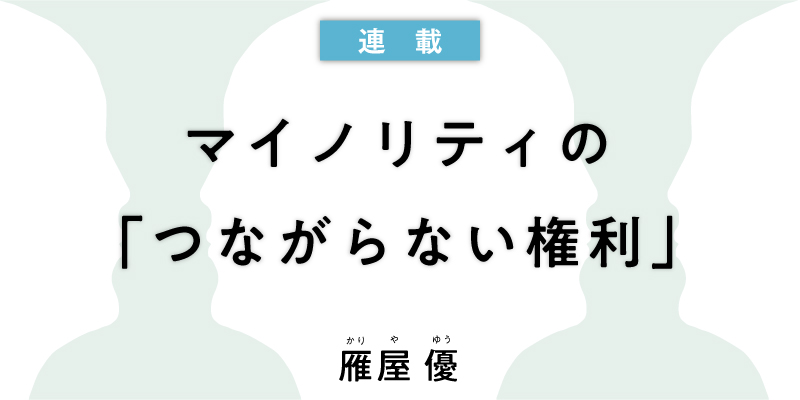障害開示や特別支援教育の視点から、マイノリティの「つながらない権利」を捉え直す~相羽大輔さんインタビュー~【後編】
第26回では、合理的配慮の抱える難しさや、必要な情報について話し、そしてマイノリティの「つながらない権利」を考える上で欠かせない課題整理を行った。引き続き、日本における当事者支援の状況や、マイノリティの「つながらない権利」実現のために必要なことを相羽大輔さんに伺っていく。
当事者支援に関する日本の現状
――先ほど出てきた当事者に必要なアーカイブは、日本では実現可能なのでしょうか。それとも、当事者団体が精力的に活動しているような国でないと難しいですか。
相羽さん(以下、相羽):まず国ごとに人口やその散らばり方、政治方針などに大きな違いがあります。それによってできることも違ってきます。その上で、アーカイブを作るなら、その情報の責任はどこが取るのかを明確にしないといけません。例えば、北欧では障害のある子どもが生まれると、子どもが0歳の段階から保護者に対する研修会を定期的に行っています。そこで保護者は視覚障害児に関する知識や子育ての方法を教わります。資金は国から出ており、保護者は仕事を休んで参加できます。実際に運営しているのは当事者団体です。こうした当事者団体には、視覚障害分野の専門家が雇用されており、専門的な研修が行われています。
――国から資金はもらうけれど、実際の活動は当事者が行う形が今のところは最適なのかもしれませんね。海外では、当事者団体でのインターンが当事者の就職に有利に働くところもあるそうですが、日本では全然そうなっていないと感じます。
相羽:当事者団体が育つことも大事なのですが、当事者団体だけでは難しい面もあります。何より、情報格差をなくすことが大切です。リアルタイムで障害のない人たちが得ている情報が、障害当事者にも届くような仕組みが必要だと思います。障害があるからこそ必要な支援情報、たとえば「皆と同じ学校に行きたいけれど、どうすればいいのか」といった情報が地域から得られたら、もっとよいと思います。
――そういったことができると、情報のバリアは改善されるでしょうね。ただ、私は、国と当事者団体が近くなるのを手放しに歓迎することはできません。元々国がやるべきことを当事者がやってきて、その成果にフリーライドされているような現実もあるように思います。
相羽:外から見ればそう見えるかもしれませんね。実は日本では当事者団体が国にコミットして意見を伝え、それが反映されているケースもあります。読書バリアフリー法や障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法はその一例です。これらは、障害のある人が障害のない人と同じ情報を、個々の障害特性にあった形式で、同じ場所、同じタイミングで受け取れる環境の整備に大きく貢献してくれています。障害のある人だけに必要な情報ですら、現状はアクセスしにくい形式で発信されている場合があります。だからこそ、当事者団体はそのような社会的バリアを解消する取り組みを頑張っています。ただ、日本の当事者団体は病気や障害種別で細分化されています。細分化されすぎると、個々の当事者団体の力も弱まります。海外だと、視覚障害と聴覚障害の団体が一緒の国がほとんどです。団体のなかで障害種別ごとにわかれていますが、日本よりも動きとしてまとまっています。そうして、皆で国との交渉や団体の運営をしています。
――アルビノはじめ難病に関する事業を考えていると話すと、「患者数が少ないから採算が取れないのではないか」と言われることが多いので、細分化してまとまらないことの弊害は私も強く感じています。でも一つの疾患ではなく、難病患者と大きく括るなどすれば、患者数も少なくないので、活発に動けるのではないでしょうか。
相羽:日本にもまとまろうとする動きはあるのですが、視覚障害やアルビノはそういったときに忘れられてしまいがちです。雁屋さんがおっしゃったように広く見ることは大事で、僕も研究の際、外見では障害の状況がわかりにくい障害(インビジブルな障害)として、視覚障害だけでなく発達障害なども含めて、調査、研究を進めています。そういった状況に合わせた戦略は必要です。
情報を審査する形で信頼性を高められる可能性
――科学的にも信頼に値し、当事者の役に立つ情報を難しい言葉のみではなく、さまざまな形態のコンテンツで届けていくのが当たり前になってほしいですが、具体的な方法まではまだわかりません。
相羽:雁屋さんの考えているのは、おそらく難病情報センターがやりたかったことなのだろうと思います。ただ、医師と研究者だけで作っていて、難しい言葉での説明ばかりで、そうはなっていません。それこそ、病名をGoogle検索しただけでトップに表示されるページなので、当事者と医師による動画解説や、当事者団体へのリンク一覧を貼るなどして、アーカイブとして充実していけばよいですね。そこではアルビノの専門家ではなくて、サイエンスと当事者をつなぐ、サイエンスコミュニケーションができる人が求められるでしょう。今の難病情報センターのページを見ても、当事者家族が満足できるとは思えません。
――たしかに、新たなものを作り上げるより、今あるものをよりよくしていく方がやりやすく見えます。科学だけに偏らず、情報の信頼性を保障する方法も考えないといけませんが。
相羽:サイエンスと当事者の視点両方からの評価基準を作って、ウェブページに掲載する情報の妥当性を審査するという方法が一案です。これは科学的根拠があって、なおかつ当事者の役に立つ情報である、と言った風に審査していくんです。それなら当事者目線でも確かであり、科学だけに偏らない情報の運用になります。もしも、実現できたら状況はよくなるでしょう。
それぞれのニーズを大切に、協力して動いていく
――マイノリティの「つながらない権利」実現のためには、しっかりした情報がちゃんと届く必要があります。その環境を整備するには当事者だけでは難しい部分もあって、どうしたらいいのでしょうか。
相羽:当事者だけでは無理ですが、当事者の組織があるから実現することもあるので、当事者団体が育たなければなりません。専門性、人材、そして資金が大事です。これらをどう得ていくかが大きな課題です。また、僕と雁屋さんがスタッフをしている日本アルビニズムネットワーク(JAN)は専門性の高いメンバーが多いですが、世界的に見てもそういった当事者団体は少ないので、そこを強みとしたいところです。
――現状、JANには課題が山積していますが、強みを活かせるところまで持っていきたいです。そのために大切なことは何でしょうか。
相羽:僕と雁屋さんでは、同じ疾患であっても、症状も、支援のニーズもそれぞれ違いますよね。それぞれのニーズをリスペクトして、協力できるところはしていくのが大事です。アルビノ一つ取っても、着眼点は「見た目」「ロービジョン」「日焼け」「遺伝」などたくさんあります。どれも大切にして、ニーズごとに協働できるところで他の当事者団体と連携をとれたらより大きな力になります。他の障害や疾患に対しても、互いのニーズをリスペクトしながら、バリアフリー・コンフリクトとも向き合い、戦略的な協力体制を築けたらよいですね。
インタビューを終えて
障害開示や特別支援教育の研究、実践を通して当事者支援に携わってきた相羽さんに、私の考える、マイノリティの「つながらない権利」がどう解釈されるか、インタビュー前にはまったく見当がつかなかった。当事者支援の現場を知る相羽さんには、私の主張が現実を見ていないものと映る可能性も考えた。でも、だからこそ、お話を伺う必要があった。
しかし、相羽さんは人にはそれぞれ得意なコミュニケーションの形があることや合理的配慮の抱える難しさ、サイエンスコミュニケーションがマイノリティ、特に病気や障害のある人々の状況を改善するときに考えられる仕組みを話してくださった。
マイノリティであっても、互いの違いを受け入れられないときがある。だからこそ、相羽さんの言う、「互いのニーズへのリスペクト」はそれを乗り越えるために不可欠な姿勢だ。
私が数年かけてようやく言葉にした、病者や障害者に届く情報の偏りを、相羽さんは既に課題として認識していた。それだけでなく、サイエンスコミュニケーターとして私がその課題に挑むことを後押ししてくださった。その言葉を心から嬉しく思う。
これからも、状況を広く見て考え、現状をよりよくするのに必要なことをやっていく。