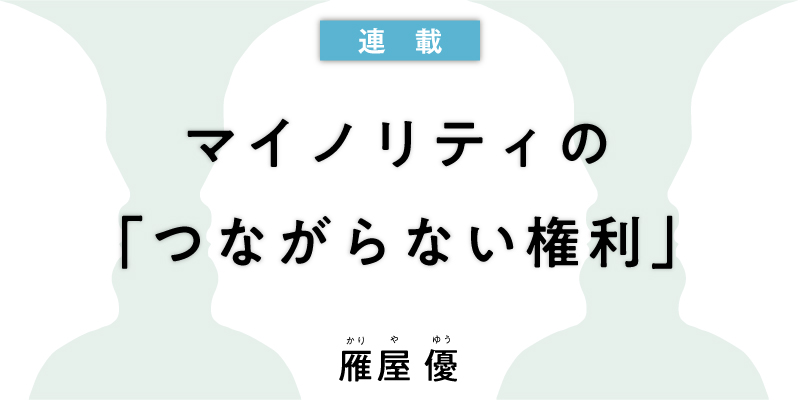問題提起編 2.当事者コミュニティの功罪(3)
他の当事者の経験を聞き、過去を再定義できる
マイノリティ性のある人々は、マイノリティ性ゆえかそれ以外の要因かも判然としないままに、多くの経験をする。私の場合、なぜか知らないが人間関係が長続きしなかったりトラブルが起きてしまったりしやすいことから、「あなたの髪の色では雇えません」とアルバイトの採用を断られることまで、多岐にわたる。
後者のアルバイトの不採用については、相手が私の「何」を問題としたのか、つまりは不採用の原因が明確だ。私が生まれ持った遺伝疾患、アルビノゆえの色素の薄い髪を問題視した、と相手は明言しているのだから。
ところが、前者はそうはいかない。「何かわからないけど知らない間に」人間関係が崩壊しているのであって、何のせいかは判断がつかない。アルビノゆえの容姿を疎まれたか、それとも眼症状に配慮しないといけないことを面倒に思われたか、運悪く性格が合わない相手を立て続けに引いてしまったか、あるいは私の性格が破滅的なのか。勿論、原因は単一とは限らない。複数の原因からなる事象の方が多い。つまり、想像は無限に広げられる。
困難の原因を無限に想像してしまえる状況に置かれたとき、人は何を原因として想定するだろうか。マイノリティ性が原因で否定されたり、マイノリティ性を自分も周囲も認識していないなかで自分を否定されたりする経験を、ある程度積み重ねてきたとしたら、どのように思考は動くだろうか。
私の場合は、いつの間にか人間関係が崩壊してしまう理由について、考えることを放棄した。学生時代は、人間関係を維持するよりも自分のなかで優先度が高いこと――学業や趣味――があったし、仕事をするようになってからは、業務上のコミュニケーションはプライベートのそれとは異なっており、自分と合う労働環境であればどうにかなると判明したからだ。つまり、「なぜかわからないけれど、そういうことがよく起こる。自分の目的のために必要な対処をしよう」と結論したのだ。
私の結論の是非は誰にもジャッジさせない。しかし、後に、当事者コミュニティに参加して、前述の状況下でこの結論を出せるマイノリティは少ないと知った。
残念なことに、マイノリティの多くは、自分自身や、自分のマイノリティ性を責めてしまうのだ。「自分が〇〇だからいけない」あるいは、「自分が何かおかしいのかもしれない」といった具合だ。
当事者コミュニティでは、他の当事者の経験を聞ける。自分と似たような経験をした当事者に出会うことで、「もしかして、あの経験は、自身のマイノリティ性への無理解や差別が原因だったのではないか」あるいは、「自身のマイノリティ性から起こる困難ゆえに生じたトラブルだったのではないか」などと考えるようになる。
私も、他の当事者の経験を聞くまでは、自分自身やマイノリティ性があることそのものに原因があると捉え、自分を責める感情に苛まれてしまうこともあった。当事者コミュニティに集うのは、テーマとしているマイノリティ性が共通している(完全に一致しないことの方が多い)、それ以外は年齢や職業などの背景が異なる人々である。
それで似通った経験をするのであれば、その経験は「私」のせいではない可能性が高い。そして、基本的なことだが、マイノリティ性があることそのものは責められるべきではない。このように、思考が整理されていく。
原因が不明瞭で掴みどころがなかった場合も、マイノリティ性から生じる困難に一因があるのではないかと考えられるようになる。
こうして、過去の経験は再定義される。
あれは、自身のマイノリティ性への差別だった。
あのときの経験は、自身のマイノリティ性ゆえに生じる困難に一因があったかもしれない。
絡み合った糸を解きほぐすように、過去の経験への認識が整理される。
闇雲に自分を責めるだけではなく、自分以外のものにも原因があった可能性に目が向くようになっていく。視界が拓けていく。
当事者コミュニティに参加することは、過去の経験を再定義するきっかけを与えてくれるかもしれないのだ。
ただし、過去の経験を再定義することは、常にポジティブな結果を生むとは限らない。
自分を責める思考や感情が軽減される代わりに、当時は味方だと思っていた人が実はそうではなかったと気づいてしまう可能性は十分にある。過去に、私の学業成績を「弱視なのにすごい」と褒めた人がいた。当時は何かもわからずもやもやしたが、褒め言葉を素直に受け取れない自分がいけないのだと思った。しかし、後にそれはマイクロアグレッションだったと気づいた。それゆえにその人と関わるのが嫌になり、今後その人には二度と連絡しないことを決めた。
私は過去の経験の再定義によって、何人かとの関係を完全に過去のものとした。つまり、見切りをつけ、葬り去ったのだ。
今まで何でもないと思っていた社会や制度が途端に醜悪に見えることもある。私には、アルバイトの採用面接や就職活動で髪の色を問題にされ落とされることを、「仕方ない」と考えた時期がある。いい気分はしないけれど、そういうものだろうと感じていた。「それは不当な扱いだ」と他の当事者の言葉を聞いて、私にそのよう経験をさせた企業に、それを当然とする社会に、嫌悪感や怒りを抱くようになった。あまりの対応のひどさに、不買を誓った企業もいくつかある。
自分を傷つけたものが何だったのか、その輪郭を捉え始めた証左だ。
それでも、他の当事者の経験を聞き、過去の経験を再定義することには意義がある。
過去を掘り返して苦しむだけに思えるかもしれない。過去の経験を振り返らない方が今を幸せに生きられる、と考える人もいる。しかし、マイノリティ性に関する経験については違うと思う。
過去の経験をそのままにしておかずに再定義し、原因は自分のみにあるのではなく、他のものにもあると考える。そのことによって、現在、そしてこれから起こる事象についても、何か不都合が生じたときに自分のみを責める前に立ち止まれるかもしれない。過去に自分を傷つけた人や組織と現在も近しいならば、そこから逃げ出す決断ができるかもしれない。
何かあったときに、「自分一人が悪いように感じるけど、本当にそうだろうか」と疑問を抱けるようになれば、世界は変わる。
過去の経験の再定義は、マイノリティ当事者が自分を否定する負のスパイラルから抜け出す突破口となる可能性を秘めている。