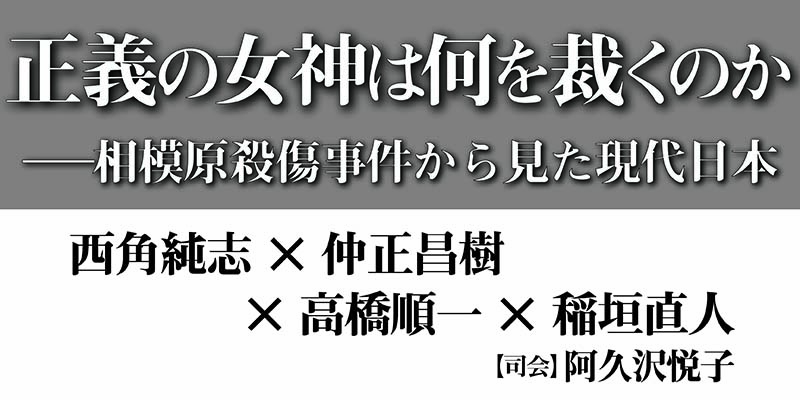正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本 第9回
2021年10月24日に開催された『元職員による徹底検証 相模原障害者殺傷事件―裁判の記録・被告との対話・関係者の証言』刊行記念トークイベント「正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本」(共催:明石書店・読書人、会場:神保町・読書人隣り)。西角純志氏(著者。専修大学講師)、仲正昌樹氏(金沢大学教授)、高橋順一氏(早稲田大学名誉教授)、稲垣直人氏(朝日新聞)が登壇し、阿久沢悦子氏(朝日新聞)の司会進行により充実した議論が交わされました。本記事は、その内容を採録したものです。
【全9回連載 ダイジェスト動画をYoutube明石書店チャンネルにて公開中⇒https://youtu.be/ZUmZHFgWico】
13.「自己責任」という名の定言命法
西角:今、自己決定の話が出てきましたけど。自己決定とか自己責任とかいう概念は、遡ればカントですね。
高橋:そうですね。
西角:今日は触れられなかったんですけど、カントの有名な言葉に「刑罰の法則は定言命法」であるというのがあります。これは「目には目を、歯には歯を」という言葉で知られる同害報復の原理です。人を殺したら自分も死ななければならないと言います。死刑制度そのものもカントは認めています。カントに対抗する形でデリダの死刑廃止議論が出てきましたが、カントは、イタリアの法学者ベッカリアの『犯罪と刑罰』(1764年)に反論する形で書いています。ベッカリアやデリダは、死刑反対論者ですよね。カントとは対極的な形で。当時はベッカリアの著書が出たというようなことで、それに対してカントも批判しています。「汝、かく為すべし」と。例外を求めない普遍妥当な原理、これが定言命法です。
高橋:もう一言だけつけ加えておくと、今いった知恵と並ぶかたちで挙げておきたい、知恵というよりむしろ失われた権力の作法というべきものがあります。それは「殺される王」という作法です。じつは王はもともと殺されるべき存在、殺されなければならない存在なんです。殺されるが故に王であり権力の所有者なんです。共同体の生贄として殺されることが予め定まっているからこそ王は王たりうるわけです。王の起源、言い換えれば権力の起源は殺される王にある。このことは王が永遠に権力者であり続けることは出来ないことを意味します。つまり最高にポジティヴな存在であるはずの王はあらかじめネガティヴなものになることを決定づけられているのです。さっきの反対ですね。聖なるものは一瞬にして賎へ、穢へ反転するのです。これによって権力者という強者に対する歯止めがかけられます。未開社会には国家という永続する権力装置を作らないという「知恵」が働いていたと、かつてフランスの人類学者ピエール・クラストルはいいました。強者が権力をほしいままにする、弱者をなぶりまわすような所業を許さないための作法、「知恵」として殺される王はあったともいえるでしょう。
ただね、私は、殺される王の中に働く生贄の作法が、共同体にとって都合の悪い存在、つまりホモ・サケルを処刑する論理にもつながっていると考えます。つまり殺される王は死刑の起源でもあるかもしれないということです。それは、これもやはりフランスの人類学者ですが、ルネ・ジラールがいった共同体から満場一致で生贄を排除=処刑する暴力に通じるものです。今我々が直面している様々な差別や排除の暴力の起源にあるのはジラールのいう満場一致の暴力なのではないかという気もします。このあたりはどうなんでしょうか。殺される王は権力を制御する知恵なのか、それとも暴力の起源となる酷い迷信なのか。
仲正:でもね、迷信っていうのは、芹沢さんなんかのやってた仕事なんだけど、明治初期だったら狐憑きとか。
高橋:そうそう。
仲正:狐憑きは、異能だったんです。
高橋:異能だね。そうそう。
仲正:『遠野物語』の世界ってそうなんですね。『遠野物語』は異能が異常でなかった時代。
高橋:あの本が出たあたりがまさに境目だったんですね、日本でいうと。
仲正:そう。今精神障害者だとされている人のかなりの割合は、異能のほうに入ってた可能性高いと思う。自己決定っていうのであれば、放っておけばいいのですが、他人に自己決定を強いるときに、問題が出てくるわけです。お前が人間であれば、自分で自分の生き方を決めろ、ただし、この社会で一定の役割を果たせるように、他人に依存するのは駄目。そういうふうに押しつけがましくなってしまう。それで、植松がなんで他人が生きるに値しないという話に妙にこだわったのか考えてみたんですけれど、今だとね、近代の国家というのは、決まった資源を管理してるってイメージがあると思うんです。で、資源がかなり豊富にあると思ったら、直接的には生産的じゃない人でも、まあ、いてもいいんじゃないか、それなりに役割を果たしてくれてるかもしれないしくらいに思えるんですよね。それが、資源が少ないって思い始めると、お前なんで取ってるんだ、となる。植松がね、なんか固執したのは、自分との境界線が微妙だという問題プラス、「お前なんでそこにいるんだ」と、「お前結構資源とってるぞ」という意識があったと思うんですね。
阿久沢:すごく国債について彼はこだわってましたよね。
仲正:そうだ。それありますよね。今の若者っていうか、たぶん90年代以降の傾向で、国の財政のこととかそんなに厳密に考えてるわけでもないのに、なんか資源が足りないと、「お前取ってるじゃないか!」っていう意識がむちゃくちゃ強くなってて、そのため、生きるに値しないっていうのが、単なる罵詈雑言というより、生きるに値しない奴が自分と同じ位置でいる、「これでいいのか」という焦りになっている。でも、たぶん、こいつは生きるに値するのか、と問うときは、自分自身の立場も怪しくなっているんですよ。
高橋:その本人自身がね、
仲正:自身が怪しいから、いや、自分もそう思われてるんじゃないかなと思って焦る。そうすると、抑圧の下方移譲の理屈のような発想が出てきて、それだったら自分よりももっと役に立ちそうもない奴を排除してやったら、自分は少しは、その資源に参与する資格があるんじゃないかみたいな、そういう、心理的に勘定を合わせるような発想が働く可能性ってあると思うんですよね。お荷物って言い方ありますよね。クラスの中でちょっと障害がある子とか、馬鹿じゃないかと思われてるような子を馬鹿にしたり差別したりする。いじめてる奴がそれをやったからって客観的に見れば何の得もないですよ。だけど本人はお荷物を排除すれば少しは楽になるかのように感じているかもしれません。自分も実は結構お荷物っぽく思ってるから、お荷物を排除したくなると。それを一応大人になった人間がもっともらしい言葉として表現したときと、生きるに値しない生、という言い方になるんじゃないかと思います。自分自身が生きるに値しないくせに無駄飯食わせてもらってるんじゃないかっていう恐怖感がある。他人のことが非常に気になってしまう。そういうメンタリティがなんかね、植松にはっきり出てきてるんじゃないかなって気がする。
高橋:それってものすごくホッブズの『リヴァイアサン』的な状況だという気がしますね。面白いなぁ。ホッブズの『リヴァイアサン』は、一般的には近代社会ないしは近代国家の起源をはじめて理論的に論じた著作だといわれてるけれど、その議論は、今まさに仲正さんがいったような、個人と個人とのあいだの血で血を洗う凄惨な相互排除の暴力から始まっているんですね。ホッブズはそれを自然状態といっています。自然状態において人間は生き延びるために互いに殺し合う。したがって自然状態は万人が万人に対して戦争状態にあることを意味します。それでは皆死に絶えてしまい生き延びるという目的が果たせなくなってしまうため、互いの殺し合いを制御するための装置である国家、コモンウェルスを導入するわけです。コモンウェルスというのは公共の福祉という意味ですね、この公共の福祉を守るために、国家は個々人に対して自分の身を守る暴力を差し出させる。以後個人は勝手に暴力を行使してはいけなくなる。明治近代になると敵討ちという私刑が禁止されてのを思い出してください。このことは、個人が殺されない代わりに一種の無権利状態へと貶められることを意味します。奴隷の安心立命です。つまり国家や社会の起源において演じられるドラマには、血で血を洗う暴力の応酬、それを止めるための作法としての個々人からの暴力の押収、そして個々人に対して厳重な線引きを行い、私性の範囲へと封じ込めてしまうことといった要素が含まれているわけですね。
その後に来るのはそうした社会を構成する主体の形成と分節化です。そのためには奴隷の安心立命のうちにまどろむ個々人をもう一度安全なかたちで目覚めさせなければならない。それが生産的身体として目覚めさせることです。それをやったのが『市民政府二論』を書いたジョン・ロックでした。彼は労働する身体をつくるわけです。個々人を労働する身体にする。そして労働する身体をそのまま私有財産を持てる身体とする。これが主体であり人間の条件であるというわけです。ホッブズからロックに至る時代は、ちょうど17世紀イギリスにおけるピューリタン革命から名誉革命へ向かう時代でした。イギリス資本主義の形成期ですね。ちなみにいえばピューリタン革命のときのイデオローグがホッブズだとすると、名誉革命によってイギリスに議会制民主主義の体制が確立されるときのイデオローグがロックだった。この過程の中に現在の我々の社会をも根底において規定する近代社会の論理が現われていると思います。
要するに殺し殺されるというぎりぎりの状況のなかにいる個人を線引きの作法を通して主体という枠の中にはめこんで、さらにそれを労働する主体、生産する主体、つまり生産的身体へと造型するということです。生産し労働したらちゃんと自分の私有財産が増えますよという餌で釣って、個々人を近代社会の奈落のうちへとドドーンとたたき込んでいったわけですね。今仲正さんが話したことは、まさにそのそういうドラマであり、しかもそのドラマが我々の社会においても依然として底流しているということだと思います。普段我々はそうしたドラマを全く意識していないけれども、今の状況を見ていると、そうしたことを意識せざるを得なくなってきているのではないか、そうした近代の論理がはたして正しいのかも含めてですね。それは、我々の社会がある種の不安定さっていうか、ある種の危うさを抱えているからだと思います。
仲正:普段は、普段っていうか安定してる社会では?
高橋:考えない。
仲正:考えないというか、国家が、これはお前の領分だと、お前は他人のことまで心配しなくていいと決めてくれてるんですよね。ところがね、自分の立場が不安定になると、人のことを気にし始めるんですよ。たとえば大学なんかで学部再編とかになると、自分より無能な人間を探し始めるんです、間違いなく。会社だってそうだと思いますよ。ネガティヴな意味でのリストラがあると、必ずね、自分より無能な人間を探します。自分もたぶん不良債権だと思ってるんですよ。そうすると、必ず探し始めます。で、これはいろんなレベルで起こってて。ヤフコメやツイッターの炎上の中心は中年のサラリーマンだということを聞きますが、中年のサラリーマンがツイッターで余計なことを書きこんでるのはひょっとすると、自分がもうお荷物かもしれない、という気持ちがあるからではないでしょうか。それがそのツイッターの攻撃性に出てるかもしれない。傍目から見ると、お前、そんな人のことまで考える必要ないじゃないかと、お前は、まだ生きていられるだろう、と見えるけど、本人は必死かもしれない。植松に対しても、お前バイトなんかすれば生きてられるだろうと、死ぬことないだろうと、なんでそこまで人の事を気にするんだと言いたくなりますが、本人としてはもう、自分はもう取り分を与えてもらえるギリギリのところにいて、お荷物扱いされてもう辛いんだみたいなふうになってたかもしれない。そういうふうに思いました。
阿久沢:すいません。あと10分ないぐらいなので、なんかお一方(ひとかた)からしか聞けなかったので。他に大丈夫ですか。じゃあそろそろ頃合いなので、ここ会場アバウト17時までに。西角先生じゃあ締めをお願いします。
14.根源悪をどう乗り越えるのか
西角:じゃあまあ最後は、この根源悪をどうやって乗り越えていこうとするかという話で。まあ要は、植松が優生思想を知らなかったが結果としてやった行為が優生思想的で、これはまさに人間社会の根源悪というふうなことで、これをどのようにして乗り越えていこうかということについて一言ずつ最後に話をして終わりにしましょう。
稲垣:やはり、他者を知らずに、こういう行為に及んだりすることがありうると思っていて。まず誰しもが他者をよく知ることが大事なのはないかと思います。朝日新聞に先日、俳優の奥山佳恵さんのインタビューが載っていて、彼女の次男のお子さんはダウン症で、それについてのインタビューでした。我が子がダウン症と知ったときには落ち込んで、モンスターじゃないかと思っていたけれど、本当のモンスターは、ダウン症について分からない、知らないことによる不安そのものだと今知った、と仰っている。むしろ長男のほうがよっぽど子育ては大変だったと、まあ今だから言えることですが…と言いつつ仰っていました。まず、みんながそれぞれ他者を知ること、知らないことには何も始まらない気がします。具体的な手段はまた考えなければいけないことですけれども。
あともう一点、今の議論を聞いて思ったのですが。先ほど、ホッブズ的な自然状態、殺し合い的なことが起こっているというお話があって、そうした現象は90年代頃から観察されると仰っていたのが非常に面白いです。経済的に見ると、この90年代にバブルが崩壊し、以来、経済成長率がほとんど上向かない、経済のパイがほとんど大きくならない状態がずっと続いている。そうすると、いろんな職場で、いろんなコミュニティで、「お前の取り分のおかげで、俺が食いっぱぐれている」と思う人たちが増えているように思うんです。これは、貧困や格差の問題、緊縮財政の問題とも関わってくるので、また別のテーマになってしまいますが。ここをなんとかしないと結構ヤバいという感じがします。この解決策を見つけるのもなかなか難しいんですけれども、ここでもやはり原因はどこにあるかをまず認識することが必要じゃないかと思います。
仲正:さっきの話の延長で言うと、やはり究極的には、分配を成長につなげるってあれ、中身ないから批判されてますけど、基本あれしかないんですよね。そうじゃないと、やっぱり、お前の取り分と俺の取り分どっちが大事だって追い詰められた気分になってしまわざるを得ないので。マクロにいうとそういう話になるんですけれど、個人の気持ちの持ち方として思うのは、自分がどれだけ生まれてこのかた人のお荷物になってたかちゃんと自覚することが肝心だと思います。この歳になると、今58ですけど、振り返るとやっぱりお荷物になってたことのほうが多かった。だからあんまり今更焦ることはない、と。だからまだ生きていようという人は、焦る前に、自分はもともとお荷物だと、ちゃんと自覚することが大事なんじゃないかと。自分は人に対して負い目を持って生きてる存在なんだ、それはもう死ぬまでしょうがない、そこはまず認めよう、文字通りの自立などありえない。当たり前のことみたいですけれど、それこそが人間の在り方だということを確認し、生き方の基本にしていく、そういう思想が必要なのではないかと思います。
高橋:何か仲正さんに言いたいことを先に言われちゃったような気がします(笑)。というのも、今仲正さんがいった「お荷物」という言葉が意味するのは、我々皆が負っているはずの「弱さ」だと思うからです。これは稲垣さんのお話とも関わるかもしれないけど、自分の内にある弱さをちゃんと直視することが大切なのではないか。不思議でならないのは、どうしてみんなそんなに強くなりたがるのかということなんですね。一番典型的なのはトランプやプーチンや習近平のような権力者の連中ですが、それだけではなく何でもない普通の人間まで、強くなりたい、マッチョでありたいと考えてしまう。そしてそれが挫折するといともたやすく社会からドロップアウトしてしまう。これが一番問題だと思います。そうではなく、自分の内にあるそれぞれの弱さをちゃんと直視すること、自分が弱い存在だということをちゃんと見つめることが大切だと思います。そして自分の内なる弱さを見つめることは、同時に他人の内にある弱さを認めることも意味しますね。そして弱さのあり様はそれぞれ人によって違う。お金がないことかもしれないし、病気や障害かもしれないし、他者の承認が得られないことかもしれない、容姿に自信が持てないことかもしれない、そうした無限に多様なそれぞれの弱さを互いに認め合うことによって、人間ははじめて違いを認め合いながら、つまり差別や排除を含まないかたちでの相互承認を通じて、他者との出会いやコミュニケーションをとることが出来るようになるのではないか。つまり弱さを社会にとって不可欠な要素として社会の中にきちんと組み込むことが大切なのです。これが多様性、ダイヴァーシティの真の意味だと思います。
そこで思い起こされるのが、今日の議論のなかではほとんど触れることが出来なかったのですが、ドイツのヴァルター・ベンヤミンという思想家のことです。ユダヤ系ドイツ人であったベンヤミンは1940年、ナチスから逃れてアメリカへと亡命しようとしますが失敗して自殺してしまいます。その最期の瞬間まで書き続けていたのが「歴史の概念について」という断章集です。私は、この「歴史の概念について」を通してベンヤミンが最後に伝えようとしたのが「弱さ」の思想、あるいは弱さに寄り添う、「寄り添う」といういい方はこの頃よく使われますが、ちょっとセンチメンタルな感じがしてあまり使いたくないんですけど、あえていえば「弱さ」に寄り添う思想というべきものだと考えています。自分の弱さを見つめることを通して他者の弱さを認めることは、人間が弱さにおいて連帯することを可能にします。強さは必ず支配するものと支配されるものという非対称的な関係を生みます。この頃はやりのいい方でいえばマウンティングによる上下関係ですね。弱さにおいて連帯するとき人間ははじめて真に対等、平等になれるのです。これはおそらく人間同士の関係だけではなくて人間と自然との関係においても同じことがいえるはずです。壊れやすい自然を慈しみ、自然に寄り添うことも、自分の弱さを知らなければ不可能です。これまで強者がどれだけ自然を蹂躙してきたかを思い出して下さい。大切なのは弱さを通した連帯です。
ベンヤミンはこのことを「歴史の概念について」の中で「弱いメシアの力」ないしは「微かなメシアの力」といっています。メシアは救済をもたらすもの、救世主のことですね。この世界に救済をもたらす救世主は決して強いメシアではない。それは弱いメシアなんです。イエスのことを考えてください。イエスは決して強い存在ではない。それどころかはりつけにされて殺されてしまう弱い存在です。しかしその殺されるという弱さの極みにおいて人類を原罪から解放するという救済をもたらす。だからイエスのもっとも忠実な使徒であるパウロは「コリント人への手紙」の二のなかで「誇る必要があるなら、わたしの弱さにかかわる事柄を誇りましょう」といったのです。ハンマーでぶん殴って一気にこの世界をぶっ壊すみたいな革命論ではなく、とぼとぼ足を引きずって歩いているような弱い存在というところから世界の救済や解放の可能性を考えていくという姿勢が大事じゃないかと私は思います。
阿久沢:ありがとうございました。長時間にわたって会場の方もお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れさまでした。
[了]