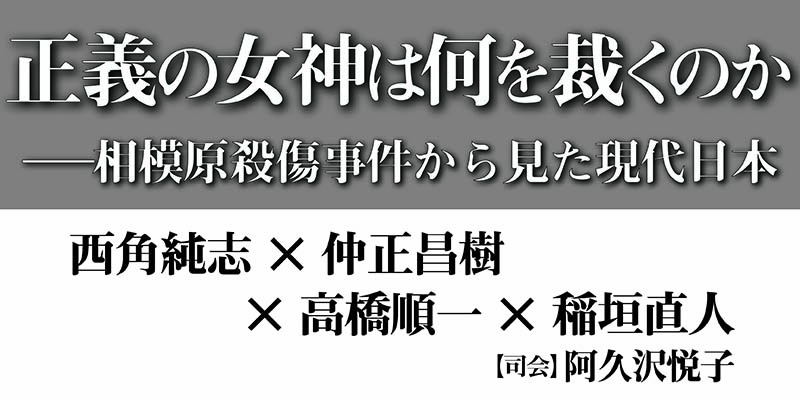正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本 第3回
2021年10月24日に開催された『元職員による徹底検証 相模原障害者殺傷事件―裁判の記録・被告との対話・関係者の証言』刊行記念トークイベント「正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本」(共催:明石書店・読書人、会場:神保町・読書人隣り)。西角純志氏(著者。専修大学講師)、仲正昌樹氏(金沢大学教授)、高橋順一氏(早稲田大学名誉教授)、稲垣直人氏(朝日新聞)が登壇し、阿久沢悦子氏(朝日新聞)の司会進行により充実した議論が交わされました。本記事は、その内容を採録したものです。
【毎月25日頃更新・全9回連載 ダイジェスト動画をYoutube明石書店チャンネルにて公開中⇒https://youtu.be/ZUmZHFgWico】
4.植松聖は、ヨーゼフ・K!
仲正:ちょっと補足させていただきます。2番目のほうの<法外なもの>によって排除される人、具体的には、心神喪失の人か精神障害者ですが、どうして彼らを法外にしないといけないの。理由を聞いてもわかんないわけですよね。昔だったら、前近代だったら、魔法使いであるとか、それから、ハンセン病の患者とか、いろんな人が法外な存在になっていました。まあ理屈はつけようと思ったらいくらでもつけられるんだけれど、なんらかの形で。まあ外国人とかもそうですけど。そこはもう理由を聞いてももうしょうがないわけでね。それが一応、一番最初にそれを決定すると、普通の人間の基準ができる。すると法のプロセスみたいなのが発動して、じゃあこういうのもあれと似ているから、こっちに入ってきちゃ困りますと、そのためにはこういうルールをつくりましょうというのがどんどんどんどん出来上がっていく。それで法が機能し始めると、普通を守るための秩序がちゃんとできあがっているような気になる。秩序というのは大抵そうですね。いったんできあがると、それが安定している理由はいくらでも考え出せる。
障害者差別いけないじゃないか、と、一体何の法的根拠があるんだと、なんでこういう病気の人は差別するんだって、法の論理に訴えて挑戦する人いますよね。ただ、そういうことをやると…。まあこう言うとなんていうかな、市民運動批判みたいになっちゃうけど、市民運動をやるとね、大体、なんか訴訟を起こしますよね。日本は必ずしもそうじゃないけどアメリカだと、もう右も左も必ず連邦最高裁まで持っていって決着をつけようとしますよね、そうするとね、いや、こんな法体制そもそもおかしいと言ってる人間が、一番法に固執するっていうなんか、まあ非常にわかりやすい逆説状況が起こってくるわけで。市民運動をやってる左翼の人を見ていると、「あんた、そもそも日本の国家体制自体が気に入らないと言ってなかったっけ?」と、「なんでそんな訴訟にこだわるんだ」と、「あんたなんで弁護士になった」ってなんか言いたくなることが多いんです。ただ、これ法の世界になじんでいる人間は分かっていても、どうしてもそういうことをやっちゃうんですよね。一番最初の高橋先生の仰った、ダッシュがついているほうの<法‐外なもの>がおかしいと、それは恣意的だって抵抗するときに、自分自身が法の、審判=プロセスの中にはまり込んじゃうという逆説があるわけです。で、植松という男は、たぶん彼なりの法への拘りでのプロセスの中にはまってしまって、プロセスにはまると、プロセスを先に進めないといけないようになってしまう。それが高橋先生のお話だとまさに物語。彼が自分で、他の人から見ると、そんな物語が進むはずないじゃないかとしか思えない。普通の法とまったく違う、彼なりの法だから。誰も相手にしてくれるはずがない。彼は彼なりに物語をつくって、プロセス、後退してるのか進んでるのかたぶん本人もわからないんだろうけれど、プロセスの中に入っちゃってる感じになってるんだと思うんです。どうしてそういう物語を作ってはまっていくのかを明らかにしていく必要があるんじゃないかなということになるかな。
西角:だから『訴訟(審判)』におけるヨーゼフ・Kというのはまさに植松聖そのものなんですね。
阿久沢:植松については弁護士が大麻による影響で犯行に及んだのであって責任能力がないということを主張して減刑を勝ち取ろうとしたときにご本人がそれを拒否したということがあって、でもそれはやっぱりその刑法39条の心神耗弱者、喪失者として扱われる、まさに自分が心失者を殺したということの法理の中に、なんかご本人がすぽっとはまり込んでしまった瞬間だったのかなというふうに私は思いました。
西角:精神鑑定って3回行われてまして、1回目は措置入院の時です。北里大学病院の東病棟で隔離されて10日あまりで出てきます。厚労省の検証チームの「中間報告」では、措置入院時にドアを蹴ったり、大声を出すなどの粗暴な行為がみられたとありますが、実はその後平静を装い、措置入院が解除されます。2回目は検察側の精神鑑定です。検察官の精神鑑定で「自己愛性パーソナリティ障害」と診断され、責任能力が問えるので起訴できると。2017年の2月24日に起訴されました。3回目は弁護側の精神鑑定です。結果としてはですね、はっきりは報道されてませんけど、「パーソナリティ障害」ということでした。その後、もう一回弁護側が精神鑑定を求めたんだけどそれは認められませんでした。合計3回やっています。結局責任能力があるということです。植松被告は、横浜拘置所に収容されてましたけども、立川の拘置所にも一時期収容されたことがありました。これはなぜかというと、やっぱり東京都の方が、立派な優秀な精神科医がいるということなんですね。たとえば松沢病院だったりそういうところに連れていって、精神鑑定を行います。法廷でも裁判でもですね、弁護側と検察側の精神科医が出頭しました。植松の両親とは1回だけ面会したという精神科医もいました。弁護側は、犯行以前の本来の植松を知ることが大切で、大麻の影響を主張しましたが、最終的には、大麻の影響を重視する弁護側と大麻の影響を否定する植松との乖離という事態にまで発展し、被告の主張と弁護側の主張のくい違いに至り、死刑判決後も、植松自身が弁護側の控訴を取り下げるという事態にまで至り、死刑が確定しました。
5.法と言語
仲正:その関連で、『テッド2』の話ちょっと触りましょうか。この西角さんの本の中で話題になっていますが、何で彼がわざわざ知的障害者の人の施設で働くことになったのか、まさにプロセスだと感じるのは、わざわざ話ができない人間と話ができる人間を区別したうえで、殺害しようとした。で、そのときこれは西角さんのこの本の中では、そのちょっと前に、元カノと『テッド2』を見たのが参考になったのではないかと分析されています。テッドってなんか魂が入ったような、なぜかわからないけど喋る人形がいて、熊ね、テディベアね、テディベアが養子を迎えるかどうかが裁判で争われます。養子を迎えるのにやっぱり人間であるかどうかが基準だということになり、そこでそのテッドが自分で喋ることができたのが決め手になります、喋れるかどうかっていうのが、責任能力の話と結びついています。

植松が元カノとみた『テッド2』(c)Iloura/Universal Pictures and Media Rights Capital
先ほど言われた、心神喪失者とされるということは彼にとっては自分も喋れない人間にされることを意味していた。この喋れる喋れないというのは、普通に考えても、法の中では非常に重視される要素です。話せないと、責任能力があると証明できません。まあ単純に考えて弁護士というのは三百代言って言われるぐらい、法の言葉を駆使して。やっぱり弁護士って素人に対して強く出ますよね、一般的傾向として。「それは法ではできません」、と。「なぜですか?」、「法律でそうなってます」、と。まあ、プロ同士になるとやっぱりちょっと態度を変えてきますけれど、相手が素人だと思うと大体そういう強圧的な感じになると思います。植松がその言語っていうのが法によって、自分が受け入れてくれるかどうかの一つの基準だというふうに思ってしまうっていうのは、そういうルールですと一言で切っていく法的な言葉へのコンプレックスがあってのことではないかと想像します。
これもちょっと自分の話に多少ひきつけると、自分の表現能力にちょっとコンプレックスがある人っていうのは、たぶん法の言葉にひっかかる可能性が高いと思う。私は、「え、君一体何が言いたいの」みたいなことを小学校のときから、先生や周りの子に言われてきました。「いや、君の言いたいことを分かるように言ってほしいんだけど、それでは伝わんないよ」、と。まあ私の場合現在自分が教師になっているので、学生に対してそういうことを言うことが多いんですけれど、こういうことを言うと傷つく奴いるんだろうなと、でもまあ大学生だからしょうがないかと思って普段やってるんですけれど。そういうので、傷ついたような経験ある人っていうのは、というより、そういう経験がない人はいないと思うので、そういう経験が多くて、深く記憶に残っている人は、法が、言語能力で、コミュニケーション能力で人を切るっていう感じを抱いているのではないかと思います。「伝わらないよ」、と切られて、痛いような、痛く突き刺さってくる感じってあると思うんですね。植松が『テッド2』を観ただけで、いきなりそういう考えになるっていうことはおそらくなくて、たぶん言葉とか自分の表現能力に関してやっぱりなんかあったんじゃないかと想像します。
その言語っていうのが、法っていうのはそもそも、言葉によって成り立っているものってところがありますよね。法の言葉っていうのは、いろんなレベルがありますね、弁護士みたいに法の言語を駆使できる者もいれば、まあかろうじて法律に反しないようなものの言い方ができる人間とか。言語っていろいろ階層をつくるっていうことがあると思うんですけれど、法は特に極端です。「法ではこうです」「いやそうではない。法は実際にはこう言っている」という闘いの土俵に挙げてもらえないで、「意味が分かりません」で、門前払いされる者もいる。
この私のレジュメの3ページ目のところに、ハーバーマスっていう、我々3人フランクフルト学派関係のことをやってるんですけど、フランクフルト学派の長老、今生きてる中の一番長老で、ドイツの現役の哲学者で一番理論的な影響力のあるハーバーマスっていう人は、コミュニケーション的理性の理論家です。簡単に言うと、我々は普段生きてるこの日常の世界、生活世界というのは、だんだん植民地化されていく、法と貨幣ですよね。法と貨幣が生活に入り込み、人間関係を仲介するようになると、世界というのは規則化されてきて、合理化されてくるんだけど、そうするといろんなもの、生き生きした経験が失われていく、と。で、それを植民地化というふうに言ってるんですけれど、ただ逆説的に聞こえますが、法によってコミュニケーションをする能力を身に着けるということは、合理的主体として認められるようになることに通じる。まあこれもちょっと陳腐な言い方になるんですけれど、いろんな日常的な感性、自分なりの物の感じ方、高橋先生の言い方だと自分の中の法外な部分を抑圧して、標準化していく。あんまり人に理解されないような部分をどんどんどんどん自分の外に押し出していっちゃって、理解してもらえる感覚だけ残す。何とか理解してもらえるようになる、特に、広い意味で法の言葉として理解してもらえるような言葉を習得することが重要です。大抵の人間はその法律家ほどうまくやってないけどなんらかの形でやっている。とにかく、まあなんとか、ルールらしいことを理解して生きてると。
おそらく、植松の問題っていうのは、彼はたぶんそれをうまくこなせてなくて、普通のコミュニケーションの世界の中に入っていけないみたいな感じを何か持っていた、というところにあるんじゃないかなと。そうすると、さっきのホモ・サケル探しみたいなことをやりたくなる、自分は「いや、でもコミュニケーションできるんだ」ってことをどうやって訴えるか考えると、明らかに自分よりコミュニケーションできない人を指さして、その人たちと自分の間に線を引くのが手っ取り早い。そのときに、その自分が働いたこともあるやまゆり園、障害者施設であまり話をできない人がいるところに、意識がいった。無論、そういう人がいることぐらい流石に、最初に勤めた時から分かってたはずなんですよ。彼はもともと、コミュニケーションの限界に関心があったんじゃないかと思うんですよ。
阿久沢:高橋先生どうぞ。
6.法に基づいて障害者殺傷を決行した!?
高橋:今、ハーバーマスの問題が出ましたが、私はハーバーマスのコミュニケーション的理性ないしは合理性の起源はカントにあると考えています。そこに関わってくるのが、そしてたぶん今仲正さんがいった問題とも絡んでくる思うんですが、西角さんの本の326ページで扱われているカントとニーチェの道徳観をめぐる議論です。そこで西角さんが述べているニーチェの解釈については、ちょっといいたいことがあるのですが、それはさておいて、問題にしたいのはここでいわれているカントの「成人性」という概念なんです。これはカントが晩年書いた『啓蒙とは何か』という文章の冒頭に出てくる言葉です。私はこれが彼の人間理解のモデルだと思っています。成人性、ドイツ語で【Mündigkeit】といいますが、この概念によってカントがいおうとしているのは、言い換えればカントが成人性の条件として考えているのは、一つには言語のコミュニケーション能力であり、もう一つ、これが興味深いのですが、法的な責任能力を持ってることなんですね。これが成人性の条件であり、これを具えていることが一人前の人間であるということです。この人間観が問われなければならないと思います。
それから西角さんがここでの議論においてもう一つ触れている問題が、カントの根源悪の概念ですね。この根源悪の問題は西角さんのこの本全体の根本テーマともいえるものです。それについて私はこう理解をしています。ヨーロッパでは、特にキリスト教の伝統が成立して以来、じつは悪の問題が非常によく議論されてきました。なぜ絶対善としての神がいるのに、その神によって創造されたこの世界には悪が存在するのか、善きものとしての神がこの世界を善きものとして創ったのなら悪なんか存在するはずがないではないか。これはキリスト教神学をひどく悩ませてきた問題でした。ではキリスト教神学はこの問題にどう答えようとしたのか。それが「悪の弁神論」です。「悪の弁神論」によれば、神の絶対善の前では人間が犯すことの出来るあらゆる悪は結局相対的な悪にすぎない。つまり神の絶対善という予定調和に向かって最終的には解消することが出来る相対的な悪でしかないのです。
カントもまた、もちろんストレートに神学的な言い方をしてるわけじゃないけれども、基本的には人間の悪を相対的なものとして扱うことが出来ると。つまり人間が成人性を持ってる限り、自己陶冶の能力、自分の理性能力というものを通してこの相対的な悪を克服というか、統御することが出来る。それはいい方を換えれば、悪という法外なものを法‐外なものに置き換えて、法から排除しつつ法の内部へと包摂する、さっきのいい方をふまえれば法‐外なものを抑圧し制御するわけですね、カントはそれを、自分の中の法外なものを自分自身の法によって抑圧・制御するという構図で語っています。この自分の内なる法による法外なものの抑圧・制御としての自己陶冶の構図が、カントの倫理・道徳の根源である定言命法の内実に他なりません。その限りにおいて人間は、人間の犯す悪を相対悪の範囲に留めておくことが出来る。したがって悪を相対悪のうちに留めておく条件となるのが法の尊厳に対する敬意であり、その敬意をもたらす条件である人間の理性能力である、つまり成人性であるというわけですね。「悪の弁神論」を集大成したのはライプニッツですが、この点でカントはライプニッツを引き継いでいるといってよいでしょう。
ところが1755年、ポルトガルのリスボンで地震が起き、ヨーロッパ史上最悪の被害をもたらした。そしてこのポルトガル・リスボン地震は「悪の弁神論」に対して致命的ともいえる打撃を与えました。一番有名なのはフランスの啓蒙思想家ヴォルテールですね。彼は「悪の弁神論」に含まれる神の予定調和という楽観論を痛烈に批判します。そしてこの批判は、一方で神の予定調和に代わって人間の理性に基づく科学的認識の拡大深化を求めることに向かいます。この点ではカントも同じでした。
しかしそれだけにとどまらない問題として悪をめぐる認識の問題が出てきます。悪はどうも相対悪というだけでは片付けることが出来ないんじゃないか、という問題です。じつは、この悪の弁神論の崩壊以降の悪の認識という問題が我々に対して本当に切実なかたちで突きつけられるようになったのは20世紀であったと思います。それは、アウシュヴィッツに象徴されるナチス・ドイツの「ホロコースト=ショアー」という悪が20世紀に生じたからです。ちなみに昔、高橋哲哉さんと話をしたときに聞いたことですが、彼の計算によると20世紀において戦争や革命、それに伴う虐殺や飢餓などによって犠牲になり死んだ人の数は1憶8千万人に達するというのです。正確な数じゃないかもしれないけれど、だいたいそれくらいの人間が20世紀において死んでいる。こんな時代って他にはないですよね。人類の歴史を仮に10万年とするとその中で、一世紀、つまり百年の間に1億人を超えるような人間が、政治的な理由で、つまり自然死ではなく、なんらかの政治的理由で暴力の犠牲になって死んでいったのはおそらく20世紀しかないでしょう。この20世紀の特別な体験というものを通して、悪というものを、あるいはそういう悪との関係における法というもの、人間の理性というもの、そうした問題について改めて根本的に考え直さざるをえなくなった。そしてじつはこの悪をめぐる問題は決して過去のものではなく、今も我々の日常の中で繰り返されていることに気づかざるを得ないのです。それがこの植松の問題であるし、国家や政府が自らを支えるはずの法規範を自らの手で歪曲したり破壊したりするという前代未聞の事態を生んだ「森友・加計」問題もそうかもしれない。
とにかく我々は法というものを連続的かつ一元的な一つの体系だった秩序構造として考えがちなわけですが、じつはそんなものじゃないのではないか。法の隙間がいたるところにあって、その法の隙間に入り込んでいったときに、その法が法の対象である個々の事犯や事例を相対悪として処理するという建て前ではおさまらないようなある極限的な状況が生じてしまうのではないのか。つまり相対悪にとどまらない根源悪、絶対悪というべきものに法を通して遭遇する瞬間が存在するのではないか。ナチス・ドイツも、あのISですらも自分たちの「法」に基づいて「正当な」虐殺行為を行っているのですから。その限りにおいては、さっき言ったことの繰り返しになりますが、我々一人一人は法の内にある限り常にホモ・サケルになりうる可能性というものを負う形でしか生きていないんだということをやっぱり骨身にしみて認識する必要があると思うんです。誰もがみんな普通に暮らしてるつもりになってるけど、ある瞬間、我々がホモ・サケルの穴へとボコンと落ち込むという可能性を含んでいる。逆にいえば法が我々に強いているのは、そういう逆説的な事態、つまりいつでも我々は法-外なものにされる可能性を負ってるということを法が我々に対して強いているという事態であるということです。ちょっと抽象的な話で申し訳ないんですけど、私はそんな風に考えています。
阿久沢:稲垣さん今の議論を受けて、実際に起こってる事象としてはどんなことを思いますか。
稲垣:仲正先生、高橋先生がおっしゃった植松と法律との関係、もしくは暴力との関係について、あの事件で現実にあったエピソードで、「ああ、なるほどそうだな」と思うことがあります。彼は自分の手紙を立法府の長である衆院議長のところに持っていってますよね。それから「自分はこういう法律をつくりたい」と元カノに言ったりしている。あれはまさに、法というものに固執し、法に禁じられると余計に門の向こうに行きたくなるという行動の表れなんじゃないか。また、仲正先生が「今、植松自身がホモ・サケルになってしまった」とおっしゃり、高橋先生は「法にふれた瞬間、人はホモ・サケルになりうる」とおっしゃった。一方で、植松自身が刑法第39条の適用を受けたくないと言ったのは、「自分はホモ・サケルになりたくない」という一つの態度の表れなんじゃないか。しかし今回、死刑判決を受けたことで、彼自身の願いとは逆に、自分が法の外に置かれる立場になった。死刑制度については西角先生が、国家権力のホモ・サケルについて述べていらっしゃいますが、そこも話が符合すると思います。
阿久沢:ありがとうございました。私は先ほど高橋先生が仰ったハーバーマスの、法によってコミュニケーション能力を身に着け、自分の中に法外を押し出すというコミュニケーションの作法について、植松はツイッターという場所を非常に使っていたんですけども、ツイッターって両極になるんですね、高橋先生のお話を受けるとすると。自分の中の法外な部分を押し出す作業をしないで、本音と称して暴力的なことを言う。もしくは過剰に防衛的になって、自分の中の法外な部分はもうとにかく見せないように見せないようにすると。若い人たちのツイッターの使い方は本当に二極化していて、なんかそれがすごく面白いなと思いながら聞いておりました。それでは一旦ここで休憩を入れて、後半、優生思想について議論を深めていきたいと思います。10分休憩いたします。15時再開です。