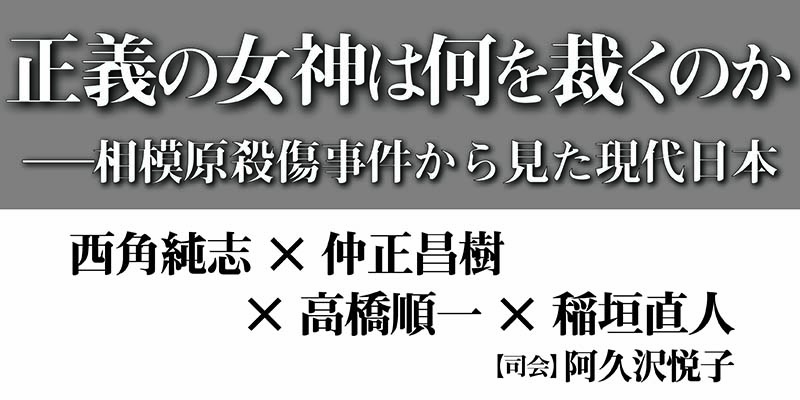正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本 第7回
2021年10月24日に開催された『元職員による徹底検証 相模原障害者殺傷事件―裁判の記録・被告との対話・関係者の証言』刊行記念トークイベント「正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本」(共催:明石書店・読書人、会場:神保町・読書人隣り)。西角純志氏(著者。専修大学講師)、仲正昌樹氏(金沢大学教授)、高橋順一氏(早稲田大学名誉教授)、稲垣直人氏(朝日新聞)が登壇し、阿久沢悦子氏(朝日新聞)の司会進行により充実した議論が交わされました。本記事は、その内容を採録したものです。
【毎月25日頃更新・全9回連載 ダイジェスト動画をYoutube明石書店チャンネルにて公開中⇒https://youtu.be/ZUmZHFgWico】
12.植松は優生思想なのか
質問者:先ほど着床前の診断でというような話がちょっとは出ていたんですけど、要するに妊娠中のたとえば重度の、さっきダウン症の話もちょこっと出てたんですけど、重度の障害児の場合にはどうするかっていうと、新聞で90%以上の人が中絶をするっていうような内容になっていたと思うんですね。で、それで結構、もちろん障害者団体やなんかが反対してるとかそういうのがあるので、まあ揺れ動いたのかもしれないですけれども。それが結構割と今の人に当たり前のように捉えられてるということだとか、あるいは安楽死ということが国によっては認められてる、法的に認められるところが出てきて、これからそれが増えていく方向にあるのかどうかっていうのはちょっと疑問の面もあるんですけど、私が西角さんの本を読ませていただいたときに、ちょっとびっくりしたのは、この植松という人は、19人だから手あたり次第だったのかと思ったらそうではなくて、相手が意思表示できるかどうかということを、途中からなんかいい加減になったみたいなんですけど、聞いて、そしてほんとに意思表示ができない、要するに喋れるかどうかということに集約しちゃうんですけど。そこで線引きをして、そういう人は要するに殺していいんだみたいな考えで、結構それにこだわってずっと、一つのところだったらその一カ所でそのぐらいの人数いったかもしれないけど、探し回ってやっているんですよね。だから、結構割と確信犯的に相手が死に値するかどうか生きてるに値するかどうかっていうことを彼なりのイメージはおそらく職員であった期間にできたんだろうなとは思うんですけど。
そういう発想というのが結局あるから、もう本人の意思がなければ、尊厳死でもたとえば植物人間だと本人の意思がないんだから、じゃあ死に至らしめていいんじゃいか、尊厳死とか安楽死がだんだん認められてるとか、あるいは重度の障害児の場合には中絶していいんじゃないか、そういう風潮のなかで、結構自分の考えを認められるみたいに思ってしまった可能性もあるのかなって思ったんですね。要するに、稚拙ではあっても総理大臣に手紙を書いたりしたわけですよね。要するに自分の、ただ突拍子もなくやったんじゃなくて、案外自分の考えが受け入れられると思ったのかなという感じもしたので、そういうところをどういうふうに捉えられるのかっていうのを。仲正さんがおそらくその、ちょっと優生思想とはズレてるんじゃないかっていうふうなことを書かれていたりしたので、そのへんをちょっとお伺いしたかったです。
仲正:私が最初に話した方が、他の人も話を続けやすいと思って、最初にお答えします。着床前診断の話って知ってる人は結構知ってると思うんですけど。ほとんどの人にとっては、たぶん他人事だと思います。だって仮想の状態を設定したアンケートに答えろと言われて、答えてるんだから。他人の子であっても、障害があれば中絶すべきだと積極的な主張する思想を持っているわけではないでしょう。自分のこととして考えろ、と言われても、本当に自分のことになるまで、考えないのが普通の人間でしょう。知的障害の遺伝的可能性っていうのはかなり微妙な問題になると思いますが、胎児が風疹とかの感染症にかかっているような場合だったら、中絶を選択したとしても、たぶんそんな責める人はいないと思うんですよね。感染症の場合は、着床前というより、出生前診断になるでしょうが、障害の可能性を理由にした中絶の理由になるという点では同じでしょう。
尊厳死、安楽死はまた別の問題だと思います。射水市民病院事件てありましたね、十数年前の事件ですが、ああいうことが行われていたのはとっくの昔にわかってたと思います。実際には事実上の、ソフトな形での安楽死が暗黙の裡に相当な件数行われていると思います。たまたま、同意書を取らないのはおかしいというふうに仰った看護師さんがいたおかげで問題として表面化したんだけれど、ずっと寝たきりの身内がいる人で、暗黙のうちに呼吸器を外してもらった、という話を聞いたことがない人はあまりいないと思うんですね。生命維持装置が意味がないので切る、ということにはっきり同意してやったら尊厳死になるけれど、はっきり言葉にしにくいので、阿吽の呼吸でやってる。そういうことは暗黙のうちにずっと昔から行われていた。少し着床前診断の話に戻りますが、遺伝子のことなど分かっていないずっと昔だったら血筋が悪いとかっていう言い方をして、結婚して子どもを産むのを避けるとか、いうことはあったんだと思うんですよね。そういうのは全部差別ですよ、暗黙のうちにやっていたことが、近代科学のおかげで顕在化したわけです。
ただ、生きている人間とそうじゃないものの境目は決めないといけない。たとえば脳死状態の人はどっちかという問題は、いくら議論しても絶対終わりません。本質は、生死、人間という共同体の境目をめぐる価値観の話です。どこかでこれは線を引かないといけない。ただ、性急な答えを求める傾向が強くなっていると思います。着床前診断の問題でも、今の段階だったら、当事者以外はああでもないこうでもないと言ってるだけに過ぎないと思うんですね。無理に答えを出そうとすると、優生思想に傾いていくと思うんです。思想研究をやってる人間は、ここから先に行ったら、もう単なる議論ではなくて、答えを決めてそれを制度化する社会運動になってしまうから、ここから先に行ったらもう危険だぞという、抑制装置の働きをすべきだと私は思うんですけど、そうじゃない人、対立を煽る人が多い。人間には、ある程度、はっきり意識してなくても、自分の身体能力とか、自分が障害を持って生まれてないのを「あ、まあよかったな」と感じるような発想はあると思うんです。近代科学は、そうした潜在的差別意識に根拠を与えて、助長しているところがあるので、それを抑制する必要はありますが、自分と他人の能力を比べる発想を根絶することはできないし、そんなことを目指す方が遥かに危険です。誰かかわいそうだなと思った時点でそれは見方によっちゃもう差別にすでになってるんですよね。
高橋:そう。
仲正:で、それがどこかで、自分についてのネガティヴな発想がふくれあがっていったとき、植松的なものになっていく。着床前診断が本当に危険なのは、それが政策になってしまうときでしょう。ただ、これは医療の難しいところで、コロナの話だったら全部政策が表に出てきちゃってるけれど、人間の生死に関する話って基本的には表に出てこないところで進みます。気付かないうちにそういうものが浸透してしまってる可能性というのはあると思いますよね。ただそれは防ぎきれはしないと思うんですよね。着床前診断じゃなくても、遺伝子レベルで判断して産む産まないを決めるいろんなやり方があると思いますから、迂回手段はいくらでも出てくると思います。で、政策になりかけたらやっぱりちょっと危険だというふうに言わざるを得ないんだけれど。やっぱり個人が選択するのを責め始めると、たぶんね、すべてがもう差別だっていうことになりかねないので、かえって危険だと思ってます。
阿久沢:それは安楽死についても同じですよね。個人が、私がこうなったら安楽死したいと願うことは止められないけど、それが政策的なトレンドになると危ない面をはらむとか。
仲正:うん。そう。暗黙のうちに今やってると思うんですよね。その病院の方針とキャパシティ、行政の裁量、と思います。病院とその患者さんの懐事情のバランスが合わさってなんとなく決まってる、と思います。
高橋:確かににそうですね。そこで考えたいのが安楽死に関してなんです。とくに安楽死は自己決定権に属するというようないい方の問題です。自己決定権、自分の命に対して、あるいは場合によっては他者の命に対して、自分で決定する権利が存在するという考え方ですね。これって現実の状況の中では、今仲正さんがいったように、非常に難しい問題をはらんでいると思います。治る見込みのない中で、あるいは激しい苦痛にさいなまれる中で、延命治療を続けるよりは安楽死を選ぶというのはやむをえない選択であると考えるのは無理ないと思います。でもそこで思考停止してしまってよいのか。我々は自己決定とは何か、自己決定は本当に自己決定という言葉によって表されようとしているものでありうるのか問う必要があるんじゃないかと思うんです。自己決定って一体何なのか、何をもってして自己決定っていえるのか。
さらにいえば自己決定の遂行が他者の決定の侵害になる場合もありうるのではないかという問題もあると思います。たとえば着床前診断でいうと、それは、母親ないし父親、場合によってはそれ以外の親族縁者も含めた大人たちの自己決定による、他者として産まれてくるはずの子どもの排除・抹殺につながる可能性をやっぱり否定出来ないですね。だから仲正さんがいうようにどこで線引きをするかが本当に難しいと思います。とりあえず考えるのは、我々のような思想に携わる人間なら、ある種の思考実験をしておかねばならないのではないかということです。たとえば重病にかかった人間なら誰でも無条件に安楽死を選択する権利を持つと法律に明記することを想定してみる、というようなことです。思考実験の中ならばいくらでも極限状態を想定して思考することが出来るわけですから、それ以外にも極限的な状況を想定してみた上で、起きうる可能性をあれこれ吟味してみることが可能です。もしかするとそれは現実的にはあまり有効性のない議論になってしまう可能性もあります。しかし私はそういう思考実験をやっぱりやってみる必要があると思うんですね。で、そのうえで自己決定や自己決定権が本当の意味での自己決定たりうるのかを考えてみる。上記の安楽死の法への明記にしたって、介護に疲れた家族が本人に安楽死の選択を迫る場合が容易に想定できます。そうするとこの安楽死は合法殺人になりますよね。植松の障害者無用論はこの合法殺人を目指していたともいえると思います。
ひとつ自己決定という問題に関して思い起こされるのが、さっき名前が出たフーコーの規律=訓練権力という概念です。あるいはむしろ西角さんが本の中で触れていたパノプティコンの例を考えたほうがよいかもしれない。パノプティコンというのは、イギリスの功利主義哲学者ベンサムが発明した一望監視装置のことです。この装置の下では主体は、監視する者の視線をたえず内面化することによって、監視者の視線とともやってくる他律的な強制、あるいはそれによってもたらされる規律を自分自身へと内在化します。このプロセスが訓練のように反覆されていくと、主体は他律的強制および規律をあたかも自分自身の意志、つまり自己決定の産物であるかのように錯覚するようになります。これが規律=訓練権力の作用であり効果です。自己決定だと思っているものがじつは監視のもとで他律的に強いられたある種の強制の内在化の結果にすぎないということです。病気で苦しむ人間に「もうお前は助からない、生きていても無意味だ」と繰り返しささやきかける状況を想定してみてください。そのひとはやがてこのささやきを内面化し、自ら生きることを断念してしまうかもしれません。これは果たして自己決定といえるでしょうか。たしかにこれは非常な極論に聞こえるかもしれません。でもある種の思考実験を行えば、主体が、そして主体の自己決定などというものがある種の錯覚や妄想に過ぎないとさえいえることが見えてきます。こういうこともやっぱり視野におさめておく必要があるのではないかという気がします。仲正さんの前でこういう話をするのはちょっと気が引けますが。
仲正:自己決定の話もですけど。ちょっと言い忘れてました。リベラル優生学というのが、20世紀の終わりころからあります。これはネガティヴな要素を取り除くというより、ポジティヴな方に発想するんですね。病気に罹りやすい遺伝子を取り去って、健康や体力を増強するわけですねと。で、そういうのは普通まあ、「それがなんで悪いんだ」っていう人がいると思うんですよね。着床前診断で障害を持ってきそうな子を堕胎するというようなネガティヴな排除は駄目だという人も、遺伝子治療とか増強で健康にすることには反対しないかもしれません。大人になってから遺伝子治療をやる人もいるのに、着床前にできたらいいじゃないかと考えられますね。
でね、それがちょっと難しい話になるのは、じゃあ身長を伸ばすだとか頭をよくするとか、どうなんだ、と。これは難しいですよね。これはサンデルが、『完全な人間を目指さなくてもよい理由』ってタイトルで、原題が【The case against perfection】という本で論じている問題です。病気はたぶん誰も文句は言わないだろう、じゃあ身長は? 頭を良くするは、目の色を変えるとかだったら、抵抗する人いるだろうけれど、線は引けません。そのままだったら障害を持って生まれる子の遺伝子に操作を加えて、障害がないようにできればいいじゃないか、と。今の技術じゃ難しいだろうけど、そのうち、可能になるかもしれません。それでもあなた反対しますかっていうとこれは結構難しいですよね。その技術が明らかにあるのに、それでもやっぱり障害は個性だというふうに捉えて、そのまま着床させますか。これはかなり難しいと思いますよね。不妊治療の場合だったらいくつか受精卵をつくりますよね。で、そのうちの着床させたいと当初予定してたのがポジティヴ遺伝性の病気が発病する可能性が高いやつだった、と。で、こっちのほうはそんなに高くないと。じゃあと入れ替えたら、これは差別か。これは潜在的には確かに、障害を持ってる人に対する差別になるとは思いますけれど、じゃあその個体に対する差別なのか。胚はもう人間だっていう人いるけど、胚はまだ人間じゃないっていう立場をとるんだったら、これは必ずしも差別じゃないですよね。
技術が発達してくると、差別かどうかの線がかなり微妙になってきます。少なくとも病気に関してはいいだろう、ということになりそうです。するとね、たぶんこういう話になってくるんだと思います。金持ちだったら遺伝子治療で病気や障害ができにくい状態の胚だけを着床させられる。で、貧乏人はできないと。そうすると差別だってこうなりますよね。そうすると、いや、それだったら平等にできるように、ということになるでしょう。つまりリベラル優生学の人たちは大体そういうふうに議論を持っていって、だったら結局利用することになるのではないでしょうか、と。それそこまで反対しますかと。今はなおす道がないから障害者差別につながるって考えているのでしょうが、今生きてる障害者の人に対する差別と、将来の可能性とは別で考えられないでしょうかと、言われたら、そう簡単にやはり差別につながることはダメだと無碍に否定しにくくなります。今だと、まだサイエンスフィクションですけど、その技術ができたとき、難しい問題になると思います。