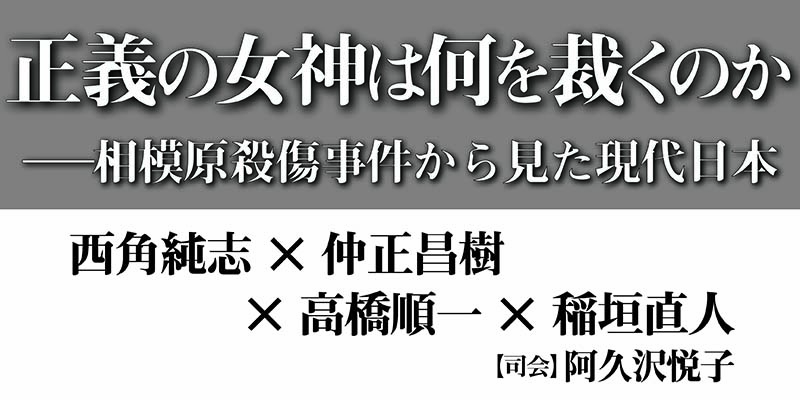正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本 第8回
2021年10月24日に開催された『元職員による徹底検証 相模原障害者殺傷事件―裁判の記録・被告との対話・関係者の証言』刊行記念トークイベント「正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本」(共催:明石書店・読書人、会場:神保町・読書人隣り)。西角純志氏(著者。専修大学講師)、仲正昌樹氏(金沢大学教授)、高橋順一氏(早稲田大学名誉教授)、稲垣直人氏(朝日新聞)が登壇し、阿久沢悦子氏(朝日新聞)の司会進行により充実した議論が交わされました。本記事は、その内容を採録したものです。
【毎月25日頃更新・全9回連載 ダイジェスト動画をYoutube明石書店チャンネルにて公開中⇒https://youtu.be/ZUmZHFgWico】
西角:優生学の歴史を振り返ってみると、ゴルトンみたいな古典的な主流派の優生学があったのですね。今では、「選択的中絶」という「自発的優生学」という、新しい優生学というのが誕生しています。「自発的優生学」というのが、特に1990年代以降は浮上してきて。特に2018年から新型の出生前検査(母体血胎児染色体検査/NIPT)という血液検査で障害の有無がわかるという検査です。2018年までの9月までの5年間の間に約6万5千人がこの検査を受けて、最終的に胎児の染色体に変化があると確定した妊婦の9割以上が中絶しました。それが選択的に中絶したということなんですね。2018年の春には産婦人科学会が臨床研究として行っていたNIPTですね、要するに新型出生前診断を一般診療として実施してきてたわけです。これが保険外診療で行われました。自己負担です。今、政府は高額な治療費について問題にしています。保険外診療としての実施で遺伝カウンセリングなどが条件になっていましたが、2019年には研修を受けた産婦人科医による説明と情報提供に簡略化されようとしています。斎藤環さんという精神科医の方も言っておられましたが、選択的中絶というのは母親の当然の権利なんですね。なぜなら誕生するまでは母親の臓器の一部であるからというのです。出生前診断で中絶を選択するのは生命の価値判断ではない。母親の決定権である。こんなことを言ってますよね。僕はこれを感じてですね、生命の問題は価値判断が不可能な問題、価値判断不可能性ですよね、差別か否かではなくて価値判断の不可能性。社会科学では価値判断論争というのもありましたけど、そうではなくて、価値判断の不可能性こそ問われなければならないと思いました。
「自己決定」というと確かにそうなんだけど、小松美彦先生の話によるとそれがある種の「自己決定の罠」に陥ってるといいますね。小松先生も事件に関心をもたれて、『「自己決定権」という罠』(言視舎、2018年)に収められた論考「鏡としての『相模原障害者殺傷事件』」を新たに書き下ろされました。これを植松に差し入れたことがあるんです。植松はとても評価してました。小松先生の名前とかも書いてあり、小松先生にも議論で加わっていただきたかったのですが、体調が悪いということで残念です。『「自己決定権」という罠』の論考には植松の「人間の条件」が検討されており、ポイントをきちんと押さえてられていると思いました。『テッド2』の人間の条件がそうです。「自己認識ができる」、そして「他人と共有できる」、それから、もう一つ、「複合感情を理解できる」。この三つが人間の条件だと言います。僕は面会の時に彼に何度も確認しました。理性、良心を持ってないと形は人間でも人間はないんだと。意思疎通がとれなければ、人間ではないんだと。人間の尊厳の基準というものを彼なりにかなり深堀してるんですね。
この人間の尊厳の基準というか、人間の条件と言い換えてもよいかもしれませんが、高橋先生が何度も話に出されたカントのいわゆる「人間性の尊厳」という定義ということにも関わってきます。人間の尊厳というのを哲学史上にきちんと定義づけたのはカントなんですね。要は人間というのは、理性と良心を持っているんだと。理性と良心をもっていないのは人間ではないということですね。古代においては国王とか権力などの高貴な身分に人間の尊厳があったと。だから一部の高貴な人間だけには尊厳が備わっていたと考えられたけど、古代ギリシアではアリストテレスが人間は理性的な動物と言います。キケロは人間は理性をもっており、動物よりも優越してると。中世になるとキリスト教が入ってきて人間の尊厳というように認識が変わってきます。キリスト教では元来神のみが尊厳があるということでしたが、人間は、神の似姿として創造されたという認識になってきます。カトリックでは自由と結びついた尊厳が優性でしたが、プロテスタントでは万人司祭主義の基礎となった平等が思想と結びついていきました。ルネサンスの時期になるとジョバンニ・ピコ・デラ・ミランドラですが、ピコが登場すると人間の尊厳というものの卓越性が強調されます。人間の本性は予め確定されておらず、人間は自由意志によって自己自身の本性を決定できるのであって、それには神的なものに向上することもできれば、動物に凋落することもできる。だから人間は自由意志によって低次の存在を選び取ることができるし、高次の存在を選び取ることができる。このような人間の自由意志のうちに自己実現というものに人間の尊厳や卓越性を見たと。この後に人間の尊厳は、ベーコンだとかデカルトとか、パスカル ロック、ディドロ、ルソー、カント、ハイデガー、と続くんですね。そして人間の尊厳の概念を哲学的に定義づけたのはカントです。これがカントの『道徳形而上学の基礎づけ』です。そこで先生の話もつながってくるという話なんですね。
質問者:すいません、たとえばその、自己決定というのと関連するんですけど、生きるに値する、それから、安楽死の場合だと、たとえば自己決定を尊重しましょう、みたいのがあれば別なんですけど、生きるに値する生かどうかっていうことを植松という人は自分で考えてやってしまったわけですよね。じゃあ死刑の問題を考えた場合、国家は生きるに値する生かどうかっていうことを、まあ裁判ということですけど、鑑定していいんだというような考えに今おそらくなってるわけですよね、その人間の条件が。だから、そこの矛盾というのはないのかなって思うんです。
阿久沢:いや、すごい矛盾してる…。
仲正:生きるに値する生かどうか。でもね、ある人の生が人間として、生きるに値する生かどうかっていう価値判断と、それを自分で実行するかどうかってまた別問題ですね。通常は切り離されてると思うんですね。だから、「お前人間じゃない」って軽く言うときありますし、こんな奴はもう人間扱いしたくないと、腹が立ったらそういうふうに思うときありますし、こんな奴とは実際もう人間じゃないから縁を切りたいと、それぐらいのことはあると思うんですけれど、ただ普通は自分じゃ実行しに行かないですよね。自分自身が犯罪者になって大変なことになるから。自分がやらなくても、国家が、共同体にとって害をなすものは、排除する。命を奪うこともある。今の西角さんの話との関連で、カントが理性による自己決定のようなものを人間の基準にしたっていうのは、近代になってからの話で、それ以前には、共同体の秩序が第一で、原初的には共同体にとっていてもらっちゃ困る者を抹消していた。ただ単純に抹殺されるんではなくて、その者が存在することによって、逆に、共同体の秩序がわかるような存在というのがホモ・サケルであったと思うんです。ホモ・サケルが共同体にいてはならない存在だとしたら、そうではない者は、共同体の内側にいていいことになる。死刑っていうのは、ある意味、ホモ・サケルを継承しているのではないかと思います。生きるに値するしないっていうのは、普通の人はたぶん、自分の問題としては考えてないと思うんです。自分は当然生きるに値するんですが、他人については、どうせ自分が殺されるわけじゃないから、他人事なんですよ。
植松の話でやっぱり特殊なのは、わざわざ自分を滅ぼしてまでも、その自分から見て生きるに値しないと思ってる者を消滅させようとしたこと。つまり、彼自身も実は、なんていうかな、犯罪を犯してからホモ・サケルになったというよりは、実は自分は日本という共同体のちゃんとした一員だという意識を持ってなかったんだと思うんですよね。自分が日本の一員であれば、自分を生かす方法というのをまず考えたと思う。で、それをわざわざ殺しにいくっていうのは結局自分、「自分自身が大切じゃないな」ってよくドラマでよくあるような心境だったと思います。でも、この場合、本当にそうだと思います。人を殺したら必ず自分に振り返ってきて自分が消滅してしまう。それをやってしまったということは、自分はこの日本という共同体、あるいは人類という共同体の中にいれてもらえないという絶望感があったんだと思います。そういうものを、実はみんな抱えてるっちゃ、抱えてるんだけど、我々の多くはなんか、自分を騙し騙しながら、日々を送っているだと思うんです。問題は自分を騙しきれなくなる人が目立って出てきている。じゃあどうして、自分を騙しきれなくなったのか、どうして自分は共同体の一員ではないかもしれない、境界線の向こうに押し出されているように強く感じてしまうのか。それがなかなかわかんないです。
高橋:ちょっと違う観点から話をさせてください。またフーコーの話になりますが、彼の『狂気の歴史』という本のことです。さっき西角さんが、正義の女神が出てくるのは15世紀から16世紀にかけてのドイツの作家ゼバスティアン・ブラントの『阿呆船』であるといいましたが、じつはこの『阿呆船』の物語が『狂気の歴史』という本の内容と非常に深く関りがあります。『狂気の歴史』は、ちょうどルネッサンスから近代、フーコーがいうところの古典主義近代が始まる時期の、ちょうど境目にあたる時代を問題にしています。『狂気の歴史』によれば、この時期にヨーロッパでは「狂気」というものの扱いというか見方が劇的に変わります。古典主義近代が始まると狂気は精神の病、精神病理とし医学的治療の対象になります。病者を隔離し治療する施設として精神病院がつくられるわけです。狂気は病となり、いわゆる「狂人」は病者、患者として病院に収容されます。これは「狂人」が社会から隔離され、社会の中で不在化・不可視化されることを意味します。今まで我々が議論してきた問題の一つの起源はこの「狂気」の病気化、それに伴う隔離・不可視化(それに伴う差別・抑圧)にあると思います。
ではそれ以前「狂気」はどういうふうに扱われていたのか。それを知る手がかりになるのがゼバスティアン・ブラントの『阿呆船』なんですね。あるいは『阿呆船』とほぼ同時代のヒエロニュムス・ボス(ボッシュ)という画家が描いた「愚者の楽園」を思いおこしてみてもよいかもしれません。この絵はスペインのプラド美術館やミュンヘンのアルテ・ピナコテークという美術館にあります。ブラントやボスを見ると、「狂気」が我々の考えているような形、つまり隔離の対象や治療の対象というような形とは明らかに異なる形で扱われていたことの痕跡が浮かび上がってきます。一言でいうと「狂気」は特別なもの、聖なるものであった。少なくとも社会から抹消されるべき対象ではありませんでした。では「阿呆船」とは何か。これは、共同体の中にいる狂人たちを船に乗せて川に流したことに由来します。

ゼバスティアン・ブラントの諷刺文学『阿呆船』(1494年)
【出典】尾崎盛景訳『阿呆船』(上)現代思潮社、1968年、8頁
これは排除に見えますが一概に排除ともいえない。むしろ特別な存在である彼らの生きる場所を保証するという面を持っていました。まさに「愚者の楽園」ですね。ちょうど時代の境目を生きたブラントやボスに近代とともに始まる狂気への差別の要素が全くないとはいえませんが、その一方で狂気を特別なもの、聖なるものと見なす感性が明らかにまだ生きています。
もう一つ違う例を挙げておきましょう。未開社会にトーテム信仰があることはご存じだと思います。それに関して大学時代に人類学を教わった先生から面白い話を聞いたことがあります。トーテム信仰というのは共同体の中である家族が、特定の動物を自分たちの祖先神として祭ることです。つまり一種の祖先信仰です。人間の側の祖先もいて、自分たちは人間の祖先神と動物の祖先神の共同の子孫であると考えるわけです。動物と人間が一緒に祖先になるというのも面白いけれど、さらに興味深いのは、そのときトーテムになる動物は思いっきり醜く悪辣な、要するにこれ以上ないほどネガティヴな存在でなければならないということなんです。つまりネガティヴの極限に行かないとトーテム、つまり神になれないんですね。これは聖と醜、賎の逆転です。聖と醜、賤を置き換えてしまうわけですね。
そして私は、この、もっともネガティヴなものをもっともポジティヴなものへと反転させるというトーテムの作法には、近代が始まって以降人類が忘れてしまった偉大な知恵が宿されていたのではないかと思うんです。ブラントの『阿呆船』やボス(ボッシュ)の「愚者の楽園」に保存されているのもこうした知恵だったのではないか。そしてこれらの作品に宿されている失われた知恵の痕跡を解読する術を教えてくれたのがフーコーの『狂気の歴史』だったのです。共同体、あるいは社会にとって客観的に見ればネガティヴでしかないもの、存在してはならないもの、存在に値しないもの、それを一気に聖なるものへと百八十度転換させてしまうという知恵を、近代以前の共同体社会、あるいは未開社会は持っていた。だが近代という時代はそういう知恵を失ってしまった。狂気を精神病理というネガティヴな病の範疇へと封じ込めてしまった。その結果ネガティヴなものは永遠不変にネガティヴなものでしかありえなくなる。もうポジティヴなものへと転換するチャンスは存在しないのです。したがって我々の社会の中で今そうした近代以前の共同体社会や未開社会に住む人たちが持っていた、聖と賤、聖と卑しいものとの価値転倒によってネガティヴなものをポジティヴなものへと一挙に救い上げるという知恵をそのまま蘇らせることは不可能でしょう。我々の社会は強い者、勝者のポジティヴティが永久に続く世界になってしまっているからです。
ただこうした知恵を生かせないまま捨て去ってしまうというのはいかにも惜しいんじゃないかなと私は思うんですね。そしてこうした知恵を生かすのにいちばん邪魔になっているもの、こういう知恵を潰してしまう一番の元凶となっているのが自己決定という考え方、より正確にいえば自己決定をつかさどる「主体」こそがまっとうな人間のあり方だという考え方、理性を持った主体の自己決定を絶対化するような考え方だと思います。でもここの人間って実際にはそんなに大したもんじゃないのではないか。そのとき大したことのない人間を生かしてくれるのが知恵なんです。知恵は理性の産物ではありません。あの中世末からルネサンスの初めにかけての時代にまだ残されていた知恵、フーコーのいう古典主義近代の世紀、啓蒙理性の世紀が始まるとともに消えてしまった知恵について考えるとき、これを失ったことの代償がいかに大きかったかというのが、今日ここで我々が語ってきた問題の根源なんじゃないかという気がします。ちょっと荒唐無稽な話に聞こえるかもしれませんが、私はそんなふうに思います。