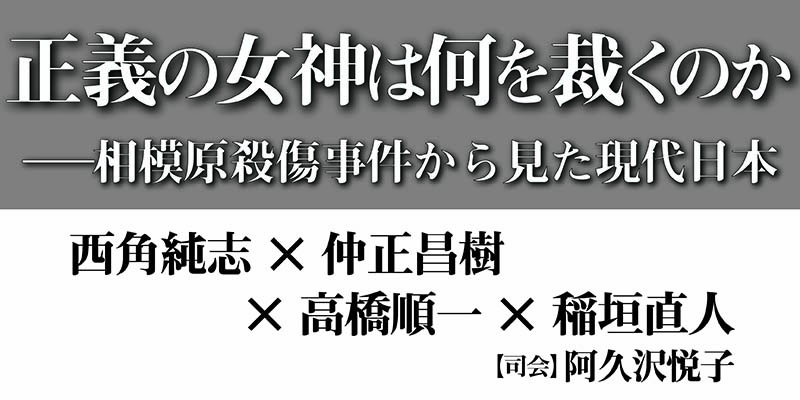正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本 第5回
2021年10月24日に開催された『元職員による徹底検証 相模原障害者殺傷事件―裁判の記録・被告との対話・関係者の証言』刊行記念トークイベント「正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本」(共催:明石書店・読書人、会場:神保町・読書人隣り)。西角純志氏(著者。専修大学講師)、仲正昌樹氏(金沢大学教授)、高橋順一氏(早稲田大学名誉教授)、稲垣直人氏(朝日新聞)が登壇し、阿久沢悦子氏(朝日新聞)の司会進行により充実した議論が交わされました。本記事は、その内容を採録したものです。
【毎月25日頃更新・全9回連載 ダイジェスト動画をYoutube明石書店チャンネルにて公開中⇒https://youtu.be/ZUmZHFgWico】
9.パターナリズムと人種差別
高橋:コロナワクチンがそうですね。
仲正:コロナ、そう。今では出産の問題はちょっと別だっていうふうな感じになってきてるんだけれど、かつては、その出産の問題も含めて、医師にまかせていた。インフォームドコンセントが一般的に認知されるようになったのは、大体ニュルンベルク裁判以降だとされてますけど、一般的な判決の中に出てきはじめるのはアメリカでさえ70年代で、日本だったらもっと後です。今ではインフォームドコンセントをやらなかったら、たとえ医学的に正当でも勝手に侵襲したら違法であるって、ことになりました。ただ、実際の判決ではなかなかインフォームドコンセント違反だけで、損害賠償を取るのは難しいし、ましてや刑事責任を問われることはめったにない。本人のためを思ってという理屈、パターナリズムに抵抗するのは、生命倫理の教科書に書かれているほど簡単ではありません。パターナリズムと人種差別、障害者差別が結び付くと、問題の所在が見えにくくなります。優生思想とかある程度意識して勉強して、社会批判的な意識を持っている人だったら、パターナリズムこそ問題だと言うかもしれませんが、パターナリズムの人は自分でそうだと名乗りません。知らないうちに、パターナリズムに取り込まれるというのはよくあることです。市民運動家って、結構、無自覚にパターナリズムの発想をしていますから。弱い一般市民のために、彼らの代わりに自分たちが発言しているんだって感じで。
こう言うと抽象的な議論に聞こえるかもしれませんが、20世紀の終わり頃から、クローンの子どもが生まれたらどうするかっていう、議論がありますね。今のところ、クローンチャイルドとして認定されている人はいないので、SFの話みたいになっていますが、そんなに非現実的な話ではないはずです。たぶん実際クローンの子どもが生まれたら、人権をちゃんと認めざるを得ないと思うんです。ただ、テロメアとの関係で寿命が短いとかってそういうことがおそらくわかるでしょうし、普通の人とどこが違うかいろいろ検査されることにはなるでしょう。じゃあね、クローンの子が産まれたら差別されるとわかってるからクローンの子どもはつくるべきじゃないっていうふうに言っていいのか。我々は今発言を求められたら、たぶんそういうことを言いますね。でも、実際クローンの子が産まれた、私たちがかつてそういう発言をしたと判明したとする。「お前差別に加担したのか」って言われたら、ギクッときちゃいます。「お前それ言説広めただろ」と。クローンだったらまだしも、キマイラ細胞で一部人間じゃない細胞を持ってる子がひょっとしたら産まれてきて、人権を認めざるをえなくなるということはあるかもしれないですよね。我々はそんな子をつくるべきじゃないって今は言いますよ。だけど実際産まれてきて、私や高橋先生や西角さんがそういうことを言ったというような記録が残ったとします。お前たちは私の人生を否定したのかってたぶん糾弾されますよね。優生思想による断種の背後には、実はそれと同じタイプの問題があるわけです。そういうのってどこで線を引いたらいいのかって分かりません。着床前診断というのはやっぱり差別につながるっていうふうに、青い芝の会の運動とか知ってるとそう思えてくるんだけど、その結果を直接引き受けるのは、当事者の家族ですし、障害というより、病にかかる可能性だってあるわけでしょう。差別につながるものは一切ダメというわけにはいかない。
もう一回植松の話に結び付けると、植松とナチスがなんで近いように見えるかっていうと、普通の人間はせいぜい軽いパターナリズムなんですね。他人のことにそこまで構わない。構いすぎて、固執して、殺してしまう。ナチスと違って、植松は、それ本人のためと思ってやったわけですが。そして、優生とそうでない生の区別があまりに強引なところが、ナチス的ですね。ただ、優れた子孫を残すという思想自体が問題なのか。これはドウォーキンって法哲学者が言ってるんですけれど、配偶者選びからして、相手を選んでいい子孫を残そうとする行為ではないか、人間がペットや植物を品種改良しているのと、なんか違うのか、と。いや、原理的にいったら、確かにそうなんですよね。自分にふさわしい配偶者を選んでるという時点で、お前は優生思想だと。でそこまで問題にできるのかって、考え始めると…。だからね、あまりにも動機を掘りすぎたら、生殖に関するあらゆる選択が不可能になってしまいます。優秀なパートナーがほしい、優秀な子孫を残したいという欲望さえ持っていけないということになったら、それこそ全人類を、宗教的に洗脳し、人格改造するしかない。差別反対運動のラディカルな人も、そこまでは言わないようにしているでしょう。それを言い出すと、どっちがファシストだっていうことになるから。それでもナチスの発想がやはり許しがたいとすれば、選別するという発想に開き直って、行くところまで、最後はもう絶滅させるってところまで、行ってしまったことです。ごく普通の人でも、そういう人が産まれたらかわいそうだ、自分の子だったら育てきれないかもしれないなと、想像するだけで終わりです。心の中でちょっと思うだけ、口には出さない。口に出して言ってしまうと、まずいと分かっているので、黙っている。しかし植松は、そこに拘ってしまって、自分も死刑になると分かっているのに、わざわざ殺しにいってるから、理解しがたい。でも、先ほどお話ししたように、彼が自分と近いものを感じていたとしたら、心の中でかわいそうな人たちと思うだけでは済まなくなってしまうような気がします。ここで、自分と彼らの間に分かりやすい線を引かないといけないと、なぜか思い込んでしまった。
人間はある意味、自他の差別によって、自分を際立たせないと生きていけない存在だけど、その線を相対化することが大事なのではないかと思います。障害を負ってる人とかいろんなハンデキャップを負ってる人と、なんとなく普通に生きてるような自分との間には何となく距離があるけど、絶対的な境界線があるわけではなく、皆なにがしか、部分的にホモ・サケルなんだ、つまり、人間の標準形にはなり切れない、弱みを抱えている、いつ何かの拍子に完全にホモ・サケルになるか分からない、くらいに思って、何とか日々をやりすごすしかない。自分がもう境界線ぎりぎりだと思ってしまったら、この法の外の存在と一体化しつつある自分をどうする、彼らを受け入れるか抹殺するかみたいなふうに、思ってしまう。この存在を認めてしまったら自分も一緒に人間じゃなくなってしまうかもしれない、というような突き詰め方をするとまずいんです。第三者的には、植松はそこまでは追いつめられてないと思うんですけれど、本人にとっちゃ、もう境界線が見えてしまったのかもしれない。だから問題で、彼がなんでそこに境界線を見てしまったのか、ということですよね。
10.大河ドラマ「青天を衝け」から見る日本近代
高橋:どこから話をしようか考えていたんですが、ちょっと意表をついたところから話を始めたいと思います。今NHKの大河ドラマで「青天を衝け」をやっていますね、渋沢栄一が主人公の。そのドラマで今ちょうどやってるところですが、大久保利通や岩倉具視が欧米視察に行ってる間、留守政府が政府を預かってる時期があります。1871年から1873年です。留守政府の一番中心にいたのが大隈重信、あるいは江藤新平といった肥前佐賀の人間と西郷隆盛でした。面白いのは、留守政府がやった施策が明治日本の近代化を考える上で決定的ともいえる重要性を持っていたということなんです。大久保は自分たちが留守のあいだは何も変えるなといって出かけていったんだけど、じつは留守政府は1872年から立て続けにいろんな施策を実行しています。一番よく知られているのは鉄道敷設です。それから地租改正もそうですね。しかし私が一番注目したいのは、学校令と徴兵令という二つの施策です。先ほど西角さんが言ったように、明治政府は富国強兵・殖産興業に象徴される近代日本の発展を目指すために必要なさまざまな施策を行っていますが、じつはその起源に位置してるのがこの徴兵令と学校令だと私は考えます。なぜか。この二つの施策は、日本人の身体を近代社会、近代国家に相応しいものに作り替えるための施策だったからです。政府が国民の身体の作り替え事業を行う。奇妙に聞こえるかもしれませんが、ぜひそれをやる必要があった。なぜか。それは、工場で働く、あるいは工場で働けるための生産的な身体が近代化にはどうしても必要だったからです。
学校令が1872年に発せられ全国に小学校がつくられます。このとき一番苦労したことが二つあった。一つは、時間で区切った行動を生徒にとらせることです。それまでの日本人の中には時間で区切るという発想がなかった。朝が明るくなったら農作業に行って、暗くなったら帰ってくると。そうすると、これ夏だったら明るくなるのは4時ですよね。それがだんだんだんだん遅くなっていって、もうぎりぎり農作業が、まあ今頃ちょうど農作業が終わる頃かな。この頃になると大体6時とかそれぐらいになる。つまり決まった時間で動いてないわけです。明るくなったら動き始めて暗くなったら止めるという行動パターンです。これは基本的に農民の行動パターンです。しかしこれでは工場で働く行動パターンには当てはまらない。時間で動くという行動パターンとそのもとになる身体感覚を日本人に習得させなければならない。これは工場で働くために絶対に必要なことだからです。
それからもう一つは、椅子に座って机に向かうという姿勢をつくることです。それまでの日本人の身体図式の中には椅子に座って机に向かうという姿勢はないわけです。ほとんどの日本人はそんな姿勢を体験したことはない。立っているか、寝そべってるか、床にペタンとお尻をつけてるかそういう姿勢しかないわけです。その姿勢しか知らない日本人に椅子に座るという姿勢を身につけさせようというのです。これもやっぱり、工場や学校や兵営のような近代化のために必要な施設に適合する身体を作るための身体規律を一人一人の主体へと内在化させることが近代化にとってどうしても必要だからです。つまり近代化にはある一定の規律を具えた身体、より正確にいえば規律の下に働ける生産的身体が必要なのです。近代化の源泉となる経済的・産業的価値を生産するとともに、国家のために兵士として戦うことの出来る身体です。
ではこの生産的身体のモデルはどこに求められるのか。それがさっき触れたカントの「成人性」ですね。少し極端ないい方に聞こえるかもしれませんが、この「成人性」をモデルにして生産的身体を考えるとすれば、そこに浮上して来るのは、健康な成人男性、これだけが生産的身体のモデルである、つまり社会において価値を生産することの出来る人間のモデルであるという考え方です。裏返していえば、健康な成人男性以外の人間は人間の範疇には入らない。そうした連中は人間ではない、少なくとも社会にとって有用かつ有意味な存在ではない、だから社会から排除しなきゃいけない、一人前の人間として扱ってはならない、という考え方です。そこでまず女性が排除の対象になるし、子どもも排除の対象になるし、もちろん病人も排除の対象になるし、高齢者も排除の対象になります。彼らは生産的な身体を持っていないからです。なぜ女性なのかと思われるかもしれませんが、この時代の性差役割分業の下では女性は家事労働や出産といったような、価値を生まない、賃金の出ない仕事の担い手ではあっても、工場で生産的な労働を行う主体とはみなされていなかったといえると思います。
ついでに言えば、子どもが未熟で未発達な存在であり、まだ生産的身体とはいえないという考え方、そうした存在としての子どもという範疇もじつは近代ととも生まれました。つまり今いったような生産的な身体という範疇に子どもというのは入らないという形で子どもと大人、つまり成人を区別するのも近代の産物だということです。このあたりはフィリップ・アリエスというフランスの社会学者が『〈子供〉の誕生』という本の中で書いています。
こう考えていくと、生産的身体を通してしか、より正確には生産的身体という基準を通してしか人間という概念が成り立たない社会、こういういい方は極端に聞こえるかもしませんが、そうした人間の定義が当たり前である社会が大体19世紀から20世紀にかけて成立したと考えてよいと思います。さっき仲正さんがちょっと触れましたが、この問題をもっとも突っ込んだかたちで検討しているのがフランスのミシェル・フーコーという哲学者だったわけですね。彼は、近代以前の国家権力が死をもたらす権力として、一人一人の身体を死の恐怖によって暴力的に支配していたといっています。その究極的な現われが死刑です。権力は、非常に残酷なやり方で執行される死刑によって象徴される死の権力でもって支配=統治を行っていた。ところが近代に入ると、権力は生ける身体、生かす身体を通して、つまり一人一人の身体を生かしていくことによって支配=統治を行うようになります。それは、死によって身体を毀損するのではなく、身体を出来るだけ創造的かつ生産的に働かせることによって、つまり生産的身体によるより多くの価値、富の産出を通して、社会の支配=統治を行おうとすることを意味します。裏返していえば、これが近代社会の中心的なあり方としての産業社会の意味であり機能だということになります。その結果権力の作用の最大の要素は生産的身体の育成になります。生産的身体になるよう個々の身体に働きかけることが権力の最大の支配=統治手段になるのです。これをフーコーは規律=訓練権力と呼んでいます。ここで出てくるのが優生学というふうな考え方であり、もう一つこれとペアをなす衛生学です。都市環境をより清潔にし、病気を減らし、死亡率を下げることはそのまま生産的身体の増大につながります。
それからもう一つ、フーコーが注目したのは生産的身体の数を表すものとしての人口です。この人口のコントロールが国家権力の非常に重要な統治手段になります。そのためには出産や子育てというふうな私的領域にまで国家の触手が及んでいきます。だからこそ出生率というようなものが問題にされるのです。もちろんそこにより優秀な生産的身体の精製の手段として優生学も関わってきます。この頃ようやく解明され始めた遺伝現象もそこに結びつけられていきます。ダーウィンの進化論から出てきた適者生存、自然淘汰の考え方がそこへ関連づけられます。こういう近代社会に特有な状況や発想が繰り返し繰り返し我々の生活や意識の中にインプリントされていくとき、さっき仲正さんがいった問題ともつながるけれども、我々は大なり小なり程度の差はあってもある種の優生思想というものに染まらざるを得なくなっていきます。もちろん、ある時期から徐々にそうしたことに対する見直しが働いてきて、たとえばらい予防法の廃止につながったハンセン病訴訟や断種法といってよい優生保護法の見直しと被害者救済の問題、さらには性的マイノリティの権利を確立しようとするLGBTの問題などがそうした流れを示しています。
しかし根源的なところに立ち帰って考えてみるならば、つまり近代国家や近代社会の歴史の根底に流れているものをあらためて捉え返してみるならば、我々の中にある内なる優生思想というべきものが依然として根強く存在し続けているのは明らかです。なぜならそれなしには生産的身体、あるいは生産的身体というものをベースにした形で成り立つ我々の社会のサブジェクト、主体が、さらにはそれが人間であるという人間観も成り立たなくなるからです。そうだとすればこの優生思想の克服は大変難しいといわざるをえない。さっきの誰もがホモ・サケルになりうるということを申し上げましたけれども、それとちょうどペアな形で誰しも自分の内側に何らかの形で優生思想を抱えているということもまた踏まえていかねばならないのじゃないかと思います。そういう意味では植松は決して我々の他者ではないと、少し極端ないい方ですけれどもそういうふうに思います。
仲正:余裕がある場合は、上のほうに対する差別っていうかな、あれは優れた人だと、たとえばオリンピックの選手だとか、ノーベル賞を取る学者だとか、そういう人を特別扱いすることに対して割と寛容でしょう。オリンピックの選手すごいとか、プロ野球の選手すごいからっていって、その反動でスポーツ音痴な子をいじめるって普通いかないですよね。でも、政治家のような権力者に対しては、お前は政治家やってんだから、日本経済をどうにかしろ、とついつい言いたくなる。政治家は庶民の代表だと言いながら、庶民にはどうしていいか分からないような問題の解決を求める、そういう矛盾した欲求を持っている。官僚とかに対しても、特殊な能力を要求しがちですね。政治家や官僚は、上というよりはけ口のような気がします。
で、上ではなく下に向かっていくとき、ものすごい不寛容が起こってくる。植松に共感するようなことを言っちゃいかんのかもしれないけれど、私は基本的に心が狭いので、自分より能力ありそうな人を仰ぎ見たくないです。特に同分野じゃあまり仰ぎ見たくないです。で、スポーツ選手とかだったら、自分と接点がないので、その人の能力に嫉妬のようなものはほぼ感じませんが、同業者に近い人で、能力が高そうな人ってあんまり見たくない、直視したくないんです。自分が惨めになるから。下の方が目がいきやすい。で、上を仰ぎ見て、いいなあと、羨ましがれるぐらいの余裕があるうちはいいんだけど、余裕がなくなると、上を見るのがつらくなる。それで、下を見だすと大変なことになる。私は今のところそんなに下のほうを見てないんだけれど、下を見ようとすると、どうしても差別感情を抱いてしまうと思います。あいつらよりは自分のほうがはるかにましだ、能力が高いだろうなっていうふうな意識にすぐにいっちゃうんですね、だんだんせせこましくね。
普通は自分の身近にいて、自分より少し下そうな人にそういう目を向けるのであって、障害者とか、いわゆる社会的弱者という人のところまで、攻撃的な眼差しを向けなくて済むけれど、本人の社会的な立場が弱くて不安定だったら、一番弱そうな人を攻撃してしまう。適当なところで、下には下がいるっていって自己満足するっていうふうにならない。本当に辛いと、下のほうにぐーっと視線が行ってしまう。上からの優生思想っていうか、ゴルトンだとか、なんか産児制限運動とかをやってた人っていうのはいわゆるエリートで、そういう人たちっていうのは、気持ちの上では、上から目線で、下層の人をどうにかしてあげたいと思ってやっていたわけでしょ。余裕がない人間が、下に対して憎悪の目線を向けると、それとは全然違う態度になる。ほんとに共感してその人たちを助けるか、こいつらと自分は違うんだって強調するために、全否定するかとに反応が二分される。ナチスってそもそもなんなのかって考えると、コンプレックスの塊。ヒトラーからしてそうだし。ドイツ人が、19世紀になって自分たちが野蛮人じゃなくて、ヨーロッパの中で実は最も優れているんじゃないかと思い始めたときに、第一次大戦でいきなりどん底に。自分たちが馬鹿にしていたチェコ人とかハンガリー人よりも下になっちゃって、プライドがずたずたになったとき、もっと下を見ようとし始めた。まさにそこに、コンプレックスの塊みたいなヒトラーの思想というのがウケてしまった。そんなに強制的じゃなくて単なる上から目線レベルで済んでた優生思想が、ぎりぎりの状態にいる人たちのルサンチマンと結び付いた時、ものすごく狂暴なものになってしまった。