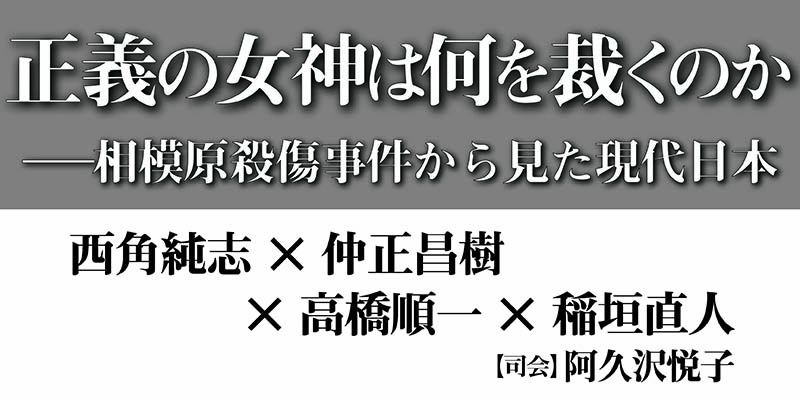正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本 第1回
2021年10月24日に開催された『元職員による徹底検証 相模原障害者殺傷事件―裁判の記録・被告との対話・関係者の証言』刊行記念トークイベント「正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本」(共催:明石書店・読書人、会場:神保町・読書人隣り)。西角純志氏(著者。専修大学講師)、仲正昌樹氏(金沢大学教授)、高橋順一氏(早稲田大学名誉教授)、稲垣直人氏(朝日新聞)が登壇し、阿久沢悦子氏(朝日新聞)の司会進行により充実した議論が交わされました。本記事は、その内容を採録したものです。
【毎月25日頃更新・全9回連載 ダイジェスト動画をYoutube明石書店チャンネルにて公開中⇒https://youtu.be/ZUmZHFgWico】
本日は西角純志さんがお書きになった『元職員による徹底検証 相模原障害者殺傷事件―裁判の記録・被告との対話・関係者の証言』という本について合評会をこうした形で持たせていただくことになりました。本日司会を務めます、朝日新聞の地域報道部の記者で阿久沢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この度の合評会は、会場とオンラインと2パターンで同時にやっております。このオンラインのほうの会場では、録画をさせていただいておりますので、参加の方々は予めご了承ください。また、登壇されている先生方への質問などにつきましては、チャットでお寄せいただくと、あとで議論の助けになりますのでどうぞよろしくお願いいたします。この会場にいらっしゃる方からは会場で挙手でという形でいただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。いくつかの論点について先生方に討議をしていただいたあと質疑応答という全体の流れになります。それでは、これから合評会のほうを始めさせていただきたいと思います。
相模原障害者殺傷事件について予め少しアナウンスをさせてください。皆さんもうご存じとは思うのですけれども、相模原障害者施設殺傷事件は2016年の7月26日未明に神奈川県相模原市緑区にあった神奈川県立知的障害者福祉施設「津久井やまゆり園」において発生した大量殺人事件です。裁判の被告となったのは元施設職員の植松聖氏で、事件当時まだ26歳でした。彼が施設に侵入して、所持していた刃物で入所者19人を刺殺し、入所者と職員併せて26人に重軽傷を負わせた事件です。殺人などの罪で逮捕起訴された植松氏は、2020年3月、横浜地方裁判所における裁判員裁判で死刑判決を言い渡され、自ら控訴を取り下げ、死刑が確定いたしました。今はもう植松氏に外部から接触することがなかなか難しいというような状況です。西角先生のこのご本なんですけれども、接見から裁判における植松被告とのやりとり、それから、西角先生が以前やまゆり園にお勤めになっていたこともあり、施設の内部構造であるとか、職員の勤務実態なども踏まえたうえで事件について多角的に検証したものになっております。
先に西角先生とお話をしていたときに、スピルバーグの『シンドラーのリスト』に批判的な視点で作られた、クロード・ランズマンの『ショアー』というユダヤ人の虐殺・ホロコーストについての、ユダヤ人側の証言を集めた非常に長い映画があるんですけれども、それを目指したというふうに仰っていました。私はそのランズマンがそのあとに撮った『不正義の果て』という映画、それは同じユダヤ人の中でも模範的ゲットーを支配していた古老のユダヤ人に焦点を絞ったインタビュー映画なのですが、それにも非常に近いものを感じました。職員の方のインタビューなどもふんだんに盛り込まれていることによって、ともすれば加害者植松のことを語りがちになる私たちに、いろいろな被害者側、それから職員側の示唆を与えてくださる非常に素晴らしい本だなと思いました。
本日の登壇者をご紹介します。まず、西角純志さんです。1965年、山口県のご出身で、中央大を卒業して明治大学で博士課程を修められました。博士論文のタイトルは『移動する理論―ルカーチの思想』です。政治学の博士をお持ちです。今は専修大の講師で、津久井やまゆり園には2001年から2005年に勤務をされていらっしゃいました。その体験を踏まえてこの本を書かれたということです。
それから、仲正昌樹さん。1963年、広島県のご出身で、東大で博士課程を修められました。98年に金沢大学の法学部の助教授になり、2008年からは金沢大法学類教授をお務めになります。雑誌『情況』の編集にも長く携わっておられます。主な著書に、『“法”と“法外なもの”―ベンヤミン、アーレント、デリダをつなぐポスト・モダンの正義論へ』、『カール・シュミット入門講義』、『〈ジャック・デリダ〉入門講義』などがあります。
高橋順一さんは、1950年、宮城県のご出身です。80年に埼玉大の修士課程を修められ、87年に早稲田大学の教育学部専任講師、その後助教授、教授となられました。吉本隆明や廣松渉への関心も深く、『ヴァルター・ベンヤミン解読―希望なき時代の希望の根源』『吉本隆明と共同幻想』などのご著書があります。
一番私に近い所に座っていらっしゃるのが稲垣直人さん。朝日新聞のオピニオン面の記者です。1969年生まれ、94年朝日新聞入社、政治部などを経て2019年から朝日新聞のオピニオン編集部の記者として、声欄の隣にある「耕論」「対論」などでご健筆をふるっていらっしゃいます。政治社会思想を中心にアカデミズム分野の研究者の方々に取材インタビューをする機会が多く、今回のテーマに関心を持っていた、ということです。以上、登壇者の方々よろしくお願いいたします。
私は朝日新聞の地域報道部の記者で阿久沢と申します。どうぞよろしくお願いします。相模原事件の直接の取材経験はないんですが、事件発生時は阪神支局に勤務し、阪神間がちょうど障害者の自立生活運動のメッカであるところから、障害者施設や障害者の方たちのこの事件の受け止めなどを記事にしてきました。
それでは、シンポジウムタイトルの「正義の女神は何を裁くのか」ということについて西角先生にこのシンポジウムでどういうことを皆さんで深めていきたいかということも踏まえてお話をまずいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

1.正義の女神とは何か
西角:今回のシンポジウムは「正義の女神は何を裁くのか ―相模原殺傷事件から見た現代日本」というタイトルです。「正義の女神」は、大学だとか裁判所とかにもいろいろあるんですけど、元々はギリシア神話に出てくる女神で、天の神ウラノスと、大地の女神ガイアとの間に産まれた娘です。テミス(Themis)というのは古代ギリシア語で「不変なる掟」という意味がありまして、正義や秩序を司る法の女神というふうに称されるようになりました。ギリシア神話の「テミス」は、ローマ神話では「ユスティティア」(Justitia)というふうになって、これがジャスティス、つまり正義の語源になります。このときから天秤と剣が「正義の女神」の象徴になります。「正義の女神」は右手に剣、左手には天秤を持っています。剣は正邪を断じる印です。彼女が左手に持つ天秤は正邪を測る正義を、剣は力を象徴し、剣なき天秤は無力、天秤なき剣は暴力にすぎないと。法はそれを執行する力と両輪の関係にあることを表しております。「正義の女神」というのはカフカの『訴訟』にも、アトリエの画家の場面にも登場するわけなんですけれども、目隠しをしたものと、目隠しをしてないもの、この二つのものがあるわけなんですね。剣や天秤というのが古くからあるのに対して、目隠しというのは16世紀になって初めて登場するということなんですね。目隠しをした女神像が最初に描かれたのはドイツの法学者のゼバスチャン・ブラントの『阿呆船』(1494年)なのですが、その風刺作品の挿絵と言われております。当時の国王に任命された職業裁判官が登場し、不正な裁判をしていたと。そして、戯画の作者は「正義の女神が目隠しをされて法廷をウロウロしている」と皮肉って目隠しをした「正義の女神」を描くようになったと言われております。つまり、当時の教会や聖職者の腐敗の意味が込められていたということなんですね。

ゼバスティアン・ブラント『阿呆船』第71章「喧嘩をしては訴訟を起こすこと」挿絵
【出典】尾崎盛景訳『阿呆船』(下)現代思潮社、1968年、55頁
その後この由来というのが次第に忘れられていって、「外見で人を裁いてはいけない」というふうな意味に変わってきました。ちなみに日本では穂積陳重の『法窓夜話』のなかに江戸時代に京都所司代を務めた裁判官、板倉重宗が、外見に惑わされないために灯り障子で遮られた場所から訴人の話を聞いたという逸話があります。「正義の女神」は本来目隠しをしていなかったのですが、次第に目隠しをすることが多くなったと言われております。僕の著書の表紙のドイツ・フランクフルトのレーマー広場にある「正義の女神」は、目隠しをしてない女神なのですが、「正義の女神」は目隠しをせず、裁判の行方というものをずっと見つめているというふうに僕は見ておりました。これは法廷の中ではなくて、法廷の外部もそうなんですね。そして、「正義の女神」は何を裁くのだろうかと、いうことですよね。それは単なる障害者の問題だけであろうか。いや、日本社会、現代日本の問題、社会そのものを裁いているんではないかというふうに感じまして今回のタイトルを「相模原殺傷事件から見た現代日本」ということにしました。
阿久沢:ありがとうございました。それでは本書の読解、合評会のほうに入っていきたいと思います。この本の中で、法と法外なもの、フランツ・カフカの『掟の門』というのが引用されています。『掟の門』については西角先生が植松に差し入れをしてですね、ちょっと感想文を書くようにというようなことを接見のときに言ったということで、植松もそれを読んでの感想文をこの本書の中にも収録されているんですけれども。本書では、事件の被害者が事件の起きた発生の発表から裁判にいたるまで終始匿名で扱われていることについて、法の外における法権利を停止、宙づりにしたと指摘しています。また、植松への死刑判決については、国家による、法による生存の否定=暴力であるとも提起しています。法と法外なものの関係について西角先生にまず、なぜカフカの『掟の門』を植松に読んでもらいたいと思ったのか。その反応をどう考えたかということ。あるいは、法と法外なものの関係について、この本書の中でも図示したものがございますので、まずその点について整理をしていただけたらと思います。

ドイツ・フランクフルトのレーマー広場にある正義の女神像

目隠しをした正義の女神
西角:カフカの『掟の門』という話は皆さんご存じだと思いますが、『訴訟』という作品ですよね。それの最終章の大聖堂の章に挿入された物語なんです。田舎から出てきた男が門の中に入れてくれと頼むのですけど、何年経っても入れてくれない。そのために貢物などもしますがそれでも入れてくれない。そのうちに年をとって死んでしまうと、こういう物語なんですね。この物語についてはさまざまな解釈があります。カフカの解釈を、ベンヤミン、デリダ、それからアガンベンですね、さまざまな解釈をしております。僕もこの『掟の門』については、かなり前からすごく関心を持っていたんですけど、これが意味するものがどういうことなのかと考えていました。報道を見てみると、「私が殺したのは人間ではない」というふうなことを言ってるんですね。「人間ではない」ということであれば、何なのかというと、植松との面会ではですね、「心失者」(しんしつしゃ)というふうに言ってました。この「心失者」というのは何かっていうと心神喪失者の造語だというふうなことですね。これを現代思想の文脈で置き換えればホモ・サケルのことであろうということなんですね。ホモ・サケルというのは何かというと、古代のローマに古法に登場する呼称で、ラテン語で「聖なる人間」というのを意味します。古代ローマにおけるホモ・サケルというのは、親に危害を加えたり、境界石を掘り起こしたり、客人に不正を働いたりといった、悪質な犯罪者のことを指しておりました。つまり、ホモ・サケルというのは世俗の法秩序の外にあるために、悪質な犯罪を犯して殺されても、殺した人物については刑事上の罪を犯したことにならず、宗教的な犠牲にも供されない存在であると。つまり、ホモ・サケルという形象は、人間の共同体から排除されているばかりではなくて、神聖の世界からも排除されてるということなんですね。これを概略図を使って簡単に説明すると次のようになります。

田舎から来た人が法の中に入ろうとします。法の中に入ろうといても門番が待ち構えており、何年経っても入れてくれない。つまり、排除と包摂というふうな形になっています。パネルの右側の田舎の男ですね。本書では、掟というのは法で、門番が暴力、田舎男は正義という形で議論を展開しました。この排除的包摂が、ホモ・サケルの位置づけになります。法の外に追いやって、法の及ばない境域を設けて、排除したものをそこに合法的に置く。これが「掟の門」の構造であり、匿名発表なんかそうですね。匿名発表というのは、事件当時神奈川県県警は、遺族の意向だとか障害者だからということで匿名でしか公開しませんでした。つまり、法の外に追いやって、法の及ばない境域を設けて排除したものをそこに合法的に置くという図式なんですね。この不分明地帯がホモ・サケルの境域です。例えば、カフカでいえば『変身』という作品がそうですね。朝起きてきたら身の毛のよだつような害虫に変身していたという物語ですが、主人公はグレゴール・ザムザに見えるんですけど実はそうじゃなくて、影の主人公というのは実は父親なんです。父親の投げたリンゴが仇になってグレゴール・ザムザは死んでいきます。つまり、父親というのは莫大な権力というものを持っていて法外に追いやってるんですね。コロナ禍での家庭内隔離だとか、ひきこもりだとか、DVとか虐待被害者とか、そういうのがこういう図式で捉えることができます。つまり、主人公はここにいるんですけど、家族によって排除されたり隔離されたりそういうふうな図式になっている。この描写がホモ・サケルです。植松被告自身は、「私が殺したのは人間じゃない。心失者だ」と言ったので、これが頭に浮かんだんですね。じゃあ、どう考えるのかというふうなことで感想文を書いてもらったということなんですね。
阿久沢:その感想文はどんなものでしたか。
西角:感想文の前に、まず初回の面会で、法とは何か、正義とは何か、それから、暴力とは何かということを語ってもらったんですね。『掟の門』のレポートをその時依頼したのですが、なかなか筆が進まないというふうに本人がぼやいておりました。僕自身、学生にレポートとかを書いてもらったことがあるんですけど、なかなか優れたレポートを書いてくれたんですけど、ところが植松の『掟の門』の感想というのは、極めて出来が悪いというか、たとえ話がよくないというか、あんまりよろしくないような印象なんですね。そして、何度か、私の方で手を入れて、法・正義・暴力を柱にして推敲してもらいました。手紙のやりとりの過程で『掟の門』の絵も描いてもらったというふうなことなんですね。だから、植松自身も、このホモ・サケルのことも知ってるだろうし、カフカばかりでなく、アガンベンなども知っています。植松は、レポートの中で、マインドブロックという言葉を使ってますが、なかなか前に進もうにも進めないというふうな状況というか、入ろうにも入れない、掟というものが邪魔をしていくというふうなことも述べています。面白いのはこの「正義の女神」というところですね、画家のアトリエの場面で「正義の女神」の話が出てきます。「正義の女神がじっとしていなくちゃ、でないと天秤が揺れて公正な裁きができない」と。僕が植松に差し入れたのは白水社版の池内紀訳の『審判』で、カフカの肖像も載っています。『掟の門』は丘沢静也訳の光文社版のものです。
『掟の門』は、短いのでコピーをして差し入れました。『審判』は、池内さんの訳の方が、読みやすいと思ったので、こちらの方を渡しました。池内訳では、「正義の女神」は、「正義の神」というふうになってますけど。ただ植松は、的確に捉えています。「正義の女神」は、目隠しをしたものと目隠をしてないものがあるのですが、「正義の女神がじっとしていなくちゃ、でないと天秤が揺れて公正な裁きができない」という件を引用して植松被告がうまくまとめたかなと思います。カフカの肖像画や、カフカやカントの格言を最初に送ったのが月刊『創』(2018年5-6月号、86頁)です。それから、『開けられたパンドラの箱』(創出版、2018年、77頁)で書籍化されました。もちろん僕のところにも、カフカの肖像画なども送られてきたわけなんですけど。僕が記事にしないだけで、植松の手紙ばかりではなく植松の描いた絵や作文などかなりの量を持ってますので、死刑が執行された後、表現の不自由展に出してもいいかとも思っています。
阿久沢:今のその、法の外に置き、法権利を停止した状態にある、ホモ・サケルというような存在が、現代日本でいろいろなところで見られるという指摘があります。そのことについて稲垣さん、どう思われますか。
稲垣:ホモ・サケルのような存在は、最近ニュースになっているいくつかの出来事からも、いくつか例があるように思います。まず思い浮かぶのは、たとえばスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんが名古屋市の入管施設で収容中に亡くなった問題、それから財務省の公文書が改ざんされたり、黒塗りになって出て来なかったりという問題。法の外に追いやって排除してしまうというホモ・サケル的なるものは、決して古代ローマやカフカの時代の話ではなく、現代社会にも相似形として起こっている問題なのではないでしょうか。
阿久沢:私も同じような感想を持っていまして。たとえば、法律と法律の外にあるもの。法律によって追いやられるという意味では、旧優生保護法下の断種手術であるとか、ハンセン病の無らい県運動などもそうなのではないかと。私は2021年3月まで、静岡総局に勤めていたんですけれども、静岡県は優生保護法の断種手術や無らい県運動が、かなり盛んでした。なぜこんなに気候温暖で大人しい県民性と言われている人たちが、せっせとそういうことをしたのでしょうかということを知事会見のときに聞いてみたところ、「非常にいい人たちだから、法律で規定されてたら、せっせとやるべきものだと思って取り組む。いい人だからやったんだよ」という話になり、「ああ、そうかもしれないな」などと思いました。自分がいい人だからこそ進んで手を貸すということがこの法律の外に追いやるという運動にはついてまわってしまうんじゃないかなということを私なんかは思っています。それでは、仲正先生、高橋先生の順に今の『掟の門』を参照するのがいいのかどうか、それこそ、事前の打ち合わせのときに仲正先生が、「植松は存在がそういうふうに見えてしまうけど、あまり現代思想的な人でもないよね」みたいな話もちょっとされていたので、『掟の門』を参照しながら、あるいは参照するのが不適切だと思われるところがあればその点についても教えてください。