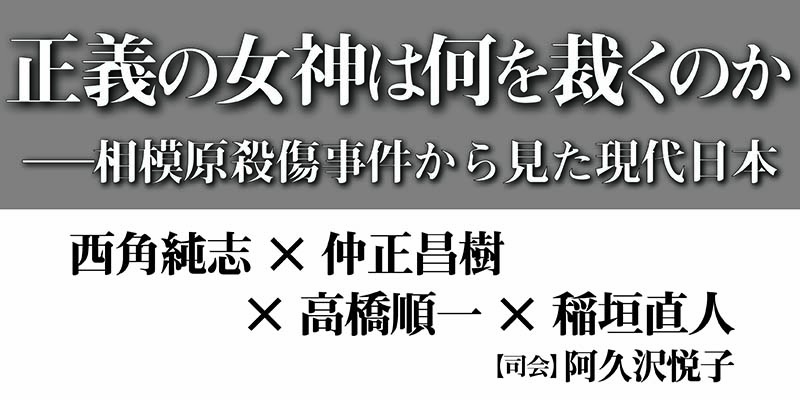正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本 第2回
2021年10月24日に開催された『元職員による徹底検証 相模原障害者殺傷事件―裁判の記録・被告との対話・関係者の証言』刊行記念トークイベント「正義の女神は何を裁くのか―相模原殺傷事件から見た現代日本」(共催:明石書店・読書人、会場:神保町・読書人隣り)。西角純志氏(著者。専修大学講師)、仲正昌樹氏(金沢大学教授)、高橋順一氏(早稲田大学名誉教授)、稲垣直人氏(朝日新聞)が登壇し、阿久沢悦子氏(朝日新聞)の司会進行により充実した議論が交わされました。本記事は、その内容を採録したものです。
【毎月25日頃更新・全9回連載 ダイジェスト動画をYoutube明石書店チャンネルにて公開中⇒https://youtu.be/ZUmZHFgWico】
2.法とは何か
仲正:先ほど西角さんの言われたことをずっとこの教科書的な解説するような感じになると思うんですけど、「掟の【前】」と植松とどこに接点が一番ありそうかっていうと、植松がこの障害者の扱いに関して、まあちょっとかなり無茶苦茶な内容なんですけれど、官邸だとかそれから衆院議長とかに働きかけようとしてる場面というのはあるわけですね。で、まあちょっとこの内容は放っといて、そうですね、一般の人間というのは普通は法ってあまり意識しないで生きてられるんですけれど、何かのきっかけで、「それは法律じゃ駄目なんですよ」と、「あんたそういうことできませんよ」ということに一度接するとね、「法」を意識して、その法の世界って、どんな世界で、なんで自分はこれを禁じられてるのかって関心持っちゃうことってあると思うんです。コンプレックスみたいのを持ってる人ほどそういうのになりやすい。お巡りさんに「それやっちゃ駄目ですよ」って言われたときに、反発しますよ。「なんで駄目なんだ」と。相手が弁護士だったら、弁護士はたぶん法律で説明します。警官は「お前がやってるほうが不当だ」とできるんです。法っていうものには、そういう側面ってあると思う。ちなみに、私は、法学部というところに勤めることになったんですけれど、務め始めたときに、語学の先生とかも多少いましたが、今は法学部出身でないのは私だけで、周りはみんな法律の専門家なんですよね。法律の専門家は、そういうふうに、「いや、法律はこうなんですよ」って言うんです。言われるとね、すごいむかつきます。なんていうかね、どんな人間でもプロから、「それできませんよ」って言われるとむかつくんですけれど、たぶん一般人が一番むかつく場面は、法律家に、法律の名においてそれはできませんよと、これは絶対です、と言われる場面です。これはたとえば科学だとか経済とかだったら、私はそういう世界に生きてませんよって言って回避できそうですけど、法律だけは、「それはできませんよ」って言われたら回避できないですよね。強制されるから。で、それをなぜか理屈ですり抜けちゃう人間っている、と。法律家とか法学者になったら、そんなのたいしたことじゃないって思い始めるかもしれないけど、そうじゃない人間というのは、なんだかその門の前で拒絶されたような気になってしまう。ある程度エリートな生き方をしてる人だったらそこまで拒絶を感じたことはないかもしれないけれど、植松のような生き方をしてきた人だったら、それを強く感じてしまったのかもしれないと。で、カフカの『掟の門』の基本的な構造というのはそういうことだと思うんです。つまり、その田舎の出てきた人っていうのは何かのきっかけで、「これは許せん」と感じた。これはこういうふうになってるはずがないと思ったんだけれど、なんか拒絶されてしまった、と。その感覚で、法というものに固執することになったのではないかと思います。
事前にお配りしたレジュメに沿って、なるべく簡潔にお話ししたいと思います。カフカには、タイトルからして明らかに法律に関係していると分かるものが結構あります。『流刑地にて』、『新しい弁護士』、『判決』、『代理人』、『【法】の問題』、それから、『審判』と並んで有名な『城』があります。『城』は法というよりは権力ですけれど、カフカは一般的には権力とか法の複雑さを扱うのがうまい作家だとされています。それで、「法の前」、「掟の前」の話なんですけれど、この門番とはなんなのかと。そうですね、西角さんの本の中では、法外なものを、お前は向こうに行けって排除する力を持っている存在だというふうに捉えられるんですけれど、ただ、彼は、俺の向こうにはもっと強い門番がいる、俺はそいつの顔さえ見たことがないと、と言っている。つまり、それは彼の従属性を表していると思います。実はこれが法の嫌なところです。なんていうかな、法を代弁する者、まあ特に警官なんかはそうですけれど、自分が言ってんじゃないと、もっとすごいのが後ろにいるんだ、とほのめかす。そう言われてしまうと、人間の反応って大体両極、負け犬根性になって、ワー、もう自分は駄目ってなるか、いや、絶対その中に入っていきたいってなるか、どっちかに分かれるんですね。それが「掟の門」だと思うんです。それがあると思い込んで、その田舎の人はもう一生を門の前に立ち尽くして、それで人生を駄目にしてしまう。最後は弱って死んでいくっていうんですけど、これはなんかのパロディかもしれないけど、現実にそうなってしまう人いますね。まあ、こういうふうに言うとほんとに失礼な感じになるかもしれないですけれど、他人から見ると、どうでもいいようなことでも訴訟絡みの問題に関わり、のめり込んでいって、これ解決できないうちは自分はもう生きていても…、死んでも死にきれないみたいな感じになってしまう方っていますよね。第三者的にも、大義のためにやってよくやったというふうに見える人もいれば、ちょっとそれあんたの個人的な遺恨でやってるんじゃない、というふうに見る人もいるし。法の世界というのはそういうところがあると思うんですね。そこで、「掟の門」ていうのは、西角さんの本に出ている植松の描いた絵が象徴的なんですけど、なんか向こうがあるのかないのかわかんないような。開かれてるようにも見えるし、タイルみたいなので閉じられてるように見えるし、どっちにもとれる。これすごく面白いなと思いました。

『掟の門』(植松聖:画)
こういうイメージに、引き込まれちゃうんですね。なんとか…、突破できるんじゃないか、いや、自分には絶対無理かも。これよく文学の解釈で出てくる話なんですけれど、なんか閉ざしたものがあると、その扉の向こうになんか大事なものがあるような気がしてしまう。で、人間そこを探ってしまう。精神分析のエディプスコンプレックスの批判をするときによく出てくる話なんですけれど、あれは要するに禁止される自分はそれをほしがっていると錯覚するということです、お前は男根がほしいんだろと、だから禁止するって言われたら、なんかほしい気になるわけ。恋愛の話なんかでよく言われる、お前はこの人と付き合っちゃ駄目だって言われると、燃え上がるってよくある話。
阿久沢:なんかやんごとなき人も最近ありましたね。
仲正:ああ、そうそうそういう話なんですよね、はい。それにかかっちゃう。その構造があるんではないかと思います。法というのは実はそういう罠をたくさん仕掛けてて、実は植松は、「掟の前」の田舎から来た人を植松だと考えると、それに引っかかった、もう見事に引っかかってしまった人というふうに見える。法の罠ですよね。それでこの『審判』の全体の枠の中で考えてみたいんですが、これもちょっと、長くなりますけど、かなり簡略化して言うと、ヨーゼフ・Kという人がいる、銀行の勤め人だと。で、普通だと法とは仲良く生きてるはずの銀行員なのに、急にお前を逮捕するという人間が、彼の下宿部屋の中にいきなり入り込んでくると。しかし、逮捕するって言ってる割には、急に拘束するわけじゃなくて、なんとなくなんか見張ってて、いろいろ不快なことをやって、彼のプライバシーをどんどん詮索していく。それで彼は気になって、これをどうにかしたいと思う。そう思ってたんだけど、訴訟のプロセスを止める具体的な行動をとってなかったら、おじさんという人がきて、いや、俺の親友の弁護士を紹介してやろうと言って、弁護士を紹介してくれる。しかしその弁護士も、後で登場する法廷画家も、いや、実は法というのは非常に複雑で、一体お前を起訴して、裁くというプロセスがどこで始まったのか本当のところわからない、と。現実だったら、たぶん誰かがこいつを捕まえろって言わなきゃ、何も動かないんですけれど。ただ、そういう、こいつ怪しいから捕まえろと、こいつ監視しろっていう判断がどこでどの瞬間できたかというと、なかなか特定できないですよね。担当者は、それは、こういうような方針があったから、従っただけだと言う。じゃあその方針は誰が決めたんだって聞くと、いや、実は前にこういう事件があったとき、こういう風な判断が〇〇のところであって、そしてその判断は…とずっと辿っていったら、本当に誰が決めたのかわかんないような構造が見えてくる。そういうのがずっと続いていく。そういう風に考えると、ヨーゼフ・Kは訴訟=審判(der Process)を回避するつもりで、自分でなんかはまりに行っちゃってる。放っといたら、なんか不快だけどまだ生きていられたのが、なんかどんどん、もがいて、どんどん、法の罠に引っかかっているのではないかと思います。つまり、自分で法の力を、法の力に抵抗しているというつもりでつくりあげていく。法をつくりだす力と、その法がその自己再生産して維持されていく力が、循環構造みたいになってるということをベンヤミンは言っているんですが、それを自分でやっちゃってると。
最後に、ホモ・サケルの話とどういうふうにつながってくのかだけちょっとお話ししておきたいと思うんですが。ホモ・サケルというのは、「サケル」って「聖なる」っていう意味ですよね。で、聖なるものっていうのは、触れてはならないものなんですね。その共同体の中では崇められ、儀礼の中心になっている。ただよく文化人類学の話で出てくるように、聖なるものっていうのは同時に穢れでもある。聖なるものに普通の人間が触っちゃうと、穢れになってしまう。聖なるものも、穢れも、共同体の法の外にある存在です。聖なるものと共同体の境界線を守らないといけない、まあちょっとこれは文化人類学の話なのでそこはちょっと端折りますけれど。ただこれは、植松の話との関連で面白いのは、この境界線の問題ですよね。法っていうのはなんらかの形で、これは法外な存在である、と指定する。だからさっきの西角さんの話だと、自分で言語で語ることができない人だとか、心神喪失者だとか、それから、精神障害等で責任能力はないというふうに認定されている人とか、普通ではないので、法外だと指定されます。じゃあどういう人が普通なのかって改めて考えると、わからないわけですね。我々普段は法と関係なく生きてるから。法が機能するには、そういう法外な存在が必要であり、法は何が法外か決める。ホモ・サケルが必要です。植松は、心神喪失者をホモ・サケルと規定して、法/法外の境界線を引こうとしているんだけど、彼自身がホモ・サケルに自分でなってしまってるような感じがあります。じゃあ精神障害者の人とホモ・サケルがどう関係してるかっていうと、線引きのために必要です。ある意味日常的な実体験として多くの人が経験していることではないか思います。
これもまた自分の話なんですけど。小学校の頃、ちょっとだけ足が悪かったのと、それから、コミュニケーションベタでちょっととんちんかんな受け答えをしていたというのがあって、なんとなくちょっと問題児扱いされてて、問題児といっても、不良みたいのじゃなくて、なんかちょっとこう、話についていけない子だったんです。たとえば運動会のときとかに変な走り方をして、みんなに笑われて、ちょっと扱いに困った子だみたいな感じだったんです。今の学校のことはあんまりわかんないんですけど。50何年ぐらい前の学校だったらね、学級に1人ぐらい、養護学校に行ってもらうべきか、それとも普通のクラスに行くべきか、ぎりぎりみたいな子っていうのがいたんですよね。で、そういう子をね、やっぱりね、小学生って、差別するっていうかな、まあ差別というよりいじめですよね。で、これ人間の心理でそういうのってあると思うんですけれど、なんていうかな、いい子で、優秀な子で、先生からも親からも好かれてる子は、自分が標準かどうか気にして、そこに留まろうとかあんまり気にしないと思うんですけれど、やっぱり、ちょっとこう、ちょっとじゃないな、コンプレックスがある子は気になっちゃうんですね。そういう自分がまともか気になっている子は、自分よりも、もっと外れてて、明らかに差別されている子がいると気になる。ときどきね、うちの親が参観日に、先生から養護学級に行かせるべきかどうか迷ってる子がいると聞かされてくる。自分ではなくて、たぶんそっちの子だと思うんですけど、気になる。なんか書き取りが少々できるから普通のクラスにおいてるんだ、とかいう話を聞くと、ひょっとしてちょっと自分も入っているんじゃないとかね、いつも多少の不安を持っていました。そうするとね、それではっきりいじめの対象になっている、今から考えて見ると、精神障害者だったかもしれない子になんか関心を持っちゃうんですよね。で、そのときの自分の態度を見たら、仲良くしてたようにも見えるし、普通にいじめてる子となんか同調してるような態度をとってたときもある。人間ってね、自分がやっぱり弱いと思うと、自分より弱いところを気にして、そことのなんか差を出すことによって、ぎりぎりこっち側にいようとするようなそういう力が働くと思うんですね。そのときに仲良くするかいじめるのかっていうのが実は紙一重みたいな気がするんです。今でもときどき、まあ自分が精神障害者かもしれないと本格的に不安になることはありませんが、なんていうかな、多少疎外感を感じるとね、そういうような感覚を思い出すときがあるんですけれど、だから植松の話をこの西角さんの本の観点で見たときに、この男そういう感覚を持って、障害者の人たちに関心を持ちすぎちゃったんじゃないかと感じました。
だから、ホモ・サケルというと、現代思想の抽象的な概念みたいな感じがしますし、実際我々は抽象的に論じますけど、実は人間って自分に関する社会的な自信みたいなのをとっぱらうと、実はホモ・サケル探しを自然とやってるんじゃないかなと、というふうに思ってます。クラスの中の特別扱いされている子は、まさに穢れのように扱われるが、同時に聖なるもののようにも扱われるでしょう。いずれにしても、下手に触るとまずい存在。ちょっと長くなりましたけど。
阿久沢:今整理していただいてほんとにすっきりと見えてきましたが、ホモ・サケル、法外なものとして置かれているんですけれども、これは聖なるものでもあり穢れでもあるということになると、被害を受けた障害を持った人もまたホモ・サケルとして定義しうるし、加害をした側の植松氏もホモ・サケルとして定義しうると。聖なるものでもあり穢れでもあるというようなそういう理解、両義的な理解というのが必要なのかなと思いました。高橋先生は、ホモ・サケル、「掟の門」などについて、ベンヤミンの研究をされてこられたので、その知見などから思うことがあればお聞かせください。
3.法に触れた瞬間、何が起こるのか
高橋:「掟の門」のことですね。ちなみに私はいつも「掟の門前」と呼んでいました。そして私もこのテクストに強い関心を抱いてきました。関心を抱くきっかけになったのは、フランスの思想家ジャック・デリダがこの「掟の門前」について日本で行った講演です。それは本になっています(三浦信孝訳『カフカ論 「掟の門前」をめぐって』朝日出版社、1986年)。この本から私は非常に強いインパクトを受けました。私が一番強く感じるのは、この「掟の門」を通してカフカの文学について考えようとするとき、よくあるようにカフカの文学を社会問題や政治問題の譬喩として読むのではなく、むしろ逆に社会や政治の問題を動かしているメカニズムや動力の根源をカフカの文学を通して捉えなければならないということです。つまりこの現実、この世界の方がカフカの文学の譬喩になっており、そのようなものとして読み解かれなければならないということなのです。それを教えてくれたのがデリダでした。たぶん仲正さんも今カフカの講座をやっておられて感じるというか、気づいておられると思いますが、この現実とカフカの文学の関係を逆に捉えてしまっているがゆえにほとんどのカフカの読み方は誤りといわざるをえません。まずこのことをいっておきたい。
その上で「掟の門」というテクストの問題に入っていきたいと思います。そうすると今私がいった問題が浮かび上がってきます。デリダの「カフカ論」が指摘しているのもまさにそのことなのですが、私は、「掟の門」というテクストが掟、つまり法の世界の譬喩なんかではなく、逆にこの「掟の門」というテクストによって法のほうが包囲されていると思います。つまり法が「掟の門」という物語を譬喩というかたちで包囲してるのではなく、逆に「掟の門」という物語のほうが法を包囲しているんです。では「掟の門」という物語が法を包囲しているというのは一体どういうことなのか。デリダは、この「掟の門」というテクストにおいては、物語と掟が同時出頭しているといっています。つまり物語が出現することと法が出現することは同時であるということです。したがって、さっきいったことの繰り返しになりますが、この物語が遅れて=後になって法を解釈しているのではなく、この物語の出現と掟=法の出現は正確に同時的なのです。したがって法の出現という出来事、その出来事の出来(しゅったい)の瞬間、その瞬間と物語の同時性、これがこの物語の根源であるといってよいでしょう。そしてこの法の出現、この「掟の門」というテクストとの同時出頭において出現しつつある法とは何かという問いがここではじめて始まります。
ちょっと迂回した話をさせてください。これはカフカ短編集の原書なんですけども、私が学部の1年生だった50年近く前に買った本で、私のカフカとの出会いはこの本がきっかけになっています。この本の目次を見ていくと、もちろん「掟の門」も入っているのですが、その「掟の門」のちょっとすぐ後に「皇帝の使者」という短いテクストが入ってます。私は、「掟の門」というテクストと、この「皇帝の使者」というテストがちょうど一つの対称形をなしていると考えます。どういうことか。「掟の門」は、掟の門、つまり法の門の中に入っていこうとする田舎者の物語ですね。一方、この「皇帝の使者」では、法の真ん中にいる皇帝から指名された一人の若者が使者として法の外、法の外部へ出かけようとします。ところがこの使者はいつまで経っても皇帝の宮殿、つまり法の内部から出られないんです。「掟の門」では、さっき仲正さんがいったように、門番がいいますよね、俺なんか下っ端で上にはもっとすごいのがいるんだ、と。たぶんその偉い連中は無限にいるわけです。だから法の中心まで達することはおろか、門に入ることも出来ないんだと門番はいっているわけですね。それとちょうど対(つい)の形で、皇帝の使者として法の中心を出発した若者もまた絶対に法の外に出られないのです。法の中心から法と法の外部の境界までは無限に遠いからです。だから「掟の門」と「皇帝の死者」はちょうどペアの構造になってるということです。ではこのペアの構造を通して語られることは何なのか。
とりあえずいえることは、おそらく誰も法の中核にあるものを見ることも、知ることも出来ない、したがって法の窮極的な根拠を把握することは出来ないということです。法というのはたまねぎみたいなもので、皮をむいていくと最後には何も残らない、つまり中心は空っぽなのです。だから法の中心や根拠を誰も見ることは出来ないわけです。法はそういうものであるということをカフカは、「掟の門」と「皇帝の使者」という二つの短いテクストをペアにして重ね合わせることによって浮かび上がらせているといってよいでしょう。でも問題はそれでは終わりません。ではなぜ、そんな何の根拠も、ということは正当性もないということですが、法が現実には大きな力、大きな威力を持って我々を支配しているのか―、さっきこれも仲正さんがいったことですが、我々は普段日常的にはおそらく法というものをほとんど意識することはないはずです。ところが、ちょっとした失策や事故を起こして他者とのトラブルになったというような場合、法の一端が突然我々の存在に触れてきます。その瞬間から法と我々の関係が始まるのです。私は、カフカが注目したのはまさにそうした瞬間だったと思います。普段意識してない法が自分たちに触れてきた瞬間に一体何が起きるのかということですね。このとき、この瞬間をめぐって我々が真っ先に捉えなければならないのが、法と法外なものの関係という問題であると思います。いわば法外にいた我々が法に触れるわけです。じつは我々が法と接触したこの瞬間、逆説的ないい方に聞こえるかもしれないけど法自体が、法と法外なものに分解するんです。我々は法というと、何か条文で規定された整然とした体系があって、それによってきちんと法秩序が形成されていると、法というのはそういうものだというふうに考えがちですが、我々が法と触れた瞬間というのは、非常に逆説的なのですが。一見整然と確立されているように見える法が法外なものとの分裂・分解に向かうこと、じつは法は法外なものとの関係においてはじめて成立しうるということ、つまり、法は法でないもの、法が及ばないものとの関係において初めて法たりうるという、一つのパラドックス、逆説に基づいて成立していることが明らかになる瞬間なのです。ではそれは一体どういうことなのか。あまり長くならないよう端折ったいい方をしますが、そしてこれもさっきの仲正さんの話を受ける形になりますが、ふだん意識していない法に我々が触れた瞬間、我々はある途方もない力、暴力といってもよい力に押しつぶされ、一人残らずホモ・サケルにされるというふうに考えるべきだと思います。裏返していえば、ホモ・サケルという言葉は我々が法に触れた瞬間に個々人が陥る境遇というか状態を指す言葉だということです。法と法外なものが触れ合う瞬間ホモ・サケルが出現するのです。このときホモ・サケルである我々は法と法外なものの間で引き裂かれます。この引き裂かれた法と法外なものの関係から法をめぐるもっとも根源的な問題が見えてきます。掟の門、つまり法の門への無限の遠さ(法への入りがたさ)と、法の中心から法の門への無限の遠さ(法から抜け出しがたさ)のパラドクシカルな対によって示される法と法外なものの関係のうちに、我々はホモ・サケルとなる可能性を抱えて宙づりにされています。網が切れて法に触れ合った瞬間ホモ・サケルとなるのです。
このとき私が一つ提起しておきたいのは、法と法外なものが引き裂かれるとき、実は法外なものの側においても二重化が、法外なもの自体が引き裂かれ二重化されるという事態が生じるということです。私はこの二つの法外なものを、<法‐外なもの>と<法外なもの>という形で表したいと思います。両方とも法の外にあることを示してはいますが、両者では法の外であることの意味が少し違う。というより決定的に違うといったほうがよいかもしれません。
<法‐外なもの>としての法の外は文字通り法の外に押し出される、排除されるということを意味します。したがってさっきの西角さんのパネルでいうと、「掟の門」の田舎者が置かれている位置を示しています。さらには、さっき仲正さんがいったいじめの対象になる子ども、障害者、心神喪失者などは、皆この<法‐外なもの>に属します。この<法‐外>は端的にいうと無権利状態を意味します。たとえば日常のなかで普通に暮らしている我々が法に触れた瞬間として思い起こされるのは、外国に行ったときに空港で入国管理や通関手続きを行うときです。あの瞬間我々は完全に宙づり状態、無権利な宙づり状態に置かれます。決定権はおろか意見を言う権利もない、相手、つまり法のいうがままに従わなければならない完全な無権利状態に陥るわけです。あれは極端なケースかもしれませんが、じつは我々は日常のなかで法に触れる瞬間、それと同じことが繰り返されているのではないか。つまり無権利状態へと追いやるという形でその人間の存在をその根底から否定する、むしろ根絶やしにする、よくいわれるいい方でいえば、差別・排除や抑圧の暴力ですね、その暴力が行使される瞬間が、法の触れてくる瞬間の意味なのではないか。そしてこの無権利状態へと追いやられた法‐外なものがホモ・サケルなのです。
しかし問題はそれだけではありません。ではこの法‐外なもの、ホモ・サケルを生み出す法の力はどこから来るのか。じつはそれが第二の<法外なもの>なのです。よく途方もないとか、とんでもないという意味で法外っていいますね。<法外なもの>の法外はその意味をはらんでいます。つまりここで問われているのは、法‐外なものにされるものを法の外へと追いやっているものがもう一つの法外、つまり途方もない力としての<法外なもの>だということなのです。こちらの法外は、法の外にありながら、というより法の外にあるからこそ、法‐外な存在を無権利状態へ、ホモ・サケルという状態へ追いやる力を持つもの、そしてその力を法に付与するものです。「皇帝の使者」における皇帝はそうした存在の象徴かもしれません。しかしカフカはこのテクストの中で皇帝そのものについては何も触れていません。ただ「皇帝」という言葉が出てくるだけで、その正体は誰も知らない。はたして人格的な存在なのかも含めて、その存在は明らかでない。つまりこの法外なものは、さっきの話でいえば排除や差別や禁止や抑圧の向こう側にある、それを発動させている何か得体のしれないものなのです。つねに支配や権力はこうした得体のしれないものによって動かされています。我々は実は法の支配のもとにおいて非常に逆説的な事態に遭遇しているのではないか。つまり、<法外なもの>に<法‐外なもの>が徹底的に非対称的なかたちで排除されつつ包摂されるという事態です。法のうちにある法的人格としてではなく、法‐外なものとして法に包摂されながら同時に法‐外という形で排除される―これが、法によって裁かれ処刑されながら、法的共同体の一員であることを拒否されるホモ・サケルの意味にもなります―。しかもそれをもたらしているのがもう一つの法外なものなのです。これがあらゆる附帯条件を取り除いたあとに残る法の支配のもっとも原型的な姿というふうに考えるべきじゃないかと思います。私は、カフカの物語が我々に教えてくれているのこうした法の秘密であると思います。だからこそカフカが問われなければならないのです。