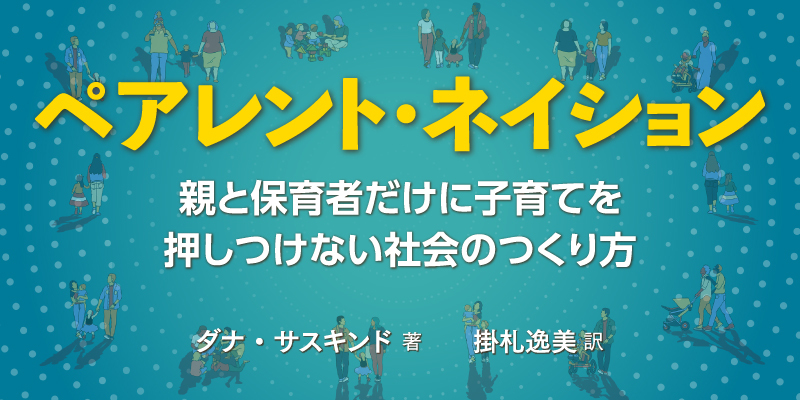『ペアレント・ネイション』推薦のことば(山縣文治)
子どもと子育てを支える社会のあり方を問う
本書は、『3000万語の格差――赤ちゃんの脳を作る、親と保育者の話しかけ』(ダナ・サスキンド2015/掛札逸美 訳・高山静子 解説2018、明石書店)の、その後の状況を示すものである。訳者によれば、本書は、「米国内で販売されている版ではなく、米国外の読者に向けられた版の翻訳」であるという(pp.324-325)。米国版に見を通していないので、何が異なるのかは不明であるが、著者が、あえて米国外向けを上梓する必要性を感じた理由を知りたいものである。
ところで、2000年代に入り、子どもの養育環境や政策的支援のあり方について、国際的には大きく2つの調査や実践が関心を集めた。1つは、J.J.ヘックマンが紹介したヘッドスタートプログラムの一環である「ペリー就学前プロジェクト」、もう1つは、OECDがとりまとめた「ストロングスタート」である。両者に共通しているのは、就学前までの養育環境の重要性、その時期の教育投資(学校教育に限らない)の個人的・社会的有効性である。とりわけ評者は、「就学前」が強調されたことで、提案の中身を表層的に理解してしまうと、プロセスではなく結果のみに関心を持ったり、その責任の中核に保護者を位置づけたりする可能性があることに不安を感じていた。社会的には、実践の対象が低所得者中心となっていること、データが古いことなどの限界も指摘されていた。サスキンドらの実験を紹介した前書も本書も、このような評価と共通の部分がある。
誤解されることを覚悟のうえで言うと、評者自身は、ペリー就学前プロジェクトや3000万語の格差については、慎重に取り扱うべきと考えてきた。たとえば、両者の実験は、いずれもジョンソン大統領時代の貧困戦争(war on poverty)との関連を抜きに考えることはできないと思われる。貧困戦争は、州単位の福祉施策が多いなかで、米国政府が国家レベルで取り組んだ、経済機会法(Economic Opportunity Act: 1964)で本格化する。時代背景もあって、貧困は、今日のような相対的貧困とは必ずしもとらえられていない。加えて、これはベトナム戦争隠しという批判もあるように、子どもを含む貧困者のためという公式の見解以外の政治的要素が絡んでいたということである。結果として、この法律はニクソン大統領の時代である10年後に大幅に縮小され、17年後の1981年、レーガン大統領時代にはほぼ廃止となった。その後、2015年、オバマ大統領の時期に子どもの貧困法(Child Poverty Act)が提案され、連邦議会の委員会も通過したが、結局成立することなく、トランプ大統領の時代を迎える。
本書に直接関係ないと思われる叙述が続いたが、ここで言いたかったのは、2つの実践的研究の評価を、アメリカの政治状況との関連を抜きに評価することの危険性である。すなわち、民主党と共和党の政権交替と大きく関係していることが推察されるということである。子どもの成長や教育効果が発揮されるには時間がかかるとはいえ、たとえば、知能指数に代表される認知能力の向上には成果がなかったと評価され、経済機会法の縮小の一因ともなったといわれるペリー就学前プロジェクトが、民主党政権時に、子どもが生み出す経済効果が顕著にあり、再度脚光を浴びた点などはその例である。サスキンドの実践については、直接民主党政権との関係をうかがわせるものは私の手元にはないが、子どもの貧困法が議論されている時期に少人数の取り組み成果が大きく取り上げられ、社会的関心を集めたことは、冷静に分析する必要がある。
評者は、社会的養護、就学前の教育・保育、地域子育て支援などのフィールドを中心に、主として子ども家庭福祉の制度研究を行ってきた。上述のコメントはこのような立場からの指摘にすぎず、研究内容そのものに強い疑問を示すものではない。研究結果の活用が政治的に利用される可能性があることを指摘したにすぎないことは理解いただきたい。
さらに、サスキンドのような保護者にも理解が容易な実践的研究は、逆に、保護者の一部に誤解を与え、3歳児神話、さらにそれに母性が加わり、3歳児母性神話の復活や、非認知能力ではなく、認知能力への関心の傾倒、声掛けや読み聞かせの呪縛など、サスキンドが意図しない方向での浸透への懸念もあった。本書の第1章「新たな北極星に向かって――本書が伝えたいこと」では、このことが強く意識されていると伺える記述が数か所ある。たとえば、以下のような記述である。
「社会は、子どもの脳を育てるために必要な条件を保護者に保証しなければならない。さらに、誕生後3年の間にこそ、子どもに積極的に働きかけ、脳の基礎を築かなければならない」(16頁)。
「人生のもっとも早い段階から社会が投資しなければ(アンダーライン評者)、大人も子どもも利益を得られないだけではなく、投資し損ねたが故の大人も子どもも利益を得られないだけではなく、多額の罰金を支払うことになるのです」(28頁)
「自助の神話」(29頁)
「(評者注:保護者は)自分たちでなにもかも『せざるを得なかった』」(29頁)
本書のサブタイトルも「親と保育者だけに子育てを押し付けない社会のつくり方」(Unlocking Every Child’s Potential, Fulfilling Society’s Promise)と社会のあり方を意識したものとなっている。このことを通じて、ペアレント・ネイション(保護者の国)を作るというものである。「異次元の少子化対策」は重要であるが、児童福祉法の精神に基づき、子育ての責任を保護者と社会が共有することがそこに加わらなければ、保護者の責任と負担が増す可能性があることも意識しておく必要がある。
この間、サスキンドらは、さらに実践を進化させ、シカゴ大学に『子ども期初期の学びと健康のためのTMW(3000万語)センター』を設置している。訳者である掛札氏はそこを訪れ、サスキンドらと直接交流しているという。ここでは、ペアレント・ネイションの基本的考え方として、以下の4つが示されている*。
保護者には実際的な選択肢が必要(Parents have real choice)
子どもには早期からの(社会的)投資が必要(Children are invested in early)
保護者の知恵と知識を尊重(Parental wisdom is honored)
雇用主との協働(Employers are allies)
また、前書で強調された3点も引き続き指摘している。
Tune In(チューン・イン)
Talk More(トーク・モア)
Take Turns(テイク・ターンズ)
日本では、保育所制度を中心に子育ての社会化が1960年代から進んだが、これは主として就労によって社会的子育てが必要な家庭に限定されていたといってもよい。1990年代からは地域子育て支援が進み、すべての家庭を対象とするものにはなったが、いまだ十分ではない。2000年代に入ると、介護保険制度や障害者総合支援制度など、家族の意向ではなく、本人の意向を尊重した制度が発足、普及し、子ども領域は、社会化が遅れていると言わざるをえない状況となりつつある。
本書は、保護者や保育者が子どもとどう向き合うかを意図したものであるが、子どもと子育てを支える社会のあり方を示すものとしても評価できる。本稿に示すように、本書は単独で評価するよりも、前書を合わせて評価すべきものである。新たに、本書を手にしたいと考えておられる方は、ぜひとも前書も合わせて読んでいただきたい。