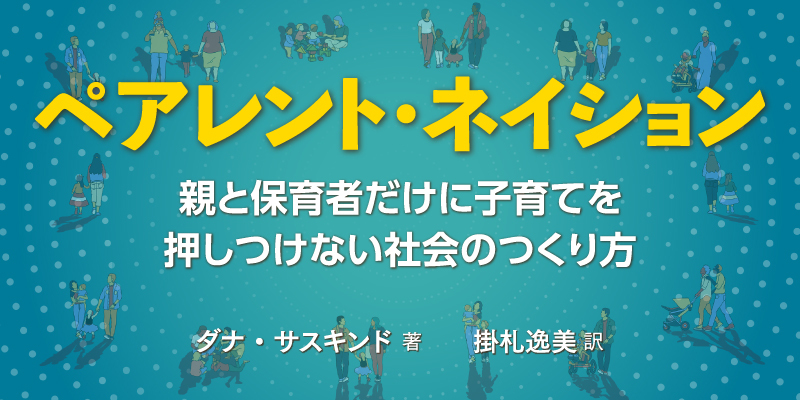『ペアレント・ネイション』推薦のことば(小崎恭弘)
保護者であることの困難──保育・教育・社会システム
本書では、Parent(ペアレント)という言葉が多様に取り扱われていることが興味深い。母親、父親、祖父母、ケアする人、保育者、他のおとなといったさまざまな表現がされている。しかし、本書で強調されている「保護者」とは広い概念であり、子どもの成長を委ねられている“おとな”を指している。「ペアレント・ネイション」つまり「保護者の国」とは将来の社会を作り出す子どもへの愛情と労力を惜しまない、多様な人的豊かさを示したものであり、それらの人的な環境が満たされている社会を指している。少子化の進展が止まる様子のない我が国において、その豊かな社会を私たち大人は創ることができるのであろうか? 本書が、私たちに投げかけた大きなテーマである。
著者ダナ・サスキンド博士が執筆した『3000万語の格差』では、乳幼児の間に豊かで温かな会話とやりとりを行うことが、子どもの脳の発達の基礎となり、どのような影響を与えるかについての知見を説明している。脳の豊な発達は、子どもの育ちを支えやがては、豊な社会を支えることにつながる。生まれながら脳の状態は未完成であるため、どのような関わりを受け、どのような環境でどのような愛情を受けるかが重要である。脳の発達はタイミングが重要であり、神経細胞のつながりを作り、脳全体の働きを調整していく驚異的な能力である「脳の可逆性」は、生まれてから3歳までの間が著しく発達することがわかっている。この時期の大人からの関わりの中でも、会話ややりとりといった愛情のあるケアは、子どもと関わるときの基本である。これは、教育のレベル、収入、職業にかかわらず子どもの脳の発達を促す方法である。そして、保護者を含む社会全体としての“おとな”は、社会全体の子どもの脳の発達に貢献できる可能性がある。それを実現することが「保護者の国」としての役割としている。すべての子どもに「同等の機会」を保証することである。現代の我が国は「ペアレント・ネイション」となり得るのであろうか?
さらに本書では、近年の幼児教育の重要なキーワードでもある「非認知能力」についても実例が示されている。幼児の非認知的なスキルの獲得の成果を検証するには、長くの時間がかかる。グリット(やり抜く力)やレジリエンス(忍耐力)といった非認知能力と、これまで多くの研究結果が示されている認知能力には、強い結びつきがあることも言及している。そして両スキルを育てるために強力な力を発揮するのが「保護者」であり、その保護者の価値観や関わり方が重要である。がまんの実験などから「子どもが行動をコントロールする方法を学べるよう、保護者は助けていくことができる」ことを紹介している。さらにこれまでの社会では、子どものさまざまなスキルが身につくことが前提で社会が成り立ってきていた風潮があるとしている。まさにこれからの幼児教育において非認知能力への取り組みが、期待される。
「保護者の国」として“おとな”に求められる役割は非常に多いにもかかわらず、“おとな”に対しての支援は十分なのであろうか。また保護者が、赤ちゃんの健康な脳を育てるのに必要なことを学んだのはいつであろうか。まだ学んでいないのであればそれはいつ、どのような手段で学ぶことができるのであろうか。とさまざまな、当たり前であり、また本質的な疑問がなされている。これらに対する答えを私たちはどのように用意すれば良いのか? これが私たちに与えられた課題である。さまざまな職業がある中で「保護者」という役割は実に困難なものであると同時に意義のあるものである。しかし残念ながら“おとな”になる訓練学校はない。
ペアレンティング・スキルについて親自身は、さまざまな関わりを通じて、自らが子どもと関わる術を見つけなくてはならない。そこには赤ちゃんや子どもの取り扱い説明書はない。一度にたくさんのことを学ぶことは困難ではあるが、保護者が子育てを行う際に最も重要視しなくてはならないことは「健康な脳を育てるには、愛情にあふれた大人の関わり」である。社会の多くの大人が子ども達に愛情にあふれた関わりをすることが、その社会全体を豊な社会にすることができる。子育てや教育は、そのような社会を作り出す最も確実なものである。
「保護者」は子どもを育てるものとして、また人としての成長においてペアレンティング・スキルを自分自身で身につける必要がある。しかしそのことにより保護者自身に、不安や葛藤が襲う場面も少なくない。本書の紹介例では「なぜ、私はこんなに大変な思いをしているのだろう…他の家の子どもとは普通に接していられるのに。こんなふうに感じる必要はないはず。私の何がいけないんだろう?」と産後の葛藤を経験した事例を紹介している。
多くの保護者は子育てを通じて、同様の経験をしたり聞いたりしたことがあるだろう。また、そのような経験をしている人々は、どのような社会システム・政策を求めているのであろうか。本書では、それらについて多くの事例紹介がある。その根幹にあるのは、保護者の健康状態が子どもに及ぼす影響の大きさを示すものである。子どもにとっての保護者の重要性に、さまざまな視点からアプローチしており、子育てのサポートに関わる保育者や教師などにとっても示唆的である。あらためて保育の可能性を感じることができる。
小児外科医である著者が、医学的な観点からさまざまに子どもと子育てを捉えているのも、本書の大きな特徴である。子どもの脳の発達や言葉の獲得のプロセスのありようが、いかに良い社会づくり貢献できるかについても多く述べている。例えば乳幼児突然死症候群(SIDS)である。今では乳幼児突然死症候群に関しての知見は増加し、「うつ伏せ寝をさせない」といった乳児に対しての啓発活動や保育施設での事故防止策が取られている。1980年代当時の先進国が進めていた事故防止の手段はなんと「うつ伏せ寝」を推奨していた経緯がある。このように、子どもの成長を委ねられている“おとな”の誤った見解が、場合によっては子どもの健康を阻害する可能性がある。つまり子どもの脳の発達を保証するためには、子どもに関わる“おとな”の教育にも目を向けるべきである。直接子どもに関わる保護者や保育、教育に関わる周りの大人や社会、あるいは専門家に対してさえ、その学びの重要性を示唆している。その情報は多くの人にとって使いやすい情報となっているのか。我が国の保育、教育に関わる人々への、大いなる警告である。「保護者の国」に必要なこととは、生まれてから3歳までの重要な時期の子どもと保護者を正しく導くための教育の手段が、政策面や社会的な認知、システムとして備わっているかということである。
サブタイトルとして「親と保育者だけに子育てを押し付けない社会のつくり方」とある。しかし残念ながら我が国に目を向けると、子どもを育てることに関して、その親の責任論はますます強固なものになっているように感じる。その一つの象徴が「親ガチャ」という言葉であろう。親の所得や職業、社会的な地位などにより子どもの育ちが決定づけられてしまう、親次第で子どもの育ちが規定されるという考えである。SNSで話題となりメディアにおいて多く取り上げられた。
そのような現代社会のあり方に真っ向から立ち向かい、そして子どもの育ちに大きな希望を感じられる本書である。子どもに関わるすべての人のあり方や、その温かさが子どもとそして親を育てる。特に支援者には巻末のガイドやアクションガイドを活用してほしいと願う。より実践的な視点での支援につながると感じる。