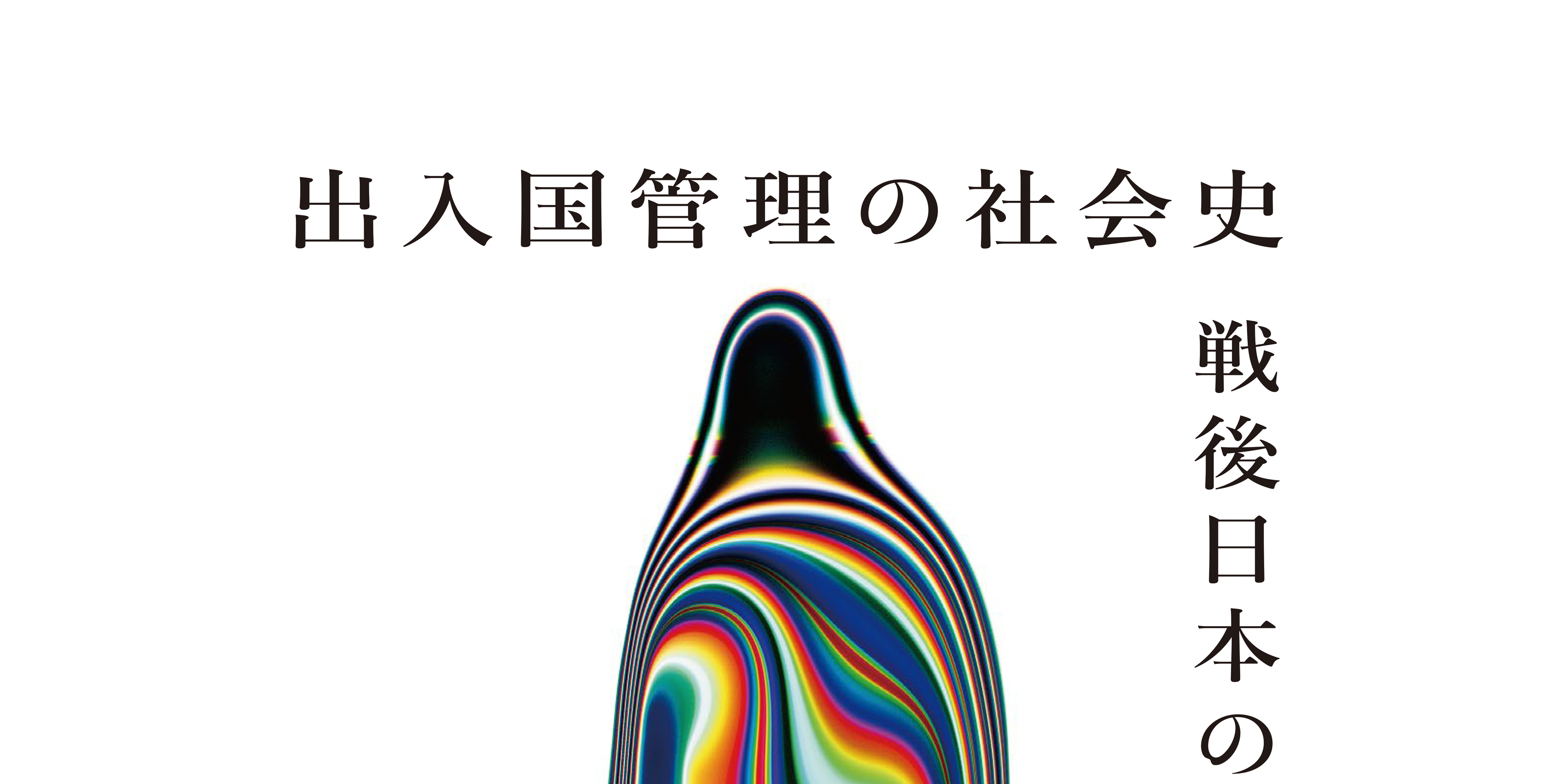朴沙羅「誰がこんな仕組みを作ってしまったのか」――李英美著『出入国管理の社会史』書評
2023年6月9日、出入国管理及び難民認定法の改正案が参議院本会議で可決された。この改正案は在留特別許可申請手続の新設、被収容者の処遇に関する手続規定の整備、収容に代わる監理措置制度の創設、難民申請者に対する送還停止の効力の一部解除、難民に準じた者の補完的保護制度の創設、送還に応じなかった者に対する刑事罰を含む退去命令制度の創設などの内容を含んでおり、移住者と連帯する全国ネットワークや日本弁護士会といった団体や個々人が、全国各地で反対を表明していた。
誰がこんな仕組みを作ってしまったのだろう。なぜこの法が成立することを、私たちは止められなかったのだろう。そのような疑問に突き動かされた人に、私は本書を強く勧める。
本書は、「第二次世界大戦後の冷戦と脱植民地化という国際環境のもとで形成された日本の出入国管理政策が、とりわけ地域社会においてどのようなかたちで執行され、国民・国籍・人の移動をめぐる「境界」を立ち上げてきたのか」(p.5)を問いに掲げる。
戦後日本の出入国管理・外国人管理制度が発足した時、「制度のレベルと、行政実務などの現場レベルとのあいだ」には「無視できない乖離」(p.7)があった。著者は、日本各地の文書館に保存された出入国管理及び外国人管理に関わる行政文書から、この乖離がどのように埋められていったのか、前者が後者にどのように影響を及ぼしていったのかを明らかにする。
第1章と第2章は、1950年代初期における外国人登録業務の現場に焦点を当てる。外国人登録業務において、誰が登録されるべき「外国人」であるのかを名前や服装、言語等から判断することは困難だった。他方、「外国人」あるいは「第三国人」と犯罪が政治の場で結びつけられる中、偽名を名乗って「外国人」になりすます日本人もいた(p.33-36)。
この混乱の中で、1950年ごろから、日本の各地で外国人登録事務協議会が発足した。この協議会では、外国人登録に関する法令の解釈や各地域の実務実態の情報交換が行われた。このような協議会が設立された背景には、外国人登録業務が膨大な業務を必要としたことがあった。毎月「国籍別人員調査月報」や「外国人国籍別職業別調査月報」を作成し、登録申請書には身元情報に加えて日本居住に至るまでの経緯を記入しなければならず、数年ごとに外国人登録を切り替える以外にも、随時、登録事項を確認しなければならなかった。
地方の外国人登録事務員は、登録を拒否する朝鮮人たちを「忍耐強く応接」(p.70)し、「これら外国人を善導」(p.70)した。窓口でのやり取りから「精神的負担」を訴えるものや、登録切替の煩雑さと難しさから「神経衰弱」に陥るものも現れた。しかし、現場に混乱をもたらした法務省は強硬な姿勢を崩さなかった。外国人登録証の切り替え期限を延長せず、どのような申請が「法的期限内」なのかを明確にし、警察の介入も認めた。そして1950年、「不法入国者」と「外国人」の移動を正確に把握するための、外国人登録証の切り替えが実施された。
第3章は、朝鮮から日本へ渡航しようとしてきた「密航者」を発見しようとした九州・中国地域の取り組みを描いている。「不法入国者」の逮捕・収容・送還を日本側で担ったのは警察(国家地方警察・自治体警察)・海上保安庁・出入国管理庁の3者だったが、この3者の分担と連携は困難だった。旧警察制度は占領改革の中で解体されようとしていたが、日本政府は退去強制業務に警察を活用することが現実に即していると判断していた。
1950年以降、警察が担っていた退去強制令書の執行は出入国管理庁に所属する入国警備官が行うことになったが、その育成に十分な予算がなかったため、警察官の経歴を持つものが採用された。
この予算と人員の不足、分掌の曖昧さを埋めたのは、沿岸地域における民間人の活動だった。鳥取県では、消防団員や防犯隣組が、あるいは戦前に結成された「犯罪防止会」が再度結成されて、「密航」の発見を含む「村内治安確保」(p.91)が行われた。島根県では、沿岸地域の消防団員と民間人が「密航監視組合」を組織した。「密航者」問題に取り組んだ人間の中には、GHQや日本政府、警察や出入国管理庁だけでなく、地域住民も含まれていた。1960年代に警察が沿岸部に設置した看板「海から平和をおびやかされまい!」は、当時の人々の気概を伝える。
第4章は大村収容所へ視点を移す。大村収容所には、非正規に日本へ移動し、退去を強制された「不法入国者」たちが収容された。1952年4月に日本が独立して以降、韓国政府は大村収容所から韓国へ送還された被収容者の受け入れを拒否し始め、1954年には一時的にではあったが、全面的に受け入れを拒否した。そのため日本側は被収容者を送還できず、大村収容所は過剰収容状態に陥った。結果として、大村収容所の建物増設だけでなく、仮放免手続きの簡易化と「確実な身元引受人」や保証書による釈放が進められた。
このとき、大村収容所からの釈放者の受け皿となった善隣厚生会は、「植民地期の朝鮮人に対する厚生保護事業のネットワークを結集して戦後に設立された機関」(p.122)だった。そのほか、入管局長が中心となった日韓親和会や、岸信介政権下で日韓関係を重視する「親韓派」が中心となった日韓文化協会も、大村収容所からの釈放者の身元引受団体となった。つまり「収容の「合法性/正当性」に対する根拠・価値観が、朝鮮半島を中心とする東アジア国際情勢および政治の原理に強く支えられたことを示していた」(p.147)。
第5章は、この大村収容所を取り巻く地域社会、中でも小学校に通う児童と教員を描く。『綴方風土記』(九州・琉球編)には、「密航」してくる朝鮮人や「李承晩ライン」で拿捕され、帰って来られなくなった漁師の父といった話題が上がる。「密航者」は食糧不足と生活苦をもたらし、「李承晩ライン」は家族の別離をもたらすものとして認識されていた。このような長崎県大村市での綴方運動を主導していた教員は、「平和をもとめる生活作文」を指導することに熱意を持って臨んだ。その後を引き継いだ別の教員は、大村市中央小学校児童による大村収容所への「慰問」を実現する。
後日、児童たちはこの「慰問」の様子を作文に書き、そのうちの1作は、1959年に読売新聞社主催第9回全国作文コンクールで佳作に入賞した。著者は学級通信に書かれた「慰問」の様子と、入賞した作文とを検討し、作文では李承晩ラインや「密航」の問題がより具体的に綴られ、また「日本」あるいは「日本語」が頻出することを指摘する。
さらに、この作文「友情をつなぐ学級」は、コンクールで佳作に入賞した翌1960年、『日本の子どもたち』として映画化された。著者は、その映画の中で、子どもたちが常に純粋で、正しい存在として描かれていると指摘する。その「正しさ」と「悪」、「日本」と「朝鮮」、収容所の「内」と「外」は「逆転したり、境界線を越えたりといった緊張をはらむことはなかった」(p.182)。
大村収容所への「慰問」が終わった後、児童たちは大村収容所に収容されている同世代の子どもたちとの文通を続けた。教員は手紙を翻訳し、1つ1つに自らの所感を添えて、学級通信に掲載した。児童たちの中には、大村に収容されている児童が日本語を解することに驚き、「なんでこの人が[引用者注=大村収容所に]入らないかんのかわからんかった」(p.189)と述べるものもいた。しかし、その問いは答えられることがないまま、大村収容所にいる子どもたちは日本の教師と子どもたちにとって「慰め」の対象であるにとどまった。
本書は出入国管理をめぐる境界線が「実際には不明瞭さ・不確かさをともなうゆらぎや、曖昧さを内包していた」(p.199)こと、そしてこのゆらぎや曖昧さの中で、「現場の状況に応じて「規範」を独自に読み替え「外国人」と「日本国民」とを位置づける実践が積み重ねられた」(p.200)ことの2点を、豊富な資料を駆使した簡潔な記述によって指摘する。この「規範」の読み替えによって境界を紡ぎ出す実務によって、戦後日本における「外国人」が生み出されていった。
著者は「外国人」とされた個々人にとって、彼らを取り巻く法制度だけでなくその執行プロセスも問題となり得ることを熟知している。それは、本書のあとがきに示された「戦後の日本社会が「外国人」に向けてきた執拗なまなざしを追体験するかのようなフィールドワーク」(p.275)から著者が学んだ結果でもあるだろう。本書の副題である「社会史」が「社会」の「史」である理由は、おそらくこの点にある。
その社会に目を向けたとき、戦後日本社会を支える、ごく普通の善い人々の姿が見えてくる。本書に記述される人々の中には、悪人も国家の意思も倒すべき指導者もいない。その代わり、優秀で職務に熱心な、平和な日本を守ろうとする善良な人々が登場する。
長野県内のある事務職員は、日本名で生き、読み書きのできない、外国人登録証を持たない高齢者を訪ね、登録証を切り替えなければならない理由を説き、彼の写真を撮影し、管区の警察署まで同行し、途中の自動車賃を立て替えた。
地方自治体の職員たちは、「殆どの書類を代筆させられる現実と立法者とのズレから起こる愚痴」(p.67)や「実情の判って居る第一線から見たまどろしさ」を訴え、「其の無意味さにやりきれない思い」がすることを隠さない。それでも彼らは、「時間が有れば、私生活の相談相手にもなってやりたい」と「専門的な業務の最前線に立っていることへの自負心」(p.67)を持って業務に臨み、時たま表彰される程度の褒賞で、この業務をやり遂げた。
日本海沿岸に住む漁村の住民たちは、自分たちの平和な暮らしを守るために、「密航船」を拿捕しようと警察や占領軍に協力する。「自警団」が警察と密接な協力のもと朝鮮人を発見しようとする姿は、植民地支配が終わったことを忘れさせる。
綴方教育を通じて平和を願う児童を育てようとする教員にとって、大村収容所の中にいる「韓国人」は、彼の担当する日本人児童のための教材に過ぎない。その教師の使う言葉に「韓国」と「北鮮」はあっても「朝鮮」はない。彼がどれほど丁寧に学級通信を発行し、1つ1つの作文を指導し、文通を励まそうとも、その教員にとって大村収容所の中にいる子どもたちは、「慰め」の欲望を向ける対象だ。
凡庸な悪という、もはやそれ自体が凡庸に響くような言葉は、本書の記述の前では陳腐だ。「外国人」は法令が制定されることによって一朝一夕に生まれたのではないことが、本書を読めばつぶさにわかる。善意に満ちた人々の、熱心な取り組みは、こうして戦後日本社会に「外国人」をつくりだし、制度の中に押し込め、それを破る力を奪う。
戦後日本における「外国人」は、本来なら無理だったかもしれないような法令を現場レベルの努力で実行可能にできるような、優秀な現場の行政職員たちと、地域の平和と安寧を願い、そのために自分自身の時間やエネルギーを割くことを厭わないような善良な個々人によって、生み出された。その熱意と親切さは、まるで良質なホラーか、ぞっとするコメディを見ているようだ。
そのホラーあるいはコメディの演者たちにとって、「外国人」たちの個々人のかけがえのない人生は徹頭徹尾、客体である。「誰がこんな仕組みを作ってしまったのか」――本書においてその答えは簡単だ。私やあなたのような、頑張り屋さんの、辛くても頑張る優しい人々が、みんなで一生懸命に力を合わせて、こんなことを成し遂げた。その制度の中に閉じ込められる人々の苦境から、目を背けながら。
もし本書から希望を見出そうとするならば、それは本書が中心的に記述した、行政と地域社会にある。いかなる法も、それを執行する人々なしに実現されないのであれば、行政の現場において、職員と「外国人」、そしてその「外国人」を支える人々が何をなし、どのような実績を積み上げるかによって、法の実態を変えることができるのかもしれない。その意味において、本書の記述は読者1人1人を勇気づけるものでもある。