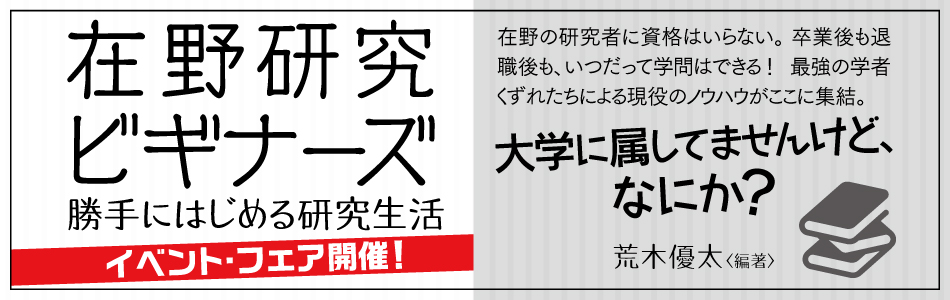対談 荒木優太さん×熊野純彦さん:困ったときの在野研究入門 第3回
(在野)研究者の「役割」と「役柄」
(荒木:) さて、本筋に戻ると、私が廣松さんの話をしたのは、彼がある種の役割論を展開した人でもあったからです。たとえばいま私は在野研究者としてみなさんの前で喋っています。ただ、それが私の役割のすべてかといえばそんなことはなく、私には有島武郎研究者という別の面がある。しかし、この面を採用した瞬間、お客さんがいなくなってしまう。誰も有島に興味ないですから。在野研究者としての役割には需要があるが、有島研究者としての役割には需要がない。
この分裂に私はずっと悩んでます。つまり役割は自分の意のままにならず、他者に適合してはじめてその真価が認められる。在野研究者としてはまあいいけど、有島研究者としての役割はお呼びでないよ、と。こういうときに思い出すのが、廣松さんが「役割」と「役柄」という言葉を区別して用いていたってことです。「役割」が人の柔軟な振る舞い方であったとして、「役柄」というのはそれが物象化されてしまった姿。役職や部署や肩書みたいに外化して物みたいに固まっちゃっている。熊野さんは『戦後思想の一断面』(ナカニシヤ出版)という本で、この廣松役割論を即興劇モデルとして解釈してますが、在野研究者であれ有島研究者であれ、肩書に自分が囚われてはいけなくて、振る舞いの柔軟さこそが大事なはずです。
反対に、「在野研究者」という自称が、もし役柄的拘束を解除するのならば、それは素晴らしい。「サラリーマン……だけど、私は在野研究者です」ということが在野研究には許されている。勝手に言ってるだけですから。そして勝手に言っていい。そういう風に割り当てられた役柄を少しだけズラす、振る舞いの柔軟さを取り戻す機会になれるのならば、在野研究を喧伝する甲斐もあると思うわけです。熊野さんも東大教授というなかなか厳めしい役柄を負っているわけですが、そのあたりいかがでしょうか。和辻哲郎やカール・レーヴィットといった思想家への関心にもおそらく結ばれることと思うのですが。
熊野: まず時系列から言うと、カール・レーヴィットは哲学的役割論の走りなんです。社会学的役割論より随分先行しているんですね。社会学的役割論っていうのはstatus and roleといって、ステータス(status 立場)によってロール(role 役割)が決まるわけですけれども、レーヴィットのところでロールの先行性っていう了解はあるのです。そういうものと関連が深い和辻さん的なもの、それから、少なくとも一見それに近しいところがある廣松役割論、そういう問題圏内でものを考えた時間の方が、ぼくの中では長いのですね。もう20歳前後からずっとその問題圏内にある意味で囚われていました。別の言葉を使えば、それは日常性の周到な分析ということになって、日常性をきめ細かく分析するときに役割・役柄っていう概念装置はとっても便利で、ある意味で不可欠なんです。
そこでその理論的な話とやや個人的な話を交錯させてしまうと、自分自身の中で分裂があるんですよ。ぼくはある意味で、なんの因果か、大学の中で結構長く行政的な職もやってきました。今は附属図書館長を兼ねた副学長なんですよ、自分でも「似合わねぇなぁ」って驚いちゃうのですけれど。そういうときに、ぼくは、その役柄にぎりぎり、役柄を求められるところにぎりぎり誠実であろうと思っています。それによって自分も縛られています。「そんなもん!」っていうふうに放りだしはしません。ところが他方では、常にその役柄に対して若干自分でずらかしをしようとも思っています。今日、(熊野氏の)この恰好を見てうちの連れ合いが、なにその売れない芸能人みたいな恰好って言ったんですけど。東京大学附属図書館長としてはたぶんね――ネクタイしめているからいいでしょっていうのがぼくの理屈だけど――、おそらく標準的に言うと、あんまり品のいい格好じゃないだろうなっていうことも自覚しています。ある種の場では勝手なことも言っていますけど、他方では、役柄に忠実であろうともしていて、その中で明らかに自覚的無自覚的な亀裂とずれが生じています。でも、それはそういうものだろうと思っています。
それから、他者を問題にしたときにやっぱり役割役柄では拾いきれない他者の深みや遠さみたいなものがあって、ぼくはそこからかなり系統が違うレヴィナスみたいな思考に一時期親しみました。これはものすごく口頭だと議論が単純化しやすいところで、ぼくとしては嫌なところでもあるのだけれど、やっぱりね、日常なんていうのはごく簡単に非日常性にひっくり返っちゃうんですよ。だから実は日常性も一色(ひといろ)ではない。ただ、日常性を見つめて、その日常性の中に一色(ひといろ)ではないものを見届けるためにも別の視点が必要だっていうのが、ものすごく図式的に整理すると、ぼくのある意味で思考の振幅の中にあります。
つまんない話を言うと、レヴィナスに関わる研究や翻訳を発表し始めたときに、言ってみれば廣松学派の面々からそっぽを向かれるようなこともありました。左翼の悪い癖でね、レーニンが背教者カウツキーっていうのを書いているでしょう? だから「背教者」ってよく言いたがるのですけどね、ぼくはそのときに「背教者熊野」と言われたわけです。今から言うとちょっと実感として遠のいちゃうのだけど、当時まだ「おフランスもの」がいわば十分に「おフランスもの」だったのです。ぼくは廣松派であり、且つドイツ系であると思われていて、「あの野郎、ちゃらちゃらと「おフランス」に手を出しやがって」と思われたわけです。ぼく自身はそんな悪口ほとんど気にしないと言いつつ、もしかして実は結構深く傷ついたかもしれません。あんまり長くなっちゃったから一旦切りましょうか。
荒木: 話としてはずっと同じような主題が続いているかと思っていて、つまり、在野と大学というふうに言っても、大学の中の在野とか反対に在野なんだけどもある種の制度で凝り固まってしまうこともあるんじゃないか、そういうことですね。これはちょっと個人的な関心なんですけども、黒田寛一に『〈異〉の解釈学――熊野純彦批判』(こぶし書房)っていう本があってですね、熊野さんはひどく批判されているわけです。あれはいま仰ったような「背教」によって生まれた本なんですか? そもそも、読みました?
熊野: そうだな、もうだいぶ経ったからいいですかね、舞台裏を喋っちゃっても。ぼくは70年代に高校・大学生活を過ごしているので、すこしは実感があるわけですけれども、70年代にあの本が出ていれば、どうだったろうか、と思います。70年代っていうのは、新左翼の各党派が、物理的に相手を殺し合った時代でした。だから世が世なら、あれは「反革命・クマノを殲滅せよ」というメッセージとなりえたものなんですよ。
荒木: まじっすか、やばいっすね。
熊野: うん。ほんとにね。でももう一面から言うと、あれはある意味でとても奇妙なところもある本で、なんて言うんだろう、黒田さんには、廣松さんに対する「愛情」めいたものもあるのですね。新左翼最大の党派の一つ、革命的共産主義者同盟の理論的指導者、黒田寛一さんと、むしろ第二次共産主義者同盟と縁が深い、かつての新左翼最高の理論家の一人だった廣松渉との間にはいろんな因縁もあり、党派的な対立はあるんです。哲学的に言っても、あるいはマルクス理解という面からしても、黒田さんは代表的な疎外論者の一人だし、廣松さんは物象化論の旗手ですから、そこにも対立がある。ところがあの本は――口頭での議論だから、ものすごく単純に言います――、自分が立場の違いを超えて愛してやまない廣松渉を、なぜ熊野は裏切るのかっていう、微妙なニュアンスを含んでいたのです。ぼくはあの本が出たとき、もちろん一瞬ぎょっとしましたけど、でもそのあともう開き直っちゃって、いろんな人に対して「すごいだろオレ、生きているうちに自分の研究書が出ちゃったんだぞ」とか、著者名じゃなくて書名に「熊野純彦」って入るなんて、これは大変名誉なことでしょ、とかって言っていました。
荒木: なるほど。いや、私もその反応でして「熊野さんすごいな、クロカンに研究されてんじゃん」みたいな。私にとってクロカンとか歴史上の人物でしかないので、むしろすごいなとか思っちゃったんですけども。いろんな歴史があったということですね。