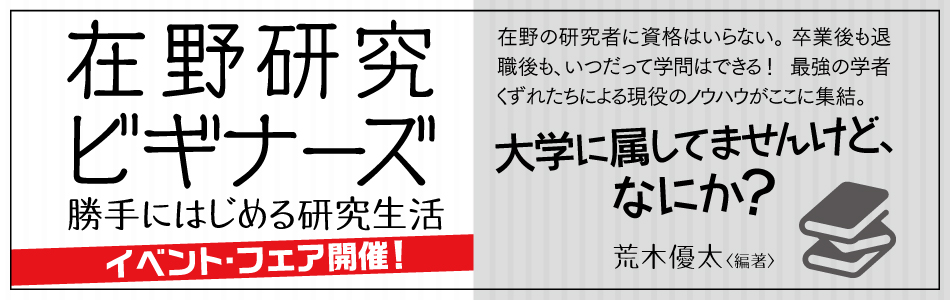対談 荒木優太さん×熊野純彦さん:困ったときの在野研究入門 第2回
二人の意外な関係
(荒木:) ところで、そもそも熊野さんって超ビッグなゲストじゃないですか。で、私とか、知ってる人は知ってるけど知らない人は知らない、小物な書き手だと思うわけです。なのに、なんでこの対談が成立しているかというと、私はかつて群像新人評論賞の優秀賞を取った、というどうでもいい経歴がありまして、その評論の選考委員の一人だったのが、なにを隠そう、熊野さんだったわけです。で、これは推測にすぎませんが、その選考委員の中で、もっとも私の論文を高く評価してくれたのが熊野さんだったかなと思ってます。ただし、まず最初に「だれが見ても破綻している」とダメ出しされていて(笑)。でも、「評論にはまちがう権利があり、切実な誤読は一箇の解釈となりうる」という仕方でフォローし、そして推してくれてます。これがなかなか興味深い。というのも、俗に評論とか批評と呼ばれている分野のものは、学術論文ではないけども論理的あるいは知的な文章として流通していて、そして、そういう形式でしか発揮しえない知があるような気がする。私はもちろん、熊野さんもそう思っているのではないか。当然、勝手がすぎると学問がもっている厳密さを壊しちゃったりするわけですが。そういう文脈で、なんで私のことを評価してくれたのかちょっと聞いてみたいんですけど、いかがでしょうか。
熊野: それはすごくやっぱり難しい問題で、3人の中でも結論出なかったし、実際に応募作を読むのに先だって3人で、雑誌上で対談もしているのですけれど、そこでも微妙に立場が分かれました。それから3年間か4年間か議論をして、その都度やっぱり立場が分かれて、結論を見ないのですけれど。一旦は、批評といわゆる学術論文、ぼくは区別したほうがいいとは思っています。ただ、その前に荒木さんから自費出版の最初の本が送ってこられたわけです。『小林多喜二と埴谷雄高』でしたか。
荒木: そうです。
熊野: ぼくはその本も大変面白く読んだのです。一応、評論賞では、応募者名はブラインドで審査するのですね。結果が出たときに、あっ、これは「あの荒木さん」と同一人物じゃないかって驚いた。率直に言って、3人の中でぼくがもっとも高く評価したことになるでしょうね、それは。そのときに出た議論として、これだけじゃロールズ論にならないっていう、これはまっとうな、学術論文に対する評価だったらまっとうな意見も出たのです。でもぼくは、それは批評の特権だろうって言いました。ロールズのあの範囲で論じるにしても、普通のロールズ研究ならば言及するけれども、荒木さんが言及しない論点っていっぱいあるわけですよ。そういう意味でロールズ研究としてはおそらくは成り立たないけれども、ロールズの、他の人はあんまり注目しない、しかしロールズの中に確実に存在する「偶然性」っていう問題を丁寧に掘り起こし、しかもそれを論じる筆致がね、魅力的なわけです。ぼくはやっぱり一発で騙されてしまいました、この人のレトリックに。やっぱり、うまいんです、書き方が。批評家としての文体をちゃんと心得ている。そもそも批評の審査をぼくなんかがやるのはおかしいのだけれども、でもそのときに思っていたのは、ああいう場で評価すべき批評というのはそれ自体作品じゃなきゃいけない、文学作品とならなきゃいけない。文学作品であるためには文体を、しかも魅力的な文体を持ってなきゃいけない、これは、ぼくとしては譲れない一線だと思ったのです。
ところが(賞の審査の)一年目に蓋を開けてわりとガッカリしたのは、これ学会誌に出せばいいじゃないっていうのが結構来るんですよ。註がびっちり付いていたりする。いやしくも商業誌「群像」でやる以上、学会誌で落とされた論文を回されちゃたまんないよっていうところもあるわけです。だからやっぱり、文学作品としての批評を書くっていう意識が強くあってほしい。それを強く感じたのは荒木さんの文章だけでした。だからぼくはそのとき以来、改めて荒木さんのお書きになるものに注目しています。
荒木: ありがとうございます。他方、いまの話は、アカデミズムの中で評価され、ポイントになっていくはずの学術論文に色々なヘンなものが混じっちゃうじゃないか、という理解もできると思うんです。つまり、私の場合は変に筆致(レトリック)がうまい、だから人々を騙せちゃう、そういう危険が内在していると。学術論文は正しいんだけど面白くない、かといってこれに面白さを加えるとしばしばそれが歪んじゃうっていう問題はいろんなところで出てくるのかなと考えていまして。先ほど小林多喜二と埴谷雄高というきわめて政治的な文学者の話をしてくださいましたが、たとえば政治みたいな要素が入ってくると、まさに学的厳密性みたいなものが政治的目的性のために犠牲にされちゃう事態もある気がします。
学問の政治性について
で、そこで思い出されてくるのが熊野純彦という書き手が、廣松渉という政治的な学者のお弟子さんの一人であったことを思い出すんです。おそらくは熊野さんにとっても廣松渉は単なるアカデミシャンではなくて一人の批評家として屹立していたのかなと思うんですけども、私の見立ては合っているでしょうか。
熊野: もうぼく、廣松さんが死んだ歳を超えちゃったので、かえって語りにくいところもあるのですけどね。廣松さんは「批評家」っていうには、やはり文体が「固い」でしょう? 独特なリズムと衝迫力のある文体であることはもちろんだけど。あともう一つ、そういうレトリックでごまかさないっていう断固たる決意もあったのだと思います。
人文系の話に戻りますけど、大学内の研究者にしても、仕事を続けていくのにやっぱり何かモチベーションが必要だと思うのです。ある意味で幸福なことに、廣松さんにとってはそれがもう一貫してはっきりしていて、ぼくなんかは当時から半信半疑っていうか、いや眉に何度も唾つけましたけれども、「哲学は政治の延長であり、自分は本当は革命がやりたいんだ」って仰ってて。少なくとも廣松さん本人にとって、それは強いモチベーションで、そのすべてに同意できるかどうかは別として、やっぱりそれほどね、強いモチベーションと断固たる意志とその持続性を持った人間は、どうしたって魅力的なんです。だから、さっき荒木さんが一般的な形と仰ったように、ある種の政治性は学問にとって危険であるのはそうなんだけど、まずその前提として「学問って最終的に本当に中立的なものなの?」っていうことは当然問題になるし、すごく難しいところです。ただ廣松さんが現に直面していた問題状況は、いってみれば今あまり共有されてないと思うから、現在でいえば、やはり難しいところを抱えこんでいるのは、たとえばジェンダー研究とかがそうでしょうね。それは悪質な形、つまりおよそジェンダー研究に対する単なる反動という形でも問われているし、ジェンダー研究者たちがまさに自分の内的な問題として引き受けざるをえない形でも問われていると思う。本当は、問われている事柄がジェンダー研究の場合は見えやすいっていうだけで、いろいろな領域において実は同型的な問題は問われ続けているのだろうと思います。
荒木: なるほど。いまの話とは直接関係しないんですけども、一瞬だけジェンダーの話が出ました。実はこの本には、おそらくですが、女性は1人しか登場していません。これは大きな欠点だと思ってます。私なりに努力したつもりでしたが、様々な事情から女性の書き手を揃えることはできませんでした。明確に傷だと思います。もし、みなさんが本書についていろんな批評をする機会があるならば、「こういう女性の在野研究者がいるのになんで荒木は見つけないんだ」とか、どんどん批判していただいて構いません。