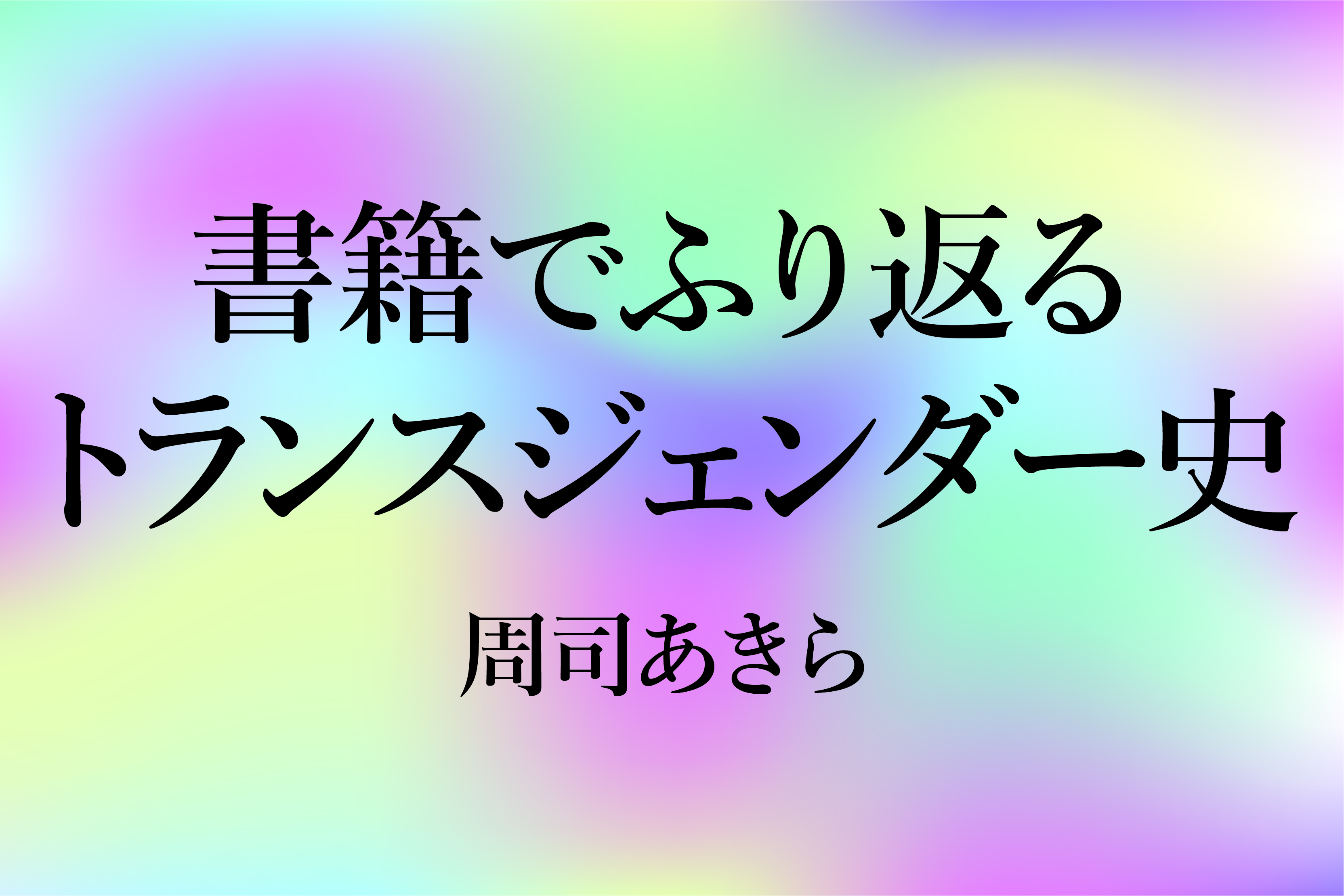書籍でふり返るトランスジェンダー史(周司あきら)
毎年11月20日は「トランスジェンダー追悼の日(Transgender Day of Remembrance)」。1998年に米国で殺害されたトランス女性の追悼行事に由来し、ヘイトクライムや自殺などによって亡くなったトランスジェンダーを悼み、トランスの権利と尊厳について考える日として国際的に知られています。日本でもトランスをめぐる状況が不安定な中でこの日を迎えるにあたり、『埋没した世界 トランスジェンダーふたりの往復書簡』(明石書店)の著者のおひとりである周司あきらさんにご寄稿いただきました。高井ゆと里さんとの共著『トランスジェンダー入門』(集英社新書)でも注目を集める周司さんが、日本語で読める書籍を通してトランスジェンダーの人びとの歩みを紐解きます。
トランスジェンダーの人たちは、昔も今も存在する。これからもそうだ。だが、トランスの人権がこれまで侵害されなかった時代はおそらく存在しない。昨今でも、トランスへの排除言説や暴力は止まない。毎年11月20日は、トランスジェンダー追悼の日である。ヘイトクライムや自死など望まぬかたちで亡くなってしまったトランスの人たちを追悼する。
この記事では、これまでトランスの人たちが歩んできた軌跡を、50冊の書籍を媒介に辿っていく。どんな動きがあったのか、全体的な流れを確認しつつ、いくつかの書籍はそれ単体でのレビューも記していく(なお、見出しの年代はおおよその目安であり、内容に応じて刊行順もバラバラに紹介している)。
もちろん、日本語で読めるトランスジェンダーにまつわる書籍は、ここで紹介するもの以外にも多数ある。書籍にはなっていない物語や活動もある。ふだん顧みられないトランスの生き様や歴史について、あなた自身が探す際に、本記事をお役に立てていただければ光栄である。
1990年代をふり返る
生まれた時に割り当てられた性別から、自分の生きていく社会的・身体的な性別を「変える」ことができる。トランスジェンダーという語が知られるようになり、早いものでは1989年に渡辺恒夫『トランス・ジェンダーの文化 異世界へ越境する知』(勁草書房)が刊行された。また、メンズリブの方面でも名の知られる蔦森樹は、1993年に『男でもなく女でもなく』(勁草書房)を書き残した。現代的な理解とは異なるが、トランス男性に連なる人たちとして、外山ひとみ『MISS・ダンディ 男として生きる女性たち』(1999年、新潮社)も参考になるかもしれない。
渡米して外科手術を受けた虎井まさ衛は、『女から男になったワタシ』(1996年、青弓社)を皮切りに、複数の著作を出している。ミニコミ誌「FTM日本」の記述を元にした『語り継ぐトランスジェンダー史 性同一性障害の現在・過去・未来』(十月舎、2003年)や、サンフランシスコでトランスの仲間と交流した10日間を記録した『トランスジェンダーの仲間たち』(2000年、青弓社)は、当時のトランス男性の置かれた環境を知るために頼りになる2冊だ。
虎井まさ衛『女から男になったワタシ』(1996年、青弓社)
当時主流だった区分にしたがい、性別違和をもつ人々をTV(トランスヴェスタイト)・TG(トランスジェンダー)・TS(トランスセクシュアル)の3つに分けた説明が用いられる。性器も含めて「男体」になることを必要とした虎井は、自身をTSとして記述する。
サンフランシスコとカリフォルニアで過ごした日記、アメリカでの手術の事情、そして日本で埋没しながら(=トランスだと知られずに)トランス男性向けの発信をしようという決意が記されている。
◇
医学的には、「性同一性障害」を正式な医療として扱おうと試みが続く。
吉永みち子『性同一性障害 性転換の朝』(2000年、集英社新書)
日本におけるトランス医療の変遷をノンフィクション作家が追った1冊。1998年に埼玉医科大の原科孝雄教授がFTM(トランスジェンダーの男性)に対する「性転換手術」(今でいう性別適合手術)を公に実施した描写から本書は始まる。診察が不十分なまま男娼に睾丸摘出手術を行ったとして産婦人科医が有罪判決を受けた「ブルーボーイ事件」のち、医師がトランス医療に萎縮してしまってから約30年も経過していた。
本書はブルーボーイ事件の裁判が当時にしては画期的な見解を提示していたにもかかわらず、なぜ日本で長らく性別適合手術がタブー視されたのかを探っていく。医療の整備が着々と進んでいく様子が描かれると同時に、第4章では規範的な女か男をゴールにしないトランスの人の存在も語られる。なお、冒頭の「性同一性」の説明には誤用との指摘もあるので注意されたい。
◇
とはいえ、身体を変えることを望むトランスジェンダーの人たちが現にいる以上、ホルモン投与や外科手術の実施は待ったなしだ。刊行はまだ先になるが、はるな愛『素晴らしき、この人生』(2009年、講談社)や、和田耕治・深町公美子『ペニス・カッター 性同一性障害を救った医師の物語』(2019年、方丈社)を読むとその切実さが伝わる。
2000年代をふり返る
医学的な診断名としての「性同一性障害」が認知されていった。「3年B組金八先生」の第6シーズンで性同一性障害という設定の生徒が登場し、競艇選手の安藤大将(『スカートをはいた少年 こうして私はボクになった』(2002年、ブックマン社))が性別変更したニュースが注目を浴びた。「性同一性障害」が描かれた小説として、藤野千夜『夏の約束』(2000年、講談社)や、東野圭吾『片想い』(2004年、文藝春秋)も知られる。
2003年7月には「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」が議員立法で成立し、翌2004年7月に施行された。厳しい要件のすべてをクリアすれば、戸籍上の性別を変更できるという内容だ。
特例法制定前後の動きについては、当時ロビー活動をしていた虎井まさ衛『男の戸籍をください』(2003年、毎日新聞社)や、上川あや『変えてゆく勇気 「性同一性障害」の私から』(2007年、岩波新書)が参考になる。特例法の解説は、南野知惠子・元参院議員『解説 性同一性障害性別取扱特例法』(2004年、日本加除出版)に記される。
だが、特例法を受けて、当事者のコミュニティに衝撃が走った。特例法の要件を満たすような「真のトランスジェンダー」であるには、手術をしなければならないのか?子どもがいてはダメなのか?という疑問が浮かび、まるで当事者間に序列が作られてしまったようだった。規範的な「女」や「男」を演じるのはイヤだ、という叫びは、例えば関西のサークル・ROSによる、迫共・今将人『トランスがわかりません!! ゆらぎのセクシュアリティ考』(2007年、アットワークス)に込められている。
米沢泉美編『トランスジェンダリズム宣言 性別の自己決定権と多様な性の肯定』(2003年、社会批評社)
トランスジェンダーの直面する社会的な問題、ガイドラインの功罪、メディアの影響、歴史など幅広くまとめた1冊。単なる医学上の診断名である「性同一性障害」に対し、トランスジェンダーという語は性別についての社会的・文化的・身体的な概念も含まれており、「生」を説明するには〈トランスジェンダー〉を使うしかない、と米沢は述べる。
トランスジェンダリズムという語は、歴史的にはアメリカで生まれ、日本でも90年代半ばには用いられている。松尾寿子『トランスジェンダリズム 性別の彼岸』(1997年、世織書房)という本でもタイトルになった。
『トランスジェンダリズム宣言』の中では、トランスジェンダリズムは「デフォルトセッティングからの自由、そして社会とのかかわりの中での自己肯定という回路をもって、トランスジェンダーの社会生活・自己主張を行う思考、感覚、生き様」を指す。他者に妨害されない自己決定権(プライバシー権の一部)を持つものとして、個人の性別を捉えようとする。
なお昨今では、「トランスジェンダリズム=性自認至上主義」とみなし、性自認を主張しさえすれば男女で分けられたスペースを自由に行き来できるとする自分勝手な主張、と歪曲されている節もあるが、トランスコミュニティが用いてきた言葉の歴史とは異なるので注意。
◇
田中玲『トランスジェンダー・フェミニズム』(2006年、インパクト出版会)
フェミニズムは「女」のもの、と認識している人も多いかもしれない。しかし著者は、男女二分法の無意味さを浮き彫りにするトランスジェンダーが、フェミニズムに与えられる可能性を語る。
著者はポリガミーでパンセクシュアルまたはポリセクシュアルで、FTM系トランスジェンダーである。セクシュアリティの多様性や戸籍制度への批判が本書にふんだんに盛り込まれている。
◇
ほか、トランスの人々のさまざまな生き様が書籍に書き残されてきた。針間克己・相馬佐江子『性同一性障害30人のカミングアウト』(2004年、双葉社)や、そこでのトランスの人々にまつわる調査を整理しつつ分析を試みた佐倉智美『性同一性障害の社会学』(2006年、現代書館)、あるいはブログが元になった能町みね子『オカマだけどOLやってます。』(2006年、竹書房)などがある。当時のアメリカでのトランスの位置が概観できるパトリック・カリフィアほか/石倉由・吉池祥子訳『セックス・チェンジズ トランスジェンダーの政治学』(2005年、作品社)も有名だ。
日本でも、自伝やエッセイが立て続けに刊行された。
山本ヒカル『ニューボーイ』(2003年、文芸社)
生まれたときから自分が男だと思っていた著者は、そうではない現実に直面し、早く本来の自分の姿に戻りたいと願っていた。初めての仕事に選んだのは、オナべのショーパブ。オナべのお店と一言でいっても、店舗や土地柄によって求められる像が違うのは興味深い。
やがてニューハーフのダンサーと惹かれ合い、結婚する。戸籍の性別変更が未整備だった当時、外見と戸籍上の性別がちぐはぐな二人の「逆転結婚」に、役所の人は驚き、興奮したそう。
◇
椿姫彩菜『わたし、男子校出身です。』(2008年、ポプラ社)
熱心な母親の教育方針で、小学校の半ばから私立の男子校に通うことになった著者の自叙伝。実は、トランスのなかには、保護者からの「矯正」目的もあって男子校や女子校に進学する者が意外と多い。馴染めなかった男子校では、文化祭でヒロイン役を演じたことが転機となり、「女」として過ごせるようになったという。そして共学の大学に進学後、「性同一性障害特例法が可決」とのニュースを知り、戸籍の性別が変えられることを知る。
「性同一性障害」も「ニューハーフ」も自身に関係のある言葉とは思えなかったものの、新宿のクラブメモリーで働きながら店舗の人たちの力を借り、手術へこぎつけた。本書は台湾でも翻訳が出版、マンガ化もされている。
◇
2010年代をふり返る
「かわいそうな病気の人」のイメージが付与された性同一性障害があるていど認知された後、それに対して都市部を中心としたトランスコミュニティ内部から批判も起きた。さらに2010年代半ばごろから、性的マイノリティを包括するカテゴリーとして「LGBT」の運動が広がり、トランスジェンダー(T)もその中に含めて語られる機会が増えた。
遠藤まめたは、『先生と親のための LGBTガイド もしあなたがカミングアウトされたなら』(2016年、合同出版)をはじめとして、いくつもの著作を出している。
トランス女性的な人々に連なる書籍として、三橋順子『女装と日本人』(2008年、講談社現代新書)や、川本直『「男の娘」たち』(2014年、河出書房新社)も挙げられる。邦訳は2023年刊行だが、原著の初版が2007年に出ている、ジュリア・セラーノ/矢部文訳『ウィッピング・ガール トランスの女性はなぜ叩かれるのか』(2023年、サウザンブックス)では、トランス女性がトランスミソジニーという複合的な差別の的にされていることが問題提起されている。
針間克己『性別違和・性別不合へ 性同一性障害から何が変わったか』(2019年、緑風出版)
「性同一性障害」は、医学用語としてはもはや消滅した。長らくトランスジェンダー的な人々は、精神疾患をもつ者として病理化されてきたが、国際的な診断基準や分類の変更によって脱病理化されたのだ。
後継概念としては、アメリカ精神医学会の発行するDSM-5における「性別違和」、世界保健機関の作成するICD-11における「性別不合」がある。これらの概念は、男女いずれかの「反対の性別」になりたがっているわけではないが、性別に違和感をもつ人々も含みうる概念として解釈される。長年トランス医療に携わってきた精神科医の著者が、目まぐるしい概念の変化について解説した1冊だ。
◇
世間的にはわかりやすさが求められる一方で、2010年代後半から2020年代にかけて、これまで取りこぼされてきた内容を書きとめる著作も相次いで刊行された。
例えば、海外での手術の手配・付き添いなどを担うアテンド業者に焦点を当てた本に、伊藤元輝『性転師「性転換ビジネス」に従事する日本人たち』(2020年、柏書房)がある。豊富な研究に基づく、佐々木掌子『トランスジェンダーの心理学 多様な性同一性の発達メカニズムと形成』(2017年、晃洋書房)も刊行された。
また、トランス男性が戸籍上の「男」になれても「父」にはなれなかったために最高裁まで判断が持ちこされた過程は、前田良『パパは女子高生だった 女の子だったパパが最高裁で逆転勝訴してつかんだ家族のカタチ』(2019年、明石書店)で知ることができる。2006年に起きた手術での医療事故とその裁判については、10年以上の時を経て刊行された、吉野靫『誰かの理想を生きられはしない とり残された者のためのトランスジェンダー史』(2020年、青土社)の中で語られる。
男女いずれかのバイナリーな性別にぴったり自身を当てはめるわけではない人々の状況をまとめた、エリス・ヤング/上田勢子訳『ノンバイナリーがわかる本 heでもsheでもない、theyたちのこと』(2021年、明石書店)や、マイカ・ラジャノフ/スコット・ドウェイン編/山本晶子訳『ノンバイナリー 30人が語るジェンダーとアイデンティティ』(2023年、明石書店)も翻訳された。
2020年代をふり返る
トランスジェンダーに対するヘイトやバックラッシュが、SNSを媒体に拡散されるようになった。バックラッシュとは通常、社会的マイノリティが権利回復して平等に近づこうとしたことへの反動として起こりうるが、トランスジェンダーに関してはほとんど何らの権利も得ていないまま、バックラッシュだけが流れ込んできたともいえる。そうして否応なく、トランスジェンダーが政治的集団として声を聴かれる存在にされていった。
ショーン・フェイ/高井ゆと里訳『トランスジェンダー問題 議論は正義のために』(2022年、明石書店)
トランスバッシングが過激化する英国で「議論」のネタにされるのは、トランスの人々が本当に直面する数多の「問題」とはかけ離れている。貧困、学校からの排除、家庭内暴力、医療の不整備、セックスワークへの偏見、刑務所、可視化の政治……。英国の悲惨な状況が、日本においても決して他人事でない様子に緊張感が走る。それでも本書は、孤立していたトランスジェンダーたちに希望を与える1冊だ。赤い表紙が目印。
◇
周司あきら・高井ゆと里『トランスジェンダー入門』(2023年、集英社新書)
「トランスジェンダーって何?」「性同一性を説明してほしい」「トランス男性って“女らしさが嫌な女”とどう違うの?」「フェミニズムはトランス女性と“対立”しているのでは?」……など、誰かに聞く前に一人で読んでもらいたい、最初の1冊。個別の領域で語られることの多かった医療・法律・メディア表象・差別事例などがまとまった、さながらお子様ランチのような中身である。
◇
青本柚紀・高島鈴・水上文編『われらはすでに共にある 反トランス差別ブックレット』(2023年、現代書館)
情報が増えれば、よりトランスジェンダーのことが「わかる」ようになるのだろうか?いや、そんなことはない。私たちが何気なく取得するトランスの情報には、最初からトランス排除的な背景が組み込まれていることを忘れてはならない。バラバラな個人が生きている現実にいつでも立ち返ろう。2022年11月にZINE版が出版されたのち、翌2023年に現代書館から増補版の商業出版に至った。増補版には、読みやすい長さのエッセイ19本、ブックガイド8本、映画ガイドが含まれる。トランスの人々は、未来から突如現れる侵略者ではない。そのことがわかるだろう。
◇
ほか、トランスジェンダーの当事者らが執筆した物語は、決して十分ではないものの、着実に増えている。
トランス男性の著作の一部を紹介しよう。例えば、YouTuberの木本奏太のエッセイ『元女子、現男子。忘れたい過去もある。けど、それを含めて僕だと気づいた。』(2022年、KADOKAWA)や、杉山文野『ダブルハッピネス』(2006年、講談社、2009年に文庫化)や『元女子高生、パパになる』(2020年、文藝春秋)などがある。また、性別移行後の「男」としての境遇や考察も語られる著作には、トーマス・ページ・マクビー/小林玲子訳『トランスジェンダーの私がボクサーになるまで』(2019年、毎日新聞出版)や勝又栄政『親子は生きづらい “トランスジェンダー”をめぐる家族の物語』(2022年、金剛出版)がある。トランス男性と男性学の可能性を探る著作に、周司あきら『トランス男性による トランスジェンダー男性学』(2021年、大月書店)がある。哲学者ポール・B. プレシアドの著作は『カウンターセックス宣言』(藤本一勇訳、2022年、法政大学出版局)をはじめとして邦訳の刊行が続いている。
強いていうならトランス男性とノンバイナリー(無性)に該当する二人による手紙は、五月あかり・周司あきら『埋没した世界 トランスジェンダーふたりの往復書簡』(2023年、明石書店)という書籍になった。シスジェンダー(トランスではない人)のわかりやすさを考慮しないで自由に交わされる言葉の応酬は、まだまだ貴重だ。
トランスジェンダーの人の年齢や家族形成にも、従来より多様さが見られるようになった。例えば、エリンマクレディ・もりたみどり『エリンとみどり ジェンダーと新しい家族の形』(2022年、天夢人)や、杉山文野『3人で親になってみた ママとパパ、ときどきゴンちゃん』(2021年、毎日新聞出版)などがある。
小嶋小百合『還暦越えトランスジェンダーの「まだこれから」 女性として生きるために通称名で暮らすことにこだわった日々と、67歳で性別適合手術を受け戸籍を変更するまでの10年の軌跡』(2023年、文芸社)
現代は、人類史上初めてトランスジェンダーが長生きするようになった時代といっても過言ではない(たいていは殺されたり、シスジェンダー的な生き方を強制されたりしてしまうため)。著者は67歳で性別適合手術を受ける。手術を受けた最高齢ではないそうだが、日記スタイルで綴られる本書において手術そのものの描写があっけないほど早く終わる点も、時代の流れを感じる。
それ以上に豊富に語られるのは、通称名を使えるように個々のサービス提供者に問い合わせて辛抱強く交渉することや、手術後の尿意との戦いがいかに大変かというエピソードなのだ。「私が一言いうくらいで性別欄が変わるのだから、そもそも何のために性別欄が残されていたの?」との疑問には、心底同意する。
◇
以上で、簡単なふり返りを終える。
筆者の価値判断は最小限に抑えたつもりだが、おそらく達せられてはいない。トランスジェンダー関連の本は、自費出版で少数部しか発行されていないものや、現在では入手困難なものも多い。もし運よく出会ったら、それを語り継ぎ、あなた自身で考えることも大事な行いになるはずだ。そうした展開を望みたい。